��l�� �̂��Ă�Ă�n�F��
�i�v�l�Ɗo���j
��
��
�͂��߂� ���������������������������������������������� 1
����
�v�l�̍\�� ������������������������������������ 3
��P�� �l����Ƃ������� ���������������������������� 3
�P�D����Ԃƌ���� ������������������������ 3
�Q�D�v�l�̗��j�I�Ӗ� ���������������������� 6
�R�D�����F���̖� �������������������������� 12
�S�D������ �������������������������������� 15
��Q�� �v�l�n�} ������������������������������������ 21
�P�D�v�l�̕��� ���������������������������� 21
�Q�D���O�v�l ������������������������������ 22
�R�D��O�v�l ������������������������������ 30
�@��_���v�l ������������������������ 33
�i����v�l�j���������������������� 33
�i�_��I�v�l�E�@���I�v�l�j�������� 36
�i�����I�v�l�E�|�p�I�v�l�j�������� 39
�A�v�_���v�l ������������������������ 46
�i�����E�F���ӎ��j���������������� 46
�S�D�g�̓I�v�l ���������������������������� 51
�i�K���I�v�l�j�������������������� 52
�i�g�̎v�l�j���������������������� 57
�i�����o�v�l�j�������������������� 61
�i���I�v�l�j���������������������� 67
��R�� �v�l�̍\�� ���������������������������������� 73
����
�o�� ������������������������������������������ 75
��P�� �ӎu ���������������������������������������� 75
��Q�� �����E���� ���������������������������������� 78
�łR�� �C�Â� �������������������������������������� 79
��S�� ���_ ���������������������������������������� 89
�P�D�����F���ӎ� �������������������������� 90
�Q�D���o�����_ ���������������������������� 91
�R�D�����o���g�̓I ������������������������ 95
�S�D�o�������z ���������������������������� 95
��O��
�ϏƎ� �������������������������������������� 101
��P�� �����̎v�l�ƊϏƎ� ���������������������� 101
��Q�� �ϏƎ҂ƎЉ� ������������������������������ 105
�P�D�ϏƎ҂Ƒ��Ҙ_ ������������������������ 105
�Q�D�ϊv������������������������������������ 110
�̂��Ă�Ă�n�F���_���I����ɂ������Ą����������������� 115
�@
�͂��߂�
�@�@�l�Ԃ͍l����B����͒n����ɂ��ސ����̒��ŁA�l�Ԃ��ł������Ɏ������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@���̐����Ɏv�l���F�߂��Ȃ��ƌ����̂ł͂Ȃ��B����������琶�������̎v�l�p�^�[���́A�T�˖{�\�ɒ����������̂Ƃ��ė��������B���Ȃ킿�����I�A���ۓI�Ȑ����������̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ��o����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�l�Ԃ̎v�l�́A���̖{�\���͂邩�ɉz�����̈�ɂ܂ōL�����Đ��藧���Ă���B�{�\�������Ƃ��ĂƂ炦��Ȃ�A�l�Ԃ͎����̂͂邩���Ȃ��ɁA�����Ȃ�v�l��Ԃ����グ��̂ł���B���͂��������ԂƌĂB�i�̂��Ă�Ă�n�F����j
�@����ɂ��Ă��A����̍��ׂȂ��Ƃ���A�d��Ȍ��S�Ɏ���܂ŁA���ׂĎ��B�̐����͍l����Ƃ������Ƃ�y��ɂ��Đ��藧���Ă���B�Ȋw�̐i���╶���̔��B�͌����܂ł��Ȃ��A���퐶�����̂��̂��l����Ƃ����\�͂̐��ݏo�������ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�u�l���v�́A���B�̒��œ���I�ɓ����Ă���B����͌`�Ƃ��Ď��o�����Ƃ͏o���Ȃ����A�m���Ɏ��B���̂��̂Ƃ��Ă���̂ł���B�������v�l�́A�����Ȃ�������l�X�Ȃ��̂����o���Đ��E�ɐV���ȕ�����t��������B�������̂��������̂��A���B���m�鎖�̏o���邷�ׂĂ̐��E�́A�v�l�ɂ���č��グ��ꂽ�ƌ����Ă����̂ł���B
�@���������̎v�l�̍��o�����E�́A�u���v�̒������ɑ��݂��A���̒N�̂��̂ł��Ȃ������g�̔F���Ƃ��Ă݈̂Ӗ������B�܂��Ɏ���Ԃ��̂��̂����o���̂ł���B
�@��̂��̂悤�Ȏv�l�͂ǂ̂悤�Ȏd�g�݂ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł��낤���B
�����Ȃ��Ƃ��납��l�X�Ȏ����v�����A�l��������̂͂ǂ����ĂȂ̂��낤���B�����ɂǂ�ȈӖ����B����Ă���̂��납�B�܂��@���䂦�ɓˑR�j���[�g����A�C���V���^�C���̂悤�ɕ��G�Ș_�����v�����̂��낤�B
�@�ǂ����Ď��Ƃ������̂������ɂ��ėl�X�Ȏ����l���Ă���̂��낤�B���������͂����ȊO�ɂ͂��Ȃ��B���̎v�l�����Ȃ̂��A�����l���Ă���̂��A���͂ǂ����đ��l�ł͂Ȃ����Ȃ̂��B�ǂ����Ď��ȊO�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂��B
�@������ɂ��Ă����̖��́A�l�ԑ��݂̍ł��[�������ɂ�������Ă��邾�낤�B
�@�l�ԂɂƂ��čl����Ƃ������Ƃ͉��Ȃ̂��B���͂܂������ɏœ_�Ă��c�_��i�߂Ă݂����B��������l�Ԃ̂���ɐ[���{���������ė���K���ł���B
�@�܂��������̖ʂ���v�l�ɂ��Č��A�v�l�ɂ��Ă̂Ƃ炦�����m���Ȃ��̂ɂ��āA�Ō�ɂ͍l�������ݏo�����\���ɔ����Ă݂����ł���B
���́@�v�l�̍\��
��P�� �l����Ƃ�������
�@
�P.����Ԃƌ����
�@����Ԃƌ���ԂƂ����T�O�́A�{����Q���ŏڂ������グ�����A�����ł�����x�ȒP�Ɏ��グ�Ă��������B�ƌ����̂��A�{�_��i�߂�ɓ������Ă͎���ԂƂ����l��������Ϗd�v�ɂȂ��Ă��邩��ł���B
�@���݂��̂��́A���邪�܂܂ɂ�����́A�����^���ƌĂԁB
�@���B�l�Ԃ͂��̐^���̂������ɑ��݂��Ă���B�����܂��^���ƌĂ˂Ȃ�Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�^���́A��������̂܂܊ۂ��ƔF�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B�^���͖����ł���A�F���͗L���ł���B�����ɐ^���ƔF���̉z�����Ȃ��ǂ�����B
�@�F���ɂ͌��t���K�v�ł���B�Ƃ��낪�^���ɑ��Č��t���g���Ƃ���ɐ^���͌��t�Ɍ��肳��Ă��܂����낤�B
�@�����������t�Ƃ��������Ȕ��ɖ����̍L��������^�����������߂�悤�Ȃ��̂ŁA�^���͂Ƃ���ɒ������Ă��܂��̂��B���Ƃ����t�̈Ӗ����L���悤���A���𑝂₻�����A���ꂪ���ς�炸���ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�t�ɐ^�����������Ȃ��悤�ɕǂ���蕥���Ă��܂��A����͂��͂┠�ł͂Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿���t�͎�����̂ł���B
�@���̂悤�Ɏ��B�͌����ĔF���ɂ���Đ^�������ނ��Ƃ͏o���Ȃ��B�������̓I�Ɍ��Ă݂悤�B
�@�u�Ԃ��炢�Ă���v�Ƃ����F��������Ƃ��悤�B���͏t�̖쌴�ɂ��ĐS�n�悢���̒��ł��̉ԁA�^���|�|�����Ă���B
�@���̂Ƃ����̔F���͂��̌��i�ƁA���̐S�̏�Ԃ̑����I�Ȃ܂Ƃ܂�̒��ɂ���B�킽���̐S�����邭��]�ɖ����Ă���Ȃ�A���̉Ԃ͌���P���Č����邾�낤���A���]�̒��Ō���Ԃ͑��ꂵ�����̂̂悤�ɍ炢�Ă��邩������Ȃ��B
�@���������̔F���͂ǂ�����^���ł͂Ȃ��B�^���͂����ɂ����炢�Ă��邠��̂܂܂̎p�̒��ɂ����āA����ȊO�ɂ͂Ȃ��̂ł���B��������Ԃ��������o���Ă��̉Ԃ����ۂɑ��݂��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��̂ł���B���̉Ԃ̑��݂́A�y���C��A���␅�ȂǁA�ۂ��Ǝ��R�̒��ɂ���̂ł����āA�����Ă�������藣�����Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B
�@���Ƃ��Ԃ�E�ݎ���Ď����̂��̂ɏo����ƌ������Ƃ��Ă��A���ꂪ�^������Ԃ��������o�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B���̉Ԃ��y�̏�ɂ��낤���A��̒��ɂ��낤���A���ꂪ�P�̂ő��݂��Ă���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�Ԃ͐��E�ƈ�̂ɂȂ鎖�ň�܂�A�����ɑ��݂��邾���Ŏ���̋�Ԃ������L���Ă���ƍl�����邩��ł���B�܂�Ԃ͖��炩�ɂ��̐��E�̉e���̌��ɂ���B��ԂƉԂƁA�ǂ��炩����������Ă����݂��邱�Ƃ̏o���Ȃ���̂̂��̂Ƃ��Đ��E�͌���Ă���̂��B
�@���������^���Ƃ́A�܂��ɂ��̐��E���̂��̂��w���Ă���B���E��K���ɕ���������A�ȗ������肷��̂ł͂Ȃ��A�藣���Ȃ����̂͐藣���Ȃ����̂Ƃ��āA���邪�܂܂̐��E��^���ƌĂԂ̂ł���B
�@���̐^���ɑ��āA�Ԃ��炢�Ă���Ƃ����F���́A�܂��ɉԂ̎p����������đ���w�i�ɉ�����邱�Ƃŏ��߂Đ��藧�B�܂莄�B�͐^�����敪���ďے��I�ɕ������Ƃ炦��ȊO�ɐ��E���Ƃ炦����@�͂Ȃ��̂��B�܂�F���ɂ���ĂƂ炦��ꂽ���E�́A���ꎩ�̂��łɐ^���ł͂Ȃ����ɂȂ�B
���͂��̔F���łƂ炦��ꂽ���E������ԂƌĂB�����Ď��B�����Ă��邱�̐��E�́A���ׂĎ���Ԃɂق��Ȃ�Ȃ��Ǝ咣����̂ł���B
�@���B�͌����Ď����̍��o������Ԃ���o�邱�Ƃ��ł��Ȃ����A���l�̎���Ԃɓ����čs�����Ƃ��ł��Ȃ��B���B�͊��S�Ɂu���v�̒��ŕ����ꂽ���E�ɐ����Ă���̂ł���B
�@����A�^���̐��E������ԂƌĂԁB
�@����Ԃ͎��B���ǂ����Ă����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��^�����̂��̂̐��E�ł���B����͂�����̑��݂ł���A�������敪���邱�Ƃ������Ȃ����邪�܂܂̐��E�ł���B�����܂ł��Ȃ�����Ԃ͎��B�̈������荞�S��I�ȑ��݂Ƃ��Ă���̂��B
�@���x���q�ׂė����悤�ɁA���B�͂��ꎩ�̂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����m�낤�Ƃ���A�F���ɂ���Đ���ꂽ�����������Ԃ͎���ł��܂������Ȃ�����ł���B
�@��������Ԃ𗝉����悤�Ƃ���Ȃ�A���E�ƈ�̂ƂȂ��Ă��鎩���̑��݂�S��I�Ȋ��o�łƂ炦�邵���Ȃ��B���ꂪ����ΐl�ԂƐ^���̗B��̐ړ_���ƍl������̂ł���B
�@���������Đl�Ԃ͐^�����Ƃ炦�邱�Ƃ��o����̂��Ƃ������́A�����炭�A�Ƃ炦��ƌ��������̔c���ł͉������Ȃ����낤�B�^���͂Ƃ炦��̂ł͂Ȃ��A�������̒��ɓ����čs�����Ƃł����������邱�Ƃ̏o���Ȃ����݂Ȃ̂ł���B
�@�����炭���B�͂��Ƃ��Ƃ��炱�̌���Ԃ��̂��̂Ƃ��Ă̑��݂ł������̂��B�Ƃ��낪�����ɁA�v�l�̗͂Ŏ���ԂƂ��������̂̐��E�ݏo�����̂��l�ԂȂ̂ł���B���̂��Ƃ͂��ꂩ��̋c�_�̒��ŏd�v�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ邾�낤�B
�@����Ԃƌ���Ԃ̊T�O���܂����̂悤�ɂƂ炦��������ŁA�l����Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂����̐��̂ɔ����čs�����Ƃɂ��悤�B
�Q�D�v�l�̗��j�I�Ӗ�
�@�l����Ƃ������Ƃ́A�s�ׂł���Ƃ�������B����͐l�Ԃ̓��ʂ������Ƃ��ɁA����Ԃ̒��Ŏv�l�̉ʂ����������\���I�ł���A�s�ׂ��̂��̂ƍl�����邩��ł���B
�@���_�A�l���̂��ׂĂ��O�ɏo�Ď��ۂ̍s�ׂɂȂ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B������������O�Ɍ������ĕ\�����邩�A���Ȃ����ɂ�����炸�A�v�l�͎���Ԃɓ�����^����B����Ԃ̒��Ŏv�l�͂܂��ɍs�ׂ��̂��̂Ȃ̂ł���B���̈Ӗ��Ŏv�l�͐��_�I�s�ׂƌ����邾�낤�B�@����l�i�A�v�z�M���ȂǁA�l�ԂƂ��Ă̊�{�I�ȏ������v�l�̓����ɂ���Đ��ݏo�����B
�@���_�l�i���v�l�̕��������肷��Ƃ������ʂ����邪�A����͓I�Ȍ���ɂ����Ȃ��B�ꎟ�I�ɂ͎Љ�̗l�X�ȋ@�\�̒��Ŏv�l�������A��������l�i�����ݏo�����̂ł���B
�@�������玩�䂪�K�肳��A�l�������肳���B�l�i�ɔ����āA�l�X�ȋ`�����ƖڕW�����ݏo����A�l�͎Љ�̒��ň�̈ʒu��B�����Ɉ�l�̐l�Ԃ���������̂��B�l�Ƃ��Ă̍s�ׂ͂��ׂĂ������琶�ݏo����Ă����ł���B
�v�l�͎��B�̐S��l�X�ɕϓ�������B�~�����A�Җ]���A��Ɗ�сA�s���⋰��ɁA�S����藧�Ăčs���̂ł���B�܂��Ɏ���Ԃ͎v�l�ɂ���ė������Ă���ƌ����邾�낤�B
�@�u�l����v�ƌ������Ƃ͂��̂悤�Ɏ��B�̐����S�ʂ��x�z���Ă���̂ł���B���邢�͂���͐S���̂��̂ƌ����邩���m��Ȃ��B������ɂ��Ă��v�l�͐l�ԓI�s���̌��_�Ȃ̂ł���B
�@�v�l�̔\�͂��Ȃ���ΐl�Ԃ͖쐶�̓����ɋt�߂肷�邵���Ȃ����낤�B���̍l�������猾���A�v�l�͓ˑR�l�Ԃɗ^����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����̐i���̌��ʂƂ��Đ��ݏo����ė����ƌ��邱�Ƃ��o����B
�@����Ɍ����A�l�Ԃ̂��̍l����Ƃ����\�͂��܂��F���̗��j�̒��Ɉʒu�t����ׂ��Ȃ̂ł���B
�@�̂��Ă�Ă�n�F���̓X�P�[���̌n�𒌂Ƃ������E�������B���̐��E�ς��猩��A�F���͕��Ƌ�Ԃ��琬�藧���Ă���Ƃ������Ƃ�����߂ė��̓I�ɔc���ł����̂ł������B
�@�F���͂�����̋�Ԃ̒��ɁA�ɑ傩��ɏ��Ɏ��镨���̂����܂肪�A�����Ԃ悤�Ȍ`�ő��݂��Ă���B�傫�Ȑ��E�̒��ɏ����Ȑ��E������A���̏����Ȑ��E�̒��ɂ́A����ɏ����Ȑ��E�������ɍL�����Ă���B���q���W�܂��Ĉ�̓V�̂�����Ă���悤�ɁA��̋�Ԃ̒��ŏ����ȃX�P�[���̕������݂͌��Ɉ����������傫�ȂP�Ȃ鑶�݂����낤�Ƃ��Ă���B����Ɍ��q�̒��ɂ͏����ȃX�P�[���̐��E�������āA�����ɑ��݂��闱�q���݂��Ɉ����������q�Ƃ����P�Ȃ鑶�݂������Ă���̂��B
�@�̂��Ă�Ă�n�F���͂��̂悤�ȍ\���������ɘA�Ȃ��Ă���X�P�[�����������E�Ƃ��ė����o�����̂ł���B�@���̉F���ς̉��ɁA���́A�l�Ԃ̐g�̂��܂����̏W�������P�Ȃ鑶�݂ł���A�ł����G�ȁA���̐��E�ɂ�����ō��̍\�������Ƃ����̂ł���B�����Đl�Ԃ̈ӎ��͋�Ԃɑ�����G�l���M�[�ł���ƒf�肵���̂������B
�@�l�Ԃ͕��Ƃ��Ă݂̍���ƁA�S�Ƃ��Ă̑��݂Ƃ����I�ȍ\���������Ă��邪�A����͕��Ƌ�ԂƂ����F���̍����I�ȍ\�����̂��̂ɍ������Ă����̂ł���B
�@���̊ϓ_����A�v�l�̐��ݏo���ꂽ���j��U��Ԃ��Ă݂�Ǝ��̂悤�Ɏ������Ƃ��o����B
�@�F�������܂ꂽ�Ƃ��A�����ɂ͂�����Ԃ��������݂����B��ԂƂ̓G�l���M�[�̏�Ƃ��čl�����邪�A�����ł̃G�l���M�[���z�͊��S�ɋψ�œ����̂��̂ł��������낤�B
�@���E�͕��Ƌ�Ԃ���o���Ă���ƌ����̂����B�̊�{�I�ȍl�����ł��������A�����ȃG�l���M�[��Ԃɂ͕��������������Ƃ��o���Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A�̂��Ă�Ă�n�F���_����ȒP�ɏؖ����邱�Ƃ��o����B�i�ؖ��͍������߂Ď����j
�@�ώ��̃G�l���M�[�̏�͖��̋�ԂƂ��Ă����ɂ��������̌��������Ȃ������B�����Ō������Ƃ́A�������݂��Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���͂����X�P�[���̌n�̖����̂��Ȃ��ɂ܂ʼn�������Ď��B�ɂ͔F���o���Ȃ��ƌ����Ӗ��ł���B
�@�F���s�\�Ȕ����X�P�[���̔ޕ��ŁA���ƕ��͈�l�̊W�������������E�͖��Ƃ��������悤�̂Ȃ����݂̐��E�������̂ł���B
�@�����ł͏d�w�I�ȃX�P�[���̐��E���܂����R���܂�Ă��Ȃ������ɂ������Ȃ��B
�@���������������̐��E�́A���B�l�Ԃ̘_���ł͋L�q�ł��Ȃ��B�܂�m�蓾�Ȃ��Ƃ������Ƃ��܂��Ƃ炦�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ƌ����̂��A���B�̂��̍�Ƃ��F���ɊO�Ȃ�Ȃ�����ł���B
�@�F���͂��łɏq�ׂ��悤�ɐ^�������̂܂܂łƂ炦�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�^���͏�ɋ敪���ĔF�����ꂽ���̊O���ɓ���čs���̂��B�@���̈Ӗ��ŁA�F���̎n�܂�͏�Ɏ��B�̔F���̊O�ɂ���ƌ����悤�B���̊O������͂��^�����ċώ��ȃG�l���M�[�̏ꂪ�h�炬�n�߂�̂ł���B
�@�₪�ċψ�ł��������ƕ��̊W���}���ɓ����o���B�Ⴆ�Ηד��m�̕��̊W�����������܂�A�t�ɑa���ɂȂ镨�ƕ��̊W�����܂�Ă��邾�낤�B�����͓����ɑS�F���I�Ɍ����B�F����Ԃɑa���������̂��B�l�X�ȊW�����ݏo���ꕨ�ƕ������������茋�ѕt���������肷��悤�ɂȂ�B�G�l���M�[�̋�����Ԃ͏k�܂�A���ƕ����W�������A��̉�����B�ア��Ԃ́A�W���������̂ƕ��̂Ƃ̊ԂɂЂ낪��A���B������Ɍ���F����Ԃ̂悤�ɁA���̂��ׂ��ԂƂȂ�B������f���q�����ݏo���ꂽ�̂��B
�@����͂܂������ɁA�X�P�[���̎������ݏo���ꂽ���Ƃ����Ӗ�����B�̂��Ă�Ă�n�F�����猩��A�f���q��V�̂͒P�ɃX�P�[���̏ꂪ�Ⴄ�����ŁA������������̌����I���݂ł������B�܂�f���q�����ݏo���ꂽ�ƌ������Ƃ́A���̏�ʂ̏�ɓV�̂����ݏo����Ă��邱�ƂɂȂ�A����ɂ��̓V�̂��W�ς��Ă���ʂ̏������ƌ����悤�ɁA�̂��Ă�Ă�n�F���̎厲�ł���X�P�[���̌n���o������̂ł���B
�@���̂悤�Ɏ��B�ɂ͒m�蓾�Ȃ��_�̈ꌂ�ɂ���āA�قƂ�Ǐu�ԓI�Ɏ��B�̉F�������ݏo���ꂽ�̂ł���B���邢�͂��̈ꌂ�ɂ���āA�^���͔F���̒��ɉF���Ƃ����`��\�����Ƃ������邾�낤�B
�@�܂��ώ��Ƃ������̐��E�ɕs�ύt�����܂�G�l���M�[������n�߂�B���͐g�����̂ł��Ȃ����肵�������F�����玩�R�n�߂�B���ꂪ���̒P�ʂƍl������f���q�̔����������̂ł���B
�@�ώ��̈��肪�j����ƁA�����I�ɉF���̕s���艻���i�݁A�f���q�����܂�A����ɑf���q���m���W�����т����Č��q�ݏo�����낤�B���������f���q�Ԃ̋�Ԃ̓G�l���M�[�����܂�A�ی������k�܂�B�����Ɉ�̉�i�P�Ȃ鑶�݁j�����o���B���ꂪ���q�ł���B
�@�F����ԂɈ�̉����ƁA���̂P�Ȃ鑶�݂͍X�ɂ��̒��ԂƗl�X�ȊW�����сA���傫�ȋ�Ԃɑa���̔g���ݏo���B���������A���ꂠ���čX�ɍ����̂P�Ȃ鑶�݂��F���Ɍ����̂ł���B
���q�͕��q�ݏo���A���q�͂���ɕ��G�ȍ����q�ݏo���B���s���ɂ���g�ݍ��킹�̒����獂���q�̌����������A�₪�ăA�~�m�_��c�m�`����������čs�����낤�B�����ƌĂ�镨�������܂ꂽ�̂��B
�@���肪�j��ꂽ�F���͂��̂悤�ɁA���X�Ƃ��傫�ȂP�Ȃ鑶�݂���葱���A�Ăш���悤�Ɠ����čs���B���̃G�l���M�[�����S���E�����グ�Ă��錹�Ǝ��͍l����̂ł���B�@
�@���̉F���̉^���́A���܂ꂽ�����ɓ��̂�^���n�߂�B�����͂܂��ɂ��̉F���̉^�����̂��̂̌���Ƃ��Đ�������̂ł���B��������肳���悤�Ƃ��ĐV��ӂ��J��Ԃ��A�܂��ɂ��̕s���肳��Ƃɂ��Ă�蕡�G�ȑg�D�����グ�čs���̂��B���̋Ɍ��Ɏ����Đ����͂��ɓ��]�����B���]���琶�܂��G�l���M�[�͒P�Ȃ镨�ƕ��̊W���琶�ݏo�������̂Ɏ~�܂�Ȃ��B�����ł̓G�l���M�[���̂����݂ɓ�������ĐV���ȃG�l���M�[�����o���悤�Ȃ��Ƃ��s����B���]�Ƃ����g�D����镨���̕��G�ȊW�͎v�l�G�l���M�[�Ƃ��Č���邾�낤�B���̎v�l�G�l���M�[�͕�����Ȃ��G�l���M�[���̂̕ω���ϗe�𑣂��悤�ɂȂ�̂ł���B�u�l����v�Ƃ͂܂��ɂ��̂��Ƃ��w���Ă���B
�@�ŏ��P�̂��̂ɂȂ낤�Ƃ���F���̉^���́A���ƃG�l���M�[���s���̂��̂Ƃ��Đi�߂���B���������̏W�����Ɍ��ɗ����Ƃ��A�܂肱��ȏ㌋�����邱�Ƃ��o���Ȃ��ō��̌`�ԁi���]�j�ɒB�����Ƃ��A����܂ŕ��ƕ��̊W�Ō���t�����Ă����G�l���M�[�����Ƃ̊W����������A�Ǝ��ŕω���B������悤�ɂȂ�A�t�ɕ��Ƃ̊W�����o���悤�ɂȂ�̂ł���B
�@�v�l�����B�̍s�ׂ����肵�Ă���̂͂܂��ɂ��̂��Ƃ��w���Ă���̂��B
�@���܂ꂽ����̎v�l�́A�܂��[�����Ƃ̊W�������Ă����B�܂���̂��v�l�����o���Ă����ƌ����Ă��������낤�B�v�l�͂܂����̂̏]���I�ȑ��݂ł����Ȃ������B
�@�������₪�Ďv�l�͓��̂��z���n�߂�B����Ɠ����Ɏv�l�͓��̂��x�z���悤�Ɠ����o���̂ł���B����͎��R�𐪕����ė����l�Ԃ̗��j�Ɗ��S�ɏd�Ȃ邾�낤�B�l�Ԃ����R��j��悤�ɁA���Ƃ��Ďv�l�͎���̐g�̂��ꂵ�ߔj�łɗU�����Ƃ�����̂��B
�@���݂̎��B�͂܂��ɂ��̒n�_�ɗ����Ă���ƌ����Ă����ł��낤�B�v�l�̔\�͔͂���I�ɔ��B�������A��������܂��R���g���[���o�����ɁA�S�͕s�K�v�ȃG�l���M�[�����o���Ă��܂��B�܂��Y�ݏo���̂ł���B���̋�Y�͌��ݐl�ɂ����Ă��傫���Ȃ����悤�ɂ�������B
�@�������v�l�͋�Y�̂��߂ɐ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�v�l���܂��F���̐i���̒f�Ђ��Ƃ���Ȃ�A���̉F���ɂƂ��ėǂ��Ƃ�����̂������ɂȂ���Ȃ�Ȃ��͂��Ȃ̂��B
�@������ɂ��Ă��F���I�Ȏ��삩����j������Ȃ�A�l����Ƃ����l�Ԃ̐��_�I�s�ׂ͍��悤�₭�n�܂������肾�Ƃ������Ƃ������邾�낤�B�܂莄�B�̎v�l�͂܂��\���ɏn���Ă��Ȃ��̂��B���̂��߂ɐl�Ԃ͋�Y������A������������A�����A���R�̒��a��j��̂��Ǝ��͍l����̂ł���B
�@�����炭���̋�Y�́A�Ȋw�̐i���Ƃ���ɗ��ł����ꂽ�Љ�ɓ��݂��閵���Ƃ��Č���Ă���̂��B�������B�͗��j�ƂƂ��ɋ�Y�̗ʂ𑝂₵�Ă���B
�@���̋�Y���Ȃ킿�������ő�ɂȂ����Ƃ��A�l�Ԃُ͕ؖ@�I�i���𐋂��邾�낤�B����͉F���̐i���ɑg�ݍ��܂ꂽ�K�R�I�ȗ���̂悤�Ɏv����̂ł���B
�@���̗���̒��Ől�Ԃ́A�₪�Ďv�l�����ݏo���ꂽ�{���̗��R��m��悤�ɂȂ邾�낤�B���̂Ƃ����B�͏��߂Đ������v�l�̎g�������w�Ԏ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A���͂����v���̂ł���B
�@�����Ȃ�Ǝv�l�͎��R�̒��Ō����ɒ��a���A��Y���܂���������ł��낤�B�l�Ԃ͉F���Ɗ��S�Ɉ�̂ƂȂ�A�^�̊y���������ɒz���̂ł���B�����ɂ͐��_�ƉȊw�̗Z�������S��I�Ȑl�ԎЉ���ݏo����Ă���Ǝ��͍l����̂ł���B
�@���B�l�Ԃ́A���̊y���Ɍ������r��ɂ���̂ł���B
�@�l����Ƃ����������̂悤�Ȏ��_���猩�߂Ă����A�K�������Ɏv�l�̑��ݗ��R�����炩�ɂȂ�ł��낤�B
�@�������Č���Ȃ�A�v�l���l�Ԃ̓����ł���A���S�Ȃ��̂��Ƃ����l���͖ϑz���ƕ������Ă��邾�낤�B�v�l�͐l�ԂɂƂ��āA�m���Ő�ΓI�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ɂ�������炸�������l�Ԃ͎v�l�̍��o�����E��S�Ă��Ǝv�����݁A��Y�������o���A�������������N�����̂ł���B
�@�����������̉F���I����Ől�Ԃ�����Ȃ�A�݂��ɎE����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�R���͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�������Ƃ���Ȃ�A���炩�Ɍ���Љ�̕����Ă�����́A�v�l���̂��̂̂Ƃ炦���Ɍ�肪����ƌ��킴������Ȃ��̂ł���B
�@���́A���́u�l����v�Ƃ��������l�@���čs�����ŁA���̐������Ӗ��Ɛl�ԂɂƂ��Ă̐^�̖����𖾂炩�ɂ��Ă������낤�B�������邱�ƂŐl�Ԃ͂₪�ĐV���ȑ��ݎ����Ɉڂ邱�Ƃ��o����ƐM����̂ł���B
�@
�R�D�����F���̖�
���͐�ɁA�G�l���M�[���ψ�œ����ȋ�Ԃ���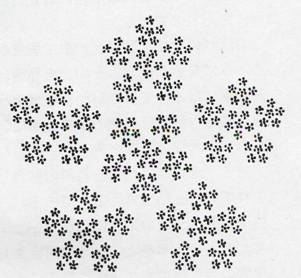 �����F���ł���A
�����F���ł���A
�̂��Ă�Ă�n�F���_���炷��A�e�Ղɂ��̏����F�������ł��������Ƃ��ؖ��ł���Ə������B
�@���̖��́A�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���������ώ��ɍL�����Ă��邽�߂ɃX�P�[���̊e��ɂP�Ȃ鑶�݂ݏo���Ȃ��̂��B
���̂��߂ɕ��͍ی����������ȃX�P�[���ɐ摗�肳��čs���A���ǂ͉��������Ȃ��^���̉F���A���Ȃ킿�����L�������Ȃ̂ł���B
�@���ď����e���ɂ���邪�A���̏ؖ������݂Ă������B
�@�̂��Ă�Ă�n�F���͖����ɃX�P�[���̏ꂪ�A�Ȃ������E�Ƃ��ĔF�������B���̂Ƃ��A�X�P�[���̊e��Ɍ���镨�́A����������ʂ̃X�P�[���̏�̕����W�����ďo�����A������u�P�Ȃ鑶�݁v�Ƃ��ĔF�������̂ł������B
��l�̐l�Ԃ́A�f���q�������ɏW�����đg�ݗ��Ă�ꂽ�P�Ȃ鑶�݂Ȃ̂ł���B���邢�́A�l�Ԃ͒n���Ƃ�����̓V�̂Ɏ�������A���̓V�݂̂͌��Ɉ��������A��̉���\�����A����ȃX�P�[���̎����ɐ_�l�Ƃ����P�Ȃ鑶�݂����グ��B���ꂪ�̂��Ă�Ă�n�F���̎��ۂ̌������ƌ�����B
���̐��E���������f���Ƃ��Đ�ɐ}���������B
�ꌩ���ĕ�����悤�ɁA�T�̓_���݂��Ɉ��������W�����ĂP�Ȃ鑶�݂����グ�Ă���B����ɂ��̂P�Ȃ鑶�݂��T��ɂȂ��Ă��傫�ȂP�Ȃ鑶�݂�����Ă���B����ɂ��̂P�Ȃ鑶�݂��T�W�����Ă��X�P�[���̑傫�Ȏ����ɂP�Ȃ鑶�݂��o��������̂ł���B�����Č���Ȃ����̌܊p�`�͊g�債�čs������\���Ă���B
�����ŏd�v�Ȏ��́A���̐}�ɂ�����_�ɂ��Ăł���B���̓_���g�勾�Ō���P�̓_�ł͂Ȃ����͂T�̏����ȓ_����Ȃ��Ă��鎖��������B���������B�l�Ԃ̖ڂɂ͂���͂P�̓_�Ƃ����ʂ�Ȃ��̂��B���B����̂��̂Ƃ��ĔF�����邱�̓_�́A���͖ڂɌ����Ȃ������ȓ_���W�����č���Ă���B���̂悤�ɐ��E�́A�P�Ȃ鑶�݁i�����܂�j����邱�Ƃɂ���ď��߂ĔF���̉��Ɍ����̂ł���B
�Ƃ��낪�A���E���ψ�ȃG�l���M�[���������Ȃ����E�͂ǂ����낤���B�����悤�ȃ��f�����g���čl���Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ邾�낤�B
�G�l���M�[�W�������ȋ�ԂƂ͕������Ԋu�ɕ��Ԑ��E�ł���B
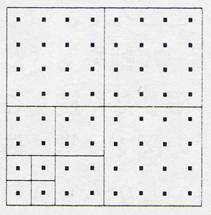 �E�̐}�͂��̂��Ƃ�\���Ă���B���̂Ƃ��S�̓_���P�̂܂Ƃ܂�ƍl��
�E�̐}�͂��̂��Ƃ�\���Ă���B���̂Ƃ��S�̓_���P�̂܂Ƃ܂�ƍl��
��ƁA�e�X�P�[���̏�͐}�̐��ŋ�������̂悤�ɂȂ�B
���̂Ƃ���ԏ����ȃX�P�[���̋��ɒ��ڂ���A�_���ЂƂ��������Ă��Ȃ����������邾�낤�B
�Ƃ��낪�G�l���M�[�W�̋ψ�Ȑ��E�ł́A���ǂ����͓��Ԋu��ۂ��Ă��Đg�����������A�ǂ����ɂ܂Ƃ܂��ĂP�Ȃ鑶�݂���鎖���Ȃ��̂ł��邩��A���̓_���P���������Ă��Ȃ��X�P�[���̋��͖������邱�ƂɂȂ�B�����ł��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�O�̐}�œ_���P���������Ă��Ȃ������S�̓_�ɂ��Ēu���������̂��E�̐}�ł���B
�S�̂ɓ_�̐��������A���R�����e�_�����ꂾ���������Ȃ��Ă���B
�Ƃ��낪�A�̂��Ă�Ă�n�F���ł̓X�P�[���̎��͖����ɏ��������Ȃ��čs���̂ł���������A���̐}���炳��ɏ����ȋ����l���邱�Ƃ��o����̂ł���B����Ƃ����ɂ����_���P���������Ă��Ȃ���悪����Ă��鎖�ɂȂ�B
��̗��R����A����������ł��邩�瓯���悤�ɂ��������K�v���o�Ă��邾
�낤�B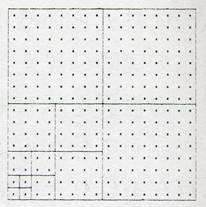
����ƑS�����l�̗��R����A����ɑS�̂̓_�̐��͐�̂S�{�ɖc��オ��A�t�ɓ_�̑傫���͂S���̂P�ɏk��ł��܂��ł��낤�B
����ł��܂��A����ɏ����ȃX�P�[���ɖڂ�������A�_���P���������Ă��Ȃ���悪����邩��A���̂��тɂ�����������čs���A�_�͂S�{�����̐��𑝂₵�Ă����A�t�ɑ傫���͂S���̂P���k�����Ă����̂ł���B
�Ƃ���ŁA�̂��Ă�Ă�n�F���͖����̃X�P�[�������������F���ł���������A���̕�͌���Ȃ��������ƂɂȂ邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̐}�ł͏�ɍŏ��̃X�P�[���̋��ɂ͓_���P��������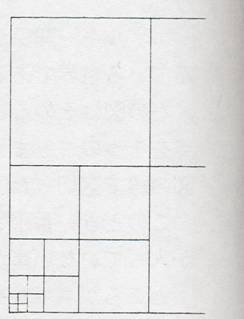 �Ȃ�����ł���B�܂�ݒ肷��_���傫�������
�Ȃ�����ł���B�܂�ݒ肷��_���傫�������
�Ȃ̂ł���B
�����Č��ǁA���̏C�����ɑ�����Ȃ�A���B�͂��̓_�����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�B�܂��ɖ��ƂȂ�̂ł���B����������C�������Ȃ��悤�ɁA���̋�Ԃ͖��Ƃ��ĕ߂炦����ł��낤�B
���̓_�����̑��݂�\���Ă���Ƃ���A�����F���͂܂��ɕ����݂��ɏ����ȃX�P�[���ɐ摗�肵�čs���A�t�ɂ���畨���݂͖����ɐ��ʂ𑝂₵�ċ�Ԃ��[�������Ă���ƌ������Ƃ��o���邾�낤�B
���Ƃ͎��̂Ƃ��뉽���Ȃ��ƌ����̂ł͂Ȃ��B����͂ނ����Ԃɂ��܂Ȃ����̏[���������݂Ȃ̂ł����āA����䂦�ɂ܂����B�ɔF�������Ȃ����݂Ȃ̂ł���B�{���̑�ꕔ�ŏq�ׂ��u�L�̖��v�Ƃ͂܂��ɂ��̖����w���Ă���B���邢�͏@���Ƃ̌��������܂����̖����w���Ă���Ǝ��͍l����̂ł���B
���́A���E�̍����ł��镨�Ƌ�Ԃ������S��̑��݂��̂��̂ł���B�����Ă��̖������A�����F�����̂��̂ł���A���B�̍ł��[���������Ȃ킿�̋��ƌ�����B���B�͂܂��ɂ����������ė����̂��B
�Ƃ�����A�ȏ�A�����ψ�ɑ��݂��鏉���F���̖��ɂ��ďؖ������B
�S�D������
���B�͌������̒��Ő����Ă���B�������̔���Ȃ����o�͖��A���邢�͌��z�Ƃ��ĂƂ炦����B�������͓˂��l�߂čl�������ӂ�Ȗ����͂��ł��邪�A���퐶���̏�ł͔��ɏd�v�Ȋ��o�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
���m���Ɏ����͖ڊo�߂Ă��āA�d����ƒ�̎����l���A���ނ����
����A�l�Ƙb��������H�������Ă���B���̂Ƃ����B�ɂ͊m���Ɍ������������āA����Ԃɂ����ْ̋������ݏo����Ă���̂��B
�������Ƃ��N����Ζ��ł����Ăق����Ɗ肤�B���������ꂪ�����Ė��ł͂Ȃ��̂��ƁA�Â���ƂȂ����o���͂���ł����邱�Ƃ��낤�B�����ɂ́A����͖��ł͂Ȃ��Ɗm�M�����錻�������m���ɂ���̂ł���B����͈�̉����낤���B
���������Ă���B���̊��o�����Ɍ������ł���A���͎������͂�����ƔF�����Ă���B���ł͂Ȃ������ɍ��A�����͂���B�l�������Ă��鎩��������B�����͖��ł͂Ȃ��B�ύX�̂����Ȃ������Ȃ̂��B���������v������܂Ƃ܂�ɂȂ��Č�����������Ă���̂��낤�B
���������ۂɂ͌����ɂ���A���ɂ���A���̂������ɂ��鎞�ɂ͋�ʂ����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���̒��ɂ����ẮA����ƒm�邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B���߂ď��߂Ă��ꂪ���������ƕ�����̂ł���B���x����������߂�o����ς�ŁA���B�͂����錻������g�ɂ���̂��B�������Ă��銴�o�ƁA���߂Ă��銴�o�Ƃ͂ǂ����������������B�����Ă����m��̂͌����̒��̎��ł����āA���̒��̎��ł͂Ȃ��̂͊m�����낤�B����ł��B�����͎c���Ă���B
�������Ƃ������m���Ɏ����͌����̐��E�ɂ���Ƃ������o�̂��Ƃł���B���̂��Ƃ��܂���̓I�Ɍ��Ă݂悤�B
���͐X�̒��ɂ���B�ڂ̑O�ɑ傫�ȘV������A�ۂ̂悤�ȐA�����}���琂�ꉺ�����Ă���B����ނ��̎����������ߓ���Ŏ}������܂������đ��z�̌��͂��̒n��ɂ͂قƂ�Ǘ����ė��Ȃ��B���X�����̍����������������A�Ђ��肵����C�����̂悤�ɗ���čs���B
���Ď��͌����̒��ɂ���̂��A���̒��ɂ���̂�������ǂ��m���߂��炢���̂��낤���B���������̒��ɂ���Ƃ����ۏ�^���錻�����Ƃ͈�̂ǂ��������̂Ȃ̂��낤�B
���͐��C���܂��t�y�ݒ��߂Ă���B������E�������Ċ��G���y���݁A���̍����k�����Ƃ��o����B�傫�ȘV�Ɋ��|���邱�Ƃ��o���邵�A���̏�Ŏ����̎v�����܂܂̍s�ׂ����邱�Ƃ��o����Ǝv����B����͈�̌������ł��낤�B
���邢�͒��Ӑ[������������A�̗t�̈ꖇ�ꖇ�����ŗh���̂��m���߂邱�Ƃ��o����B���܂��A�����ɋ߂��ɏ����̐���X�̂���߂����������Ă���B��������芪�����ׂĂ̂��̂����R�̂܂܂ɂ����߂��Ă���B���̕ω������o���͂�����ƂƂ炦��B�����ɂ���̌�����������B
�܂������̓��ʂɖڂ�������A�Ђ���Ƃ�����C�ɕ�܂�ċْ������畆���S�n�悭�������Ă���B�X�̕��͋C����������肵�����o���̂�L�т₩�ɂ��čs���悤�Ɏv����B���̋ؓ��ɐS�n�悢��J�����L�����Ă���B��������B�����������o���܂��������ƌ����邾�낤�B
����Ɏ��̋L���ɂ́A���N���Ă����ɂ���ė����o�܂����߂��Ă���B���͂Ȃ������ɗ����̂��m���Ă��邵�A���ꂩ�牽�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����������Ă���B���邢�͐E��ł̐l�ԊW�ɔ����������̎p��A���܂�Ă��̕��������Â��Ă��������̐��i�ȂǁA�����Ɋւ����̔F��������B�v����ɂȂ������������ɂ���̂��n�������Đ����o����͂����肵���L���ƔF��������B���̔F�����܂��������ݏo���B
���B�̎��������́A���悻���̂悤�ȗv�f�����܂肠���Đ��ݏo����Ă���ƍl���Ă����ł��낤�B
�������͊O�ɑ��l�Ƃ̊W��������ݏo�����B�܂莄�B�͑����̐l�X�Ɨl�X�ȃR�~���j�P�[�V�����������Ƃ��o����B���B�͂����ɋ��������������̂ł���B
���ǁA�������́A���̂T�̗v�f�ɕ��ނ��鎖���o���邾�낤�B
�P�D���̂ɐG��邱�Ƃ��o����B�i���ڒm�j
�Q�D���i�≹�����ׂ������ʏo����B�i���u�m�j
�R�D�S�g�̊��o�ɒ��ڂ��邱�Ƃ��o����B�i���Ȋ��o�j
�S�D�L���̑O��W���͂�����ƂȂ����Ă���B�i���ȔF���j
�T�D�R�~���j�P�[�V��������������B�i���ҔF���j
���̂T�̗v�f���d�Ȃ荇���A���ݍ����Ď��B�͎��������̐��E�����グ��B���������̐��E�Ƃ����̂́A����ł��ꂪ�^���̐��E�ł͂Ȃ��ƌ������Ƃ����Ӗ����Ă���B���B�����E���ƔF�����Ă����Ԃ��R�����l���A�����Ď������g�������A����͐^���ł͂Ȃ��B����͐^���ł͂Ȃ��A�F���Ȃ̂ł���B����䂦���͂��̐��E������ԂƌĂ�ŁA�^���̐��E�Ƌ�ʂ���̂ł���B
�^���̐��E�́A�����̏u�Ԃɑ��݂��Ă���B���������B�̔F���͂��̐^�������̂܂܂Ƃ炦�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂��B���Ƃ��ڂ̑O�ɂ���V�Ɏ��G��A�l�X�Ȋp�x���炱��߂Ă��A������̂͂����V����̏�����ł���A���͂��̏��V�̑��݂��ʒu�t���邵���Ȃ��B���͐^���������ė��邪�A�^�����̂��̂ł͂Ȃ��B����Ԃ͂��̂悤�ɂ��Đ��藧���Ă���̂ł���B
���̂��Ƃ͎������g�ɂ��Ă������邾�낤�B���B�������Ƃ��ĂƂ炦�Ă��銴�o��F���ɂ��Ă��A�����͌����Đ^�����̂��̂ł͂Ȃ��̂ł���B������܂��^���������ė�����ɊO�Ȃ�Ȃ��̂��B
�R�~���j�P�[�V�������܂��^���̂����ł͂Ȃ��B�^���͂������R�Ƃ����ɂ�����̂ł����āA�����o����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B�����̏���炱�����B�̊ԂŃR�~���j�P�[�V�����Ƃ��Đ��藧�Ƃ������邾�낤�B
�܂莄�B�̂��������A���邢�͌����ƌ�������̂́A�^���Ƃ͊|�����ꂽ����Ԃ̒��ł̂Ƃ炦���Ȃ̂ł���B���Ȃ킿���������グ�����E�ƌ����Ă������낤�B���̂悤�Ɍ����Ƃ́A�^���ƈ���Čl�I�Ȏ��ɂ���ӂ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����ӂ₾�ƌ����̂́A�����Ɩ��̊Ԃɂ͑傫�ȍ��ق��Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�܂莄�B�̎����������A�^�����̂��̂łȂ��Ȃ�A���ǂ��̌����Ƃ������̂����B���g�����o�������̂ƌ����邩��ł���B
�����Ă��̈Ⴂ���グ��Ȃ�A�����͒��ڂɐ^���������ė�����ɂ���č��o�����̂ɑ��āA���⌶�z�͓��]������ɍ��o�������Ɉ˂��Ă���ƌ����邾�낤���B
�������Ȃ��玄�B�������Ƃ��Ă��邱�̎������̏���ώ@����A
���ڐ^���������ė���������̂܂܂Ƃ炦�ė������Ă���ƌ����悤�ȏ�ʂ́A�ɂ߂ď��Ȃ��̂ł���B
���Ƃ��Ύ��̖ڂ̑O�ŁA
��l�̒j�������B���̂Ƃ����͂�������̂܂܂łƂ炦�邱�Ƃ͂܂��Ȃ����낤�B���͂���J�Ǝ�邩������Ȃ����A�F�D�̂��邵�Ǝ�邩������Ȃ��B������ɂ��Ă����́A����ė������]�ŏ�������B����ƁA�Ƃ���ɂ���͖��ƑS�������\���ƂȂ�B
�O����̏��Ɏh�����Ă̂��ƂƂ͌����A�������瓪�]������ɏ������ւ��Đ��E����邩��ł���B
����ɏ������ւ���ƌ����͖̂��_�A�F�����̂��̂̂��Ƃ��w���Ă���B���ہA�F���͐^�����w�������͂��邪�A�^�����̂��̂ł͂Ȃ������B�������̂ł��l�ɂ���ĔF��������Ă���̂͂��̂��߂ł���B
�t�Ɍ����A�����܂��F���̈���ƌ����邾�낤�B
�ӎ��Ɍ��ꂽ���������Ƃ̊֘A�ňӖ��t���邱�ƁA�Ƃ����̂����̎������F���̒�`�ł������B�������猾���A���́A����Ă����A��������ł͂Ȃ����]�ɋL�����ꂽ���̂��Ƃ������Ƃ����ŁA���̍\���͔F�����̂��̂Ȃ̂ł���B
�܂肱���������Ƃ��o����̂��B
���ƌ������A���B�͑S����������̂ƍl���Ă��܂����A���ۂɂ͂����قȂ���̂ł͂Ȃ��B��������ʂ�����̂͂����������̗L���݂̂ł���B���������̌������ɂ��Ă��F���ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��A���ǂ́A���������������̂��̂ƌ�����̂ł���B���̈Ӗ����玄�͎���Ԃɖ��ƌ����̋�ʂ�t���Ȃ��̂ł���B����Ԃ�F���̋�Ԃƌ���Ȃ�A�����܂������ł���A����Ԃ��^�����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ��������猾���A�������܂����Ȃ̂ł���B
����Ƃ����ŏd�v�ɂȂ��Ă��鎖�͖ڊo�߂Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���B�ɂ́A�ڊo�߂���ɏ��߂Ă��ꂪ���ł������̂��ƕ�����̂ł����āA���̂������ɂ��鎄�B�͂����v�l�������邵���Ȃ��B�ڊo�߂Ȃ����肻����Ƃ��āA�v�l���̂��O���璭�߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B
�������̂���v�l�́A�\���q�ϓI�Ȍ������o����Ǝ��B�͐M���Ă���B���̋q�ϓI�v�l���Ȋw�W�����A������z���ė����̂ł���A���B����芪�����E�͌������̂��̂ł���B�Љ�͂����ɐ��藧���Ă���̂ł����ċ^���悤���Ȃ����낤�B����͎��B�̕�����Ȃ��������ƌ����悤�B
���������̂Ƃ���A���̌����������ł͂Ȃ��Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ������̂ł���B���B�͊o�����Ȃ��܂ܖ����������Ă��邩������Ȃ��̂��B
���͂܂������ŁA�v�l�����o�����E�ɑ���A���B�̐�ΓI�Ȋm�M�ɁA��̋^����o�����B���ƌ��������`���Ƃ���Ȃ�A���B�͂��̎v�l�̍��o�����\���ɂǂ��Ή������炢���̂��낤�B
���������̌������Ɗo���̖��́A����������ŁA�ڂ����l���邱�Ƃɂ��āA���͍l����Ƃ������Ƃ̋��\��������Ɋ���̖ʂ��猩�Ă��������B
��Q�� �v�l�n�}
�P.�v�l�̕���
�@ ����Łu�l����v�ƌ����Ă��A�����ɂ͗l�X�Ȏv�l�̌`�Ԃ��܂܂�Ă���B
�ƌ����̂��A���͍l����Ƃ������Ƃ����̂܂ܐS�����グ�Ă���Ɨ������邩��ł���B
�S�́A�_���I�ȑ��ʂ�����O�I�ȗ̈�ɂ��傫�ȈӖ�����������B�S�͋�J���Ę_������g���Đ��E�����グ�邪�A����ł͂���Ȑ��E���悤�ȁA��_���I�ŕs�����Ȑ��E�����Ƃ��ȒP�ɍ��グ�Ă��܂��̂ł���B
���邢�͌��t�Ō����\���Ȃ����o�⊴��̎x�z���鐢�E�����グ�邱�Ƃ�����B
���́A�����S�S�ʂɂ킽�铭�����̂��̂��l����Ƃ������t�łƂ炦�����̂��B���������̂��߂ɂ́A�v�l�����ۓI�Ȍ���ɑ����đΉ��ł���悤�ȕ��ނ��K�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�B
�����Ŏ��͂��̍l����Ƃ����`�Ԃ����̂悤�ɕ��ނ����B
�P�A���O�v�l�i�_���I������I������I��p�Y���I�v�l�j
�Q�A��O�v�l�i��_���I��v�_���I�v�l)
�R�A�g�̓I�v�l�i�K���I��g�̓I�A���o�I�A���v�l�I�v�l�j
���̕��ނ́A�S�̎��ۂ̌��ꂩ�猩�����ނł���B���������Đg�̓I�v�l�Ȃǂ́A�l����Ƃ������Ƃɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��悤�Ɏv���邪�A���͂����ĐS�̂��̂悤�ȑ��ɂ܂ŁA�l����Ƃ����Ƃ炦���������B
�Ȃ��Ȃ玄�́A�v�l���s�ׂƂƂ炦�邩��ł���B�܂�s��ׂ��܂��s�ׂł���A�S�̌���ɊO�Ȃ�Ȃ��B�����Ɏ��B�����v�l�I�ł���A����͖��v�l�Ƃ����v�l�Ȃ̂ł���B���ہA�v�l�̐��̂̓G�l���M�[�̔g���ł���B���E�͕��ƃG�l���M�[���琬�藧���Ă���̂ł��������A�v�l�͊m���ɕ��ł͂Ȃ��B����Ƃ������玩���Ǝv�l�̓G�l���M�[�̌���̈���ƌ������Ƃ��������Ă���̂ł���B����͂����ꏇ��ǂ��Ę_��i�߂čs�����ŁA���������ł��낤�B
�����Ƃ����̕��ނ͕X�I�Ȃ��̂ł����āA�S�����̂悤�ɐ藣�����ƌ����̂ł͂Ȃ��B���R�Ȃ��炱�̕��ނ���R�����̂�A
���̒��Ԃɑ�������́A�ǂ���ɂ�����悤�Ȏv�l�̌`�Ԃ͂��邩������Ȃ����낤�B
����������͎��ɂƂ��Ă����������ł͂Ȃ��B���������S�͋敪�ȂǏo���Ȃ���̂��̂Ȃ̂ł���B���̖{�ӂ́A���̐S�ݏo���v�l����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃɂ���B���̕��ނ͂��̂��߂̘_�������邽�߂̕��ւƂƂ炦�����B
�Ƃ����ꂱ�̕��ނɉ����āA�l����Ƃ������ԂɐG��čs�����Ƃɂ��悤�B
�Q.���O�v�l
���O�v�l�́A����Ȋw�ݏo�����l�Ԃ̊�{�I�Ȏv�l�`�Ԃł���B
���B�͖ڊo�߂Ă������A���炩�̌`�Ő��E��F�����Ă���B
���������B����芪���Ă���^���̐��E�͂�������͂邩�ɍL���傫���B���̐^���̐��E������Ԃ́A�������邾���ł͎��B�ɂ͔F���ł��Ȃ��B����͂������B�̋C�Â��Ȃ����̂Ƃ��Ă����ɂ��葱���邾�낤�B
���̋C�Â��Ȃ����E�����B�̑O�Ɍ����̂́A���ꂪ���B���g�Ƃ̊W����茋������ł���B
�Ⴆ��C�ɂ��čl���Ă݂悤�B
�l�Ԃ��܂���C�̑��݂�m��Ȃ��������A�l�X�ɂƂ��ċ�Ԃ͂������Ƃ������̂ł����Ȃ��������낤�B����͋���ۂ̉����Ȃ��ꏊ�ł����āA���ꂪ�F���̔w�i�ƂȂ��Ă��A�����ĔF���̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ������B
���Ȃ݂ɋ�Ԃ�����F�����悤�Ǝ��݂Ă݂邪�悢�B��ԂɌ�����ꂽ�F���͂������ɕ�������ŁA�����Ă�����Ƃ炦�邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��낤�B���Nj�Ԃ��Ƃ炦����̂́A������芪�����̂Ƃ����ƕ��̌��Ԃƌ������悤�ȓI�ȊT�O�ł����Ȃ����ƂɋC�Â��͂��ł���B
�Ƃ��낪�A���̋�Ԃɋ�C�������āA���ꂪ���B�̌ċz����_�f���_���Y�f�Ȃǂ̕��q���琬�藧���Ă���ƒm�����Ƃ��A���B�̔F���͑����ɂ��̋�Ԃ��Ƃ炦�n�߂邾�낤�B���B�̐��E�ς́A���͂₱�̋�Ԃ������̋���Ƃ͂Ƃ炦�Ȃ��B���̋�Ԃ͋�C�̏[��������̑��݂Ƃ��Č���Ă���̂ł���B
��C�͂��̎���ɂ��A���B�̖ڂɌ�������̂ł͂Ȃ��B�ɂ�������炸����l�̔F���́A�͂�����Ƃ����ɂ����C���Ƃ炦�邱�Ƃ��o����̂ł���B
���B�̍��o���F���̐��E�ɂ́A�ɂ߂Ă�������Ƌ�C�̑��݂��ʒu�t�����Ă���B����͋�Ԃ̒��ɁA�u���v�Ƌ�C�̊W����������Ǝ�茋��Ă��邱�Ƃ������Ă���B���͂⎄�B�͂��̐��E�����C����菜�����͏o���Ȃ��̂ł���B
���B�̐��E�ɋ�C�����ꂽ�̂́A���B�l�Ԃ�������ώ@�����͂𑱂��āA�ڂɌ����Ȃ����̑��݂��m�F���Ă������j��ʂ��Ăł���B
����ɑ���v������₪�Đl�Ԃ́A�ڂɌ����Ȃ��A�藣���悤�̂Ȃ���Ԃ��A��C�i���q�Ƌ�ԁj�Ƃ����`�ŋ敪���邱�Ƃɐ�������B
�^���̐��E������Ԃ��猩��A��C�͂��̎���ɂ��������葱���Ă����B���B�ɂ͒m�蓾�Ȃ��Ă��A��C�͎��B�̔F���̊O�ŁA���B�̐������̂��̂��x�������ė����̂ł���B
�������ɂ�������炸�A�F���̐��E������Ԃł́A����͔F�������i�K����ł������݂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B���̓_�͂��炽�߂Ċm�F���Ă����K�v�����邾�낤�B
�v�l�́A�܂��ɂ��̂悤�ȔF������{�Ƃ��Đ��ݏo����Ă�����̂ł���B���̂Ƃ������I�Ș_���̗�������v�l�̈�𗝔O�v�l�ƌĂԁB
���O�v�l�͂܂�A�F���ɂ���ċ敪���ꂽ���ꂼ��̒P�ʁA���Ȃ킿�����Ƃ���f�ނɂ��Ę_���I�ɑg�ݗ��Ă��čs���v�l�ƌ����邾�낤�B
�Ƃ���ł��̗��O�v�l�́A�܂��ڕW���ݒ肳���B�v�l�͂��̖ڕW�Ɍ������ē����A�₪�Ă����ɍs���������ƂŊ�������B
���̎v�l�ڕW�́A�Ⴆ����т����i���ҁj�Ƃ������̂�A�Ȃ����͗����ė��Ȃ��̂��i�^��j�A�P�{�P�͂������i�ݖ�j�Ȃǂ̖��ݒ肩�琶�ݏo�����B
�����̖��ݒ�͖����ɐ��ݏo����A�v�l�ڕW�͌���Ȃ������B���������̍l���ł́A�����̖ڕW�͋��ʂ��邽����̂��̂ɒu�������邱�Ƃ��o����̂ł���B
���퐶���̒��Ŕ����������^��A�w��I�Ȍ����ۑ�A���邢�͕֗����̒Njy�ȂǁA�l�X�Ȏv�l�ڕW�̂��ׂĂɋ��ʂ�����́A���ꂪ�u���v�Ƃ����₢�����Ȃ̂ł���B
����͎������l�Ԃ̍ł���{�I�Ȗ₢�����ł���A���Ɏ��B�͔F���Ƃ̊W�̒��ʼn��x���G��ė��Ă���B�܂薢�m�Ȃ���̂ɑ���u���A�Ȃ��A�ǂ����āA�ǂ�������v�Ƃ����m���I�ȗ~�����V���ȔF���ݏo���Ƃ����A���̊�{�I�ȗ��ꂪ�v�l�̂��ׂĂ̍���ɉ�������Ă���̂��B
���̂悤�ɋ���т����Ƃ����v������l�͔�s�@�����o�������A���̉ߒ��́u���v�Ƃ����₢��������Ȃ藧���Ă���B�܂聃����͉������Ȃ���ׂ�̂������ǂ�����Δ�ׂ�̂����Ƃ�����ł���B
���̂悤�Ɂu���v�Ƃ����₢�������v�l�ݏo�������͂ƂȂ��Ă���͖̂��炩�Ȃ��Ƃł��낤�B
��������Ɨ��O�v�l�́A�F���ɂ���ċ敪���ꂽ���E�A���Ȃ킿���Ƃ��g���āA�u���v�Ƃ����₢�����ɓ����悤�Ƃ����A�̉ߒ��ł���ƌ������Ƃ��o���悤�B
���̌��ʂƂ��Đl�͂܂��V���ȔF����B�����l����Ǝv�l�͔F������V���ȔF�������o���čs�����I�ȍs���ł���Ɨ����o����̂ł���B
���B�͂��łɔF���ɂ��Ă͏ڂ������ė����B�����ŐG�ꂽ�F���̃_�C�i�~�b�N�ȍ\���͎��̂Ƃ���ł������B
���Ȃ킿�F���́A�l�Ԃ̉F���I���݂Ƃ�������ӎ�����o������B
�܂�����̓��̂�m��A�g�̂́u���E�s���v��̌����邱�Ƃɂ���ď������m��������o���n�߂�B��������u���v�Ƃ����₢���������܂�邱�ƂŔF���͔���I�ɍ��߂���B�F���͂��ꎩ�̂��V���ȔF���ݎn�߁A�ו�������Ă����̂ł���B
���O�v�l�͂܂��ɂ��̔F���̐������čs�����ꂻ�̂��̂ł������̂ł���B�܂藝�O�v�l�́u���v�Ƃ����₢�������������ƂȂ��ċN���铪�]�̘A�������ƌ��Ă������낤�B
�u���v�Ƃ����₢�����ɂ���Đݒ肳�ꂽ����_���̓���ʂ��ĉ����čs���B����͂܂��Ƀp�Y���I�v�l�ƌĂׂ邾�낤�B
�������ꂪ���R�̗���Ƃ��Ă���̂��A�u���v�̈ӎu�Ƃ��ē����̂��͎��̖��ł���B���͂܂����̎��ł͂Ȃ��B
�Ƃ���Ŏ��������ŗ��O�v�l�Ƃ������Ƃ��g���̂ɂ͗��R������B
����܂ŏq�ׂė������e���猾���A�ނ���_���I�v�l�Ɩ��t����ق����ӂ��킵���悤�ɂ��v����̂����A���������͐l�Ԃ̂��̘_���I�v�l�̔��B���x���ė������̂̑����́A�_���I�łȂ������������ė����̂��B
����͘_���������A�l�Ԃ̓��@�͂Ƃł������ׂ������ł���B�����ɂ��Ă͏�O�v�l�̒��Ŏ��グ�����ł��邪�A�_������g���Đ��E��c�����悤�Ƃ��鎄�B�̒T���́A���̋��߂鐢�E�����m�ł������قǁA���̒����Ȃ����Ă͒B�����꓾�Ȃ��̂ł���B
�Ȃ��Ȃ�A�����̘_����������ςݏグ�čs���Ă��A�������琶�ݏo�������̂̂قƂ�ǂ��A���m�̐��E���z���邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B�_���̒Njy�́A���m�̐��E�����m�̐��E�Ɏ�荞�����Ƃ����Ƃł��邪�A���̖��m����荞�ނ��߂ɂ́A�������m�̐��E�Ɏ��L���Ď�荞�ނ����Ȃ��B�܂�莝���̍ޗ�����������H�������ŁA���ꂾ���Ŗ��m�Ȃ鐢�E�����o�����ȂǏo������̂ł͂Ȃ��̂ł���B
���̖��m�̐��E�Ɏ��L���ƌ����̂́A�����钼���ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�l�Ԃ͒����ɂ���Ă܂����E�𗝉�����B����������͘_���I�Ȏv�l���猩��Ό����悤�̂Ȃ��s���肳�Ƌ^���ށB�����Ől�͂��̒�����_���������Đ�������̂ł���B�����ɐ^���̔���������B�l�X�Ȑ^���̔����́A�܂����������̔����J���鎖�������̂ł���B
�������Đl�Ԃ͔F����[�߁A�_���I���E���L���ė����̂��B���B�̂��������v�l�̗���́A�����Ĉ�̑��ʂ����Ő��藧���Ă���̂ł͂Ȃ��A�藣�����Ƃ̏o���Ȃ���̂Ƃ��Ă̂Ȃ���������Ă���B�l�Ԃ̎v�l�́A���Ƃ��_���I�Ȏv�l�Ƃ����ǂ��A�R���s���[�^�[�ł͂Ȃ����Ȃ��Ƃ������̘_���͂����ɂ���̂��B
���Ȃ킿����́A�_���I�v�l�ł͂Ȃ����O�v�l�Ȃ̂ł���B
���āA���͂����ŏ��������~�܂��āA���O�v�l�̋��\���ɂ��Č��Ă������Ƃɂ������B
���B�̎v�l�͂��̂܂���Ԃ����グ��B�܂肻���ɂƂ炦��ꂽ���E�́A���̏ꍇ���^�����̂��̂ł͂Ȃ��B
�v�l�Ƃ́A��Ɂu�����i�^���j�ɂ��āv�̎v�l�ł���A�v�l���ꎩ�̂����́u�����i�^���j�v�ł͂Ȃ��B�܂肻���Ɏv�l�̋��\�������܂�Ă����Ȃ̂ł���B
��������������܂��^�₪���ݏo����Ă���̂������Ȃ̂��B�ł͗��O�v�l�̐��ݏo�����Ȋw�╶�����܂����\���Ƃ����̂��ƁB
���ۉȊw�̗͂͗l�X�Ȃ��̂ݏo�����B��������炪���\���Ƃ���Ȃ�A�ǂ����Đl�Ԃ������C�ɐ�������A�ʂĂ͉F���ɔ�яo���Ƃ����悤�Ȏ��ۓI�ȗ͂ݏo����̂��낤�B���������Η��_�����ł���Ȃǂƌ����͍̂����̂Ȃ���_�ł͂Ȃ����B
�ꉞ�����Ƃ��̂悤�ɕ������锽�_�ł͂��邪�A�����������ɂ͋��Ǝ������������l����������̂ł���B
��s�@�����A���P�b�g���F���ɔ�яo�����肷��̂͐^���̈�̌��ۂł���B�m���ɂ���͐l�Ԃ���������������Ȃ����A�����������Ę_��������Ԗ�ł͂Ȃ��̂ł���B�l�Ԃ����P�b�g��������̂͐^���ł��邪�A�v�l�͂���������w�������������̂��̂ł���A���ꎩ�̂����P�b�g�ł��蓾�Ȃ��B���̎v�l�́A���P�b�g�����B�̔F�����鎟���̉F�����ԂƂ������Ƃɂ��Ă͐����ł��邩������Ȃ����A�ʂ̎����̒��ɂ��郍�P�b�g�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ���������Ȃ��B
�����Ƌ�̓I�ɂ����A�j���[�g���̗͊w�Ƒ��ΐ����_�̑������悢��ł��낤�B
�n���Ƃ�������ꂽ�����Ō���A���͒��i����Ƃ����_���͐^���ƍ��v���Ă���悤�Ɍ�����B�A�C���V���^�C���������܂Ŏ��B�́A����͒��i����Ƃ����l�ł����Č����Ƃ炦�Ă����B
���������̗��_�͂��������Ɍ�����̉^���ƁA���܂��܈�v���Ă���悤�Ɍ����������Ȃ̂ł���B�^���̌��͏d�͂ɂ���ċȂ����Ă����B�F���Ƃ����傫�Ȏ���������������Ƃ��A�A�C���V���^�C���̂��̗��_�̐��������͂�����ؖ����ꂽ�̂ł������B
���̂��Ƃ͂܂��ɗ��_�Ƃ������̂��^�����̂��̂ł͂Ȃ�����\���Ă���B���_�Ƃ͌��ǂ��̏�Ŋm�F�ł���^���̌�����A���t�ł��܂������\�������̂ɉ߂��Ȃ��B���Ȃ킿���ꎩ�̂͋��ƌ����ׂ��Ȃ̂ł���B
���ł���Ȃ���A�Ƃ肠�������ꂪ�^���ɊԈႢ�Ȃ��Ή��o���Ă��邾���̂��Ƃł���B�t�Ɏ��B�́A����ȏ�̐^���������Ȃ����߂ɁA���̗��_��^���Ƃ��Ď���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂��B�����Ă���͂��ׂĂ̘_���ɋ��ʂ��闝�O�v�l�̈�̌��E�������Ă���Ƃ������邾�낤�B
�J��Ԃ��A���B�̍��F���ł����Ԃ̒��ł́A�m���Ƀ��P�b�g�����邩������Ȃ��B�������������_�Ń��P�b�g����Ȃ��������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��̂ł���B�^���͂܂��ɂ��̂悤�ɍL���[���̂��B�����A�u���b�N�z�[���̓����ł͌��݂̕������_�͂܂������ʗp���Ȃ��̂ł��邩��A����͌����ċ�_�ł͂Ȃ��Ƃ����͖̂������낤�B
�܂�����A���O�v�l�͑���Ɍ���Ȃ��`���Ƃ������ʂ�����B����������Ă��ė��O�v�l�͋��\�ƌ����̂͂��������Ƃ����l���������܂�Ă��邾�낤�B
���Ƃ��P�{�P�͂Q���Ƃ���������A���G�Ȑ������_�Ɏ���܂ŁA
�����ŕ\�����ꂽ�l���͂قڊ��S�ɑ���ɓ`��苤�ʂ̗�����������̂ł���B�����Ɏ��B�̕���������A�Љ�������Ă���B
���邢�͑��z�������珸���Đ��ɒ��ނƂ����悤�Ȏ��R���ۂɂ܂��v�l�ɂ��Ă��A�����͌�����悤�̂Ȃ����m�̎����Ƃ��������Ȃ����낤�B
��I�Ȏv�l�͌������ē��R�Ƃ��Ă��A���̂悤�Ș_���I�v�l�͂��Ƃ��Ə��r�������R�̌����ɏ]�������̂ł��邩��A������������悤�ɂ���𗝉����邱�Ƃ��ł���B���������Ă��̂悤�Ȏv�l�͐^���ł͂Ȃ����ƍl�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B
����������ł�����͋��ł���ƌ��������Ȃ��B
�_���I�v�l������Ȃ�����ɓ`���̂́A����͏��߂��獇�ӂł���悤�ɋ��ʂ̌��t����茈�߂Ă��邩��ł���B
�_���I�v�l�́A���̂��炩���ߗp�ӂ��ꂽ���t�̘g�ɐ^���̕��Ă͂߂ĕ\�����Ă��邾���̎��Ȃ̂ł���B�݂��ɗ����ł��鋤�ʂ̌��t������Ă����Ă��̘g�̒��Ŏv�l��g�ݗ��Ăčs���B���ꂪ�_���I�v�l�̊�{�ł���B�܂菉�߂���v�l�𐧌����đg�ݏグ��̂����_�Ȃ̂ł���B
���������Ă��̃��[���ɏ]���ĕ\�����ꂽ�v�l�͒N�ł�����𗝉��ł���ƌ����͓̂��R�̂��ƂȂ̂ł���B
���������̂悤�Ș_���I�v�l�́A���������v�l�̕������^�����牓���Ȃ��Ă��邱�Ƃ����B�͌������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�_���͂��̘g�̓����Ő�������������邪�A�^���̕��͂���Șg�ɂ͌����Ď��܂�Ȃ����낤�B
���邢�́A�m���ɘ_���I�v�l�́A���t�ɂ���ĕ\�����A�����ɓ`���邱�Ƃ��o���邪�A���������肪��������������ǂ����͕�����Ȃ��B����͊��Ɏ���Ԃɂ��Ă̍l�@�Ŏ��グ�Ă���悤�ɁA�����̂��̂ł���B
�^���͌��t�̔w��ɂ����āA�����m��̂͑̌��ȊO�ɂ͂Ȃ��A�����ɂ͌��t�Ō����\���Ȃɂ��̂��Ȃ��B���ǐ^���͂��Ƃł͌����\�����Ƃ��o���Ȃ��̂ł���B
�ɂ�������炸���B�͐^�����Ƃ炦�悤�ƌ��t����g����B�_���I�v�l�͂��Ƃɂ���đg�ݗ��Ă���B���Ƃ̈������B�ɈӖ���^���Ă���邪�A�����������͂������������ȌC�ɖ�����葫�����悤�Ƃ��āA���̂ق�������Ă���悤�ȕs���R������ɕt���܂Ƃ��Ă���̂ł���B�Ⴆ�Ό���Ȃ��O�ɋ߂Â��������O�ƍl����悤�ɁB
�������ǂ�ȗD�ꂽ���_�ł��A���ꂪ����Ȃ��^���ɋ߂Â��Ƃ͌����Ă��^�����̂��̂ɍs���������Ƃ͂Ȃ����낤�B�Ȃ��Ȃ�܂��ɐ^���Ƃ͍s���������̂ł͂Ȃ��A���łɍ��A�����Ɋ��S�ɑ��݂��Ă�����̂�����ł���B
���͂���������Ă��āA���O�v�l�Ӗ��Ȃ��̂ƌ�������͂Ȃ��B����͂ނ���l�ԑ��݂��̂��̂�\���Ă���B�����ے肷�鎖�͐l�Ԕے�ɂȂ����čs�������Ȃ����낤�B
�܂莄�̌����������́A���O�v�l�͐^���Ɍ��������Ƃ���l�Ԃ̈ӎu�����ݏo�����v�l�`�ԂȂ̂��Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ��Ӗ����Ă���̂́A�l�Ԃ������Ă���F����Ԃ��̂��̂����\�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƌ������ƂȂ̂ł���B
�����炱���l�͐^�������߂��ɂ͂���Ȃ��̂ł���B
�R�D��O�v�l
��O�v�l�͎��o���ꂽ��_���I�v�l�ł���B
���O�v�l���_���I�ȓ���ʂ�̂ɑ��āA��O�v�l�͂��̓����̂��̂��Ȃ�䩔�����L������������v�l���E�Ƃ�������B
���邢�͗��O�v�l�����t��\����i�Ƃ��đg�ݗ��Ă�ꂽ���E�ł���A���������Ă���͓��]�����グ�����Ƃ̐��E�ł������̂ɑ��āA��O�v�l�͂�����z���ĉ������A���R�ɐ��E����������v�l�`�Ԃ����B
���t�̐�����Ȃ��ׂɁA���̎v�l�͐^���ɂ܂œ͂��\���������Ă���B
���������̔��ʁA��O�v�l�łƂ炦��ꂽ���E�́A���S�Ȍ`�ő��l�ƕ������������Ƃ��o���Ȃ��B�܂��Ɍl�̓��I�̌��Ƃ��Ă݂̂Ƃ炦����v�l�Ȃ̂ł���B
��O�v�l�͂����̓_�ŗ��O�v�l�Ƒ傫�ȈႢ������B�������܂���ɏq�ׂ�悤�ɁA���̓�̎v�l�`�Ԃ͖��ڂɊW������ł���B���̂Ƃ��낱�̎v�l�̌����W���������̍ł����ڂ��������Ȃ̂ł���B���̊W�͔����Ō��߂�����₷���A����܂ł��܂��舵���Ȃ���������ł͂Ȃ����Ǝv����B
�Ƃ���Ŏv�l�͊m���ɋ��\�̋�Ԃ����グ��B����͗��O�v�l�ɂ����Č����ł���A��̋��\�͍X�ɐV���ȋ��\�ݏo���B���̍\�������B�͔F���̍l�@�̒��Ŋ��Ɍ��ė��Ă���B�l�Ԃ͂܂��ɋ��\��ςݏグ�Đ��E���\�z���铮���Ȃ̂ł���B
�������悭�l���Ă݂�A���̋��\�͋��琶�ݏo������ł͂Ȃ������������Ă���B
�m���Ɏ��B�͋��\�����\�ݏo���čs���\�������ė����B������������t�ɒH�����Ƃ��A��ԏ��߂ɐ��ݏo���ꂽ���\�ɍs�������B���̍ŏ��̋��\�͂ǂ����痈���̂��B
���\�Ƃ͎������Ȃ����̂ł���A���������ď�ɐV���ɐ��ݏo����Ȃ���Α��݂��Ȃ����̂ł���B���̐��ݏo����Ȃ����葶�݂����Ȃ����̂������\�Ȃ̂ł���B
����Ƌ��\�̑O�ɂ���ݏo�����̂����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ŏ��ɋ��\�͂��蓾�Ȃ��̂��B
�������Ƃ���ƁA����ݏo�����͎̂��݂ł��邵���Ȃ����ƂɂȂ邾�낤�B
���݂Ƃ͊��ɂ����ɂ�����̂ł���A���܂�邱�Ƃ����ʂ��Ƃ��Ȃ����S�Ȃ鑶�݂ł��邩��ł���B
���݂Ƃ͊��ɂ����ɂ����āA���������ɂ���A�i���ɂ��葱������̂ł���B����͌����Đ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����Ɍ��R�ƁA������̂��̂Ƃ��đ��݂��Ă��鐢�E�Ȃ̂ł���B
���\�͏�ɂ��̏o�������邪�A���݂͎n�߂��I�����Ȃ����݂��̂��̂ł���B���\�̌��_�����߂�Ό��ǂ��̎��݂������蓾�Ȃ��ł��낤�B
����������A���݂Ƃ͑S�Ă��B��̑��݂Ƃ��Ă������Ԃ��̂��̂ł���A�������玄��ԂƂ����v�l����鋕�\�̐��E�����ݏo�����ƌ������Ƃ��o����̂��B
��̓I�Ɍ����A����Ԃ̎�l���ł���u���v�ƌ����ϔO���A���ꎩ�͎̂��̖̂������\�ƌ������邪�A����ɐ旧���Ă��̊ϔO�ݏo�������͎̂��̂��̎��݈ȊO�ɂ͂Ȃ��B�u���v���ŏ����炠������ł͂Ȃ��̂ł���B
�Ƃ���ŏ�O�v�l�͂��̎��݂ł������ԂƁA���Ƃ��Ă̎���Ԃ̋��n���Ƃ��āA���邢�͐ړ_�Ƃ��Ĉʒu�t���鎖���o����Ǝ��͍l����B
�����Ƃ���O�v�l�̗̈�͍L���A����Ԃ������ԂɎ���i�K�ɗl�X�Ȏ������܂܂�Ă���B�����Ă��̂قƂ�ǂ̏ꍇ�Ɏ��B�͂����ɂ܂����Ă����\�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B
��������O�v�l�̍ł����������ɂ͌���Ԃ̒��ړI�ȑ̌��Ɨ������ӂ��܂�Ă���A�����ɋ��Ƃ��Ă̐l�ԑ��݂����݂֗����Ԃ点��\��������ƌ�����B
���ɂ��̏�O�v�l�ɗ��������Ă݂悤�B
��O�v�l�͔�_���I�Ȏv�l�ł���Ɗ��ɏ��������A����ɂ͓�̈Ӗ�������B
��͂܂��ɔ�_���I�Ȏv�l�ł����āA�_���Ƃ��ē��ꐫ�������v�l�ł���B����������͍����I�Ș_���ł͂Ȃ��Ƃ��������ł����āA����Εs�����Ș_���v�l�ƍl���Ă�������������Ȃ��B
���̔��e�ɓ�����̂Ƃ��āA����I�v�l�A�_��I�v�l�A�����I�v�l���l������B
���ē�ɂ́A�_���ł͌����\���Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ŕ�_���v�l�ƌ����B����Ζv�_���v�l�ƌĂׂ邾�낤���B�����ɂ͎v�l�Ƃ����������݂��̂��̂ɓ��邱�Ƃɂ�闝���Ƒ̌�������B
�����Ŏ������グ��̂͒����Ɗo�������ӎ��ł���B
�ȉ��������čs�����Ƃɂ��悤�B
�@��_���v�l
�i����I�v�l�j
�O�҂̈Ӗ��ɂ������_���v�l�ɂ́A���Ƃ��Ί���I�Ȏv�l������B�l�X�Ȑl�ԊW��Љ�W�̒��ŁA���B�͂����Ί���I�Ȕ������o������B����I�Ȉӌ��͘_���������Ē��ڐS��ɑi���悤�Ƃ�������ł���A�����̏ꍇ�_���ɍs���l�܂����҂̎��\���ł���B�������܂��A�t�ɌQ�O������ړI�Ŋ���I�Ȕ���������ꍇ������B����͘_���ɍs���l�܂��ĕs���ɋ��ꂽ�Q�O����藧�Ăčs���傫�ȓ���������̂ł���B
�_���ɍs���l�܂����҂ɂ́A�����˂��j�낤�Ƃ��鋭���~�������܂��B�ނ̐S�̒��ɂ͋����s�������[������B���̕s�����͘_���ɂ���ď[������Ȃ�����f���o�������Ȃ��Ȃ�̂��B
�c�_�͂���Ӗ��Ő킢�ł���B�_�҂͗�Âȋc�_�̒��ɁA�����I�ȐS���悹�Ă���B���������̘_�������܂��g�ݗ��Ă��Ȃ��Ȃ�Ƙ_�҂͎���̓����S�����̂܂ܕ\�����邵���Ȃ��Ȃ�B��c���̊���_�҂���ɍU���I�Ȃ̂͂��̂��߂ł���B
���邢�͕����̐悪�����Ȃ��ƌ����s��������B�����ł͉����������Ȃ��ׂɌ��ГI�Ȉӌ��ɖӏ]���A����̂܂܉��̔��Ȃ��Ȃ��ɍs������B�����ɂ���̂͂����_���̌�����������I�v�l�Ȃ̂ł���B
������ɂ��Ă����̊���I�ȕ\���́A�����̍l����_���i���Ƃj
�ɒu�������邱�Ƃ��o���Ȃ����߂ɋN�������̃q�X�e���[�Ƃ������ł��邪�A����������͋t�ɂ��̊���I�Ȏv�l���_���i���Ƃj
���x�[�X�ɂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���B
�Ȃ��Ȃ犴��I�ȑԓx�ɂ͎����𐳓��t���錾�t�����߂悤�Ƃ���ӎ��������Ă���A���ǂ��ꂪ�����Ȃ����ɂ��q�X�e���[�ł��邩��ł���B
����͕�����F�����鎞�̈�̗v�f�ł������B���Ȃ킿�F�����镨���Ǝ����Ƃ̊W�����̎��̊�������肷��̂ł��������A���̊���͕K���������ƂŌ����\���Ȃ����������̂ł���B
�Ⴆ�Ύ��̍D���ȕv�������������Ƃ���B���̎��Ȃ�����ė��Ă��Ȃ��͊̑��������̂����炨���͂��߂ł��ƌ������Ƃ���B
�Ȃ̌������Ƃ͂ǂ����猩�Ă��������̂��B�������v�͂�������Ă��ĂȂ����������݂����ƌ���������m���Ă���B�o���̎v�l���ǂ�������Ƃ���Ȃ�A�ނ̎v�l�͘_���ł��܂��u���������Ȃ����ɂȂ�B�ނ͕��𗧂Ă邩���k���Ĉ��������邵���Ȃ��̂ł���B
����������ł��A�ނ̎v�l�͂͂�����Ƃ������Ƃőg�ݗ��Ă��Ă���B�܂�u���v�Ɓu�a�C�v�Ƃ�����̂��Ƃ��ނ̒��ɂ����đΗ����_���I�Ȗ��������܂�A���������Ȃ����߂Ɋ�������o���B�a�C�Ƃ����}�C�i�X�̊����y��ɂ��āA��������Â���Ƃ����v���X�̊�����܂��B�����Ɏ��Ƃ����v���X�̊����������Ƃ��A�ނ̒��ł��̓�̃v���X����͖������邱�ƂɂȂ�̂��B�����ɘ_��������A���NJ���̋���ɂ���ĕ��������肵�悤�Ƃ���B�����Ŏ������ݏo���v���X�̊���a�C�������Ƃ����v���X�̊���ɏ����āA�ނ͎��Ɏ��L���̂ł���B
�Ȃɐ��~���ꂽ���A�ނ̎v�l�̒��ɂ́u�ȁv�Ƃ������Ƃ������B����ɔ����āA���̍Ȃɑ��ĕ����Ă�������܂ł̎v�����A������B�����ɔނ̍Ȃɑ��銴����ݏo�����B���ꂪ�v���X�̊���ł������Ȃ�A�܂�ނɂƂ��Ă悫�Ȃł������Ȃ�A�ނ̎v�l�͍Ȃɑ���v���X�u���̂��߂ɁA���ƌ����v���X�̎v�l�͎�߂���B�t�ɍȂ��}�C�i�X�ł������Ȃ�A�ނ̎��ɑ���v�l�͂���ɋ��߂��邾�낤�B���̂悤�Ɋ���ɂ��v�l�͘_���Ƃ��Ă͔j�]���Ă��邯��ǂ��A����ł��Ȃ������t�ɂ��v�l�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂ł���B�����v�l�̗��������ɔC���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�������̊ϓ_���猾���Ȃ�A�_���I�v�l�Ƃ����ǂ�����̓y�䖳�����Ă͍l�����Ȃ����������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ犴��͔F���̒��ɕs���Ɍ����v�f�ł���A�X�ɘ_���͔F���������Đ��܂�邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B�����_���I�v�l�́A���̊�������t�ɂ���Ė������Ă���ׂɂ��̊���\�ɏo�邱�Ƃ��Ȃ������̎��ł���B
���̂��Ƃ�}������Ǝ��̂悤�ɂȂ�
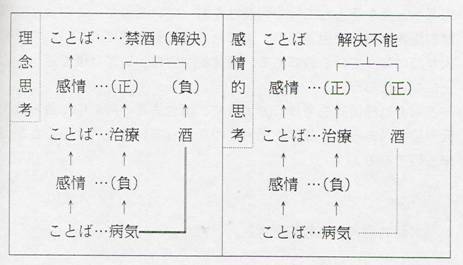
�������Č���Ζ��炩�Ɋ���I�Ȏv�l�͗��O�v�l�Ɠ����`�Ԃ�����Ă��邱�Ƃ�������ł��낤�B
���������Ă����ł�����I�v�l�̋��\�����w�E���邱�Ƃ��ł���̂ł���B����I�v�l�͎�����o�������̐��E�A���Ȃ킿����Ԃ̒��Ő��ݏo���ꂽ����̑Η��▵���ɂ���Ę_�������������v�l�Ȃ̂ł���B
�_�������������Ƃ����ǂ��A�����ɐ��܂�Ă��銴��I�v�l�ɑ��鎩�o�͂���B�ނ͎����ʼn������悤�Ƃ��Ă���̂��m���Ă���̂��B�m���Ă��邩�炱�������ݏo���A���Ȃ��܂�����ė���̂ł���B�ނɂ��Ă݂�A���ÂƎ��Ƃ�����̌��t�ɍ����I�ȉ����������Ȃ�����A���̊����Ɣ��Ȃ͏�ɔނ��ꂵ�߂邱�ƂɂȂ邾�낤�B
���Η�����T�O���Ɏ��������鎖�͌��ǎ������Ă��܂��̂ł���B��������͊���\����������ė��Ȃ��B
���邢�͂��̋�Y���甲���o�����߂ɁA�v�l���̂��̂��������Ƃ��邾�낤�B����Ȃ��Ƃ͖Y���B���Ȃ킿�v�l�����o����ǂ����Ƃ����Ƃ��邾�낤�B
���̂悤�Ȏ���ŁA����I�v�l�͂₪�Ď��̐߂ŏq�ׂ閳���o�̎v�l�ւƐg�𗎂Ƃ��čs���\���������Ă���̂��B����I�v�l�͑�O�̎v�l�`�ԁA���Ȃ킿�g�̓I�v�l�ɂȂ����čs��������ɂȂ��Ă���̂ł���B�g�̓I�v�l�ɂ��Ă͌�ŏq�ׂ邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�Ƃ����ꊴ��I�v�l�͂��̂悤�ɁA��O�v�l�̘g�̒��ōł�����̈ʒu�ɂ����āA�g�̓I�v�l�ƂȂ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��o����̂ł���B
�i�_��I�v�l�E�@���I�v�l�j
�_���̔j�]���A����I�v�l�͊�������̂܂����o�����Ő��藧���Ă����̂ɑ��āA�_��I�v�l�͂��̔j�]���̂��̂��u���b�N�{�b�N�X�ɕ����߂邱�Ƃʼn������悤�Ƃ���v�l�ł���ƌ�����B�����o���Ȃ��o�����⌻�ۂ�_�̗͂ƍl���邱�Ƃł���ȏ�̖₢�����𒆒f���A���ꎩ�g��^���Ƃ��ė������悤�Ƃ���B��������͐_��I�v�l�ƌĂт����B
�_���̔j�]���A�_�����H�v���đU���Ƃ���J�͂̑���ɐV���Ȍ��t�����o���A���ꎩ�̂��ۂ��ƂƂ炦�悤�Ƃ��邱�̍l���̔w�i�ɂ́A���炩�Ɋ���I�v�l�ɂ͂Ȃ��A�������E�F���ւ̈ӎu���F�߂���B�����Ă��̍ł��������̏��ɁA�@���I�ƌĂׂ�v�l�`�Ԃ�����B
���̎����ɂ����ẮA�v�l�ɑ��鋭�����o�������āA�����̑��݂���铹��T����������Ɍ��������낤�B
���_���̒��ɂ����Ă��A�����̈Ⴂ�͂���B�����܂Ő_��Njy���悤�Ƃ���҂ƁA�_�������ӐM����҂Ƃ̊Ԃɂ͖��炩�ɑ傫�Ȏ����̈Ⴂ������̂ł���B
�O�҂ɂ͐l���ɑ���\���I�ȓ����������F�߂��邪�A��҂Ɏ����Ă͎I�ȑԓx�����Ȃ��B
�I�ȑԓx�Ƃ́A���̏@���I�v�l�������^������܂܂Ɏ���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł����āA�K�����������Ɏ��犴���̌�������݂����Ă����ł͂Ȃ��B��������ނ���A�_�ƌ������Ƃ�P�Ɍ��t�Ƃ��ĂƂ炦�Ă��鎟���ł����āA�����ɂ��܂����\����������Ă���B���͂����ɂ�����@���c�̂̋�������B�_�̖��ɂ����ĎE������ݍ����l�X�͂܂��ɁA���̋��\�ɂ���Ė|�M����Ă���̂ł���B
�_�Ƃ͎��݂��̂��̂ł���B�����Ă��̐��Ɏ��B�����S�ɕ`���o����悤�Ȑ_�Ȃǂ͑��݂��Ȃ��B�܂��ɐ_�́A��X�̑z���͂��͂��͈͂��͂邩�ɉz���Ă���B
���B�͎l���������͂邩�ɑ傫�Ȑ��E�A���Ȃ킿�����F���̔F���ɐ����������A���������́A�̂��Ă�Ă�n�F���ɂ��Ă����݂ɑ��đ����ł��o������̂ł͂Ȃ��B
�@���݁��_�́A�����Ă��Ƃł͌����\���Ȃ��S��̐��E�ƌ�����̂ł���B
�Ƃ���ŁA���̐_���C���[�W���悤�Ƃ���A�u���v�Ƃ����ϔO���ɖc��܂��čs���ƍl��������B
�u���v�Ƃ͂��̑̂Ƃ��̓��ʂ��Ӗ����A���̊O���̐��E�͑��҂Ƃ��Ĕ��f�����B�u���v�Ƃ����ϔO�͕��ʂ����܂łŁA�Ⴆ�Ύ��������Ă���֎q�����܂߂Ď��Ƃ͍l���Ȃ����낤�B
�����������ŁA���̊ϔO�̂����Ă���̈���ɍL���čs���̂��B���̈֎q�����ł���B�Ƃ���n�����ł���B�n������͌n�����ł���B���̂悤�Ɂu���v�������Ƃ�����̑̂���F���̑傫���ɂ܂ʼn������A����ɖ����Ɏ����g�債�čs�����Ƃ��A�����Ɍo������u���v�̊��o���ł��_�ɋ߂����낤�B���̂Ƃ����͂܂��ɑS��Ƃ��č݂�B���݁��_�Ƃ͂܂��ɂ��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B
���̌��t�ł͂Ƃ炦��Ȃ����݂�_�Ƃ������t�ōς܂��悤�Ƃ���̂��_��I�v�l�Ȃ̂ł���B
���������̐_��P�Ȃ錾�t�Ƃ��Ď��A�Ⴆ�ΐ_��l�Ԃ̌`�������悤�ȁA�������ȒP�̂Ƃ��Ďv���`���Ă��܂��Ƃ���ɎI�ȑԓx������B�@���̑��������lj��炩�̋������q�Ɋׂ��Ă��܂��̂͂��̂��߂��낤�B�_�ƌ������t���w���������̂�̌������Ȃ��ȏ�A���̎I�ȏ@���I�v�l�����\�ƌ������Ȃ��̂ł���B
���B�ɂƂ��Č��t�͏�ɉ������w���������̂Ƃ��ė��������B���ƌ����Ύ��𐢊E����藣���ē��̒��ɕ`���o�����Ƃ��o����B���邢�͋�C�Ƃ����悤�ȖڂɌ����Ȃ����̂ł����Ă��A��������炩�̌`�Ŏ���Ԃɕ`���o�����Ƃ��o����̂ł���B
���Ƃ���͌n�F���ł����Ă��A���B�͎���Ԃɂ��̉F�����������o���Ă��ꂪ��͂��ƍl���邱�Ƃ��o����B�l�Ԃ̑z���͂͂��ꂮ�炢�ɂ͏\���ɍL���čs�����Ƃ��o����B�����Ă����炭�l�͂��̂悤�ȗ����̎d���Ɋ���Ă��܂��Ă���̂��B
�ǂ�Ȃ��̂ł��A���t���g���Ύ���Ԃɕ`���o������̂Ǝv������ł��܂��Ă���B���邢�͋t�Ɍ��t���Ȃ���Ύ���Ԃɉ����`���o�����A����𗝉����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ǝv������ł���̂��낤�B
���������Ă��̂��߂ɁA���悻����Ԃł͂Ƃ炦��Ȃ����݂�_�ƕ\������̂ł��邪�A���̐_�����t�Ƃ��ē�����ۂ�A���B�͎���Ԃɏ����Ȑ_���o��������̂ł���B����ł͌��ǎ���Ԃ̒��Ɏ��܂��Ă��܂����Ƃ��Ă̐_�ɂ��Ƃ��߂Ă��܂��̂ł���B�ڂɂ͌����Ȃ����A�_�͂ǂ����ɂ��Ď��B��������Ă���ƌ����l�����͂܂��ɂ��̂��Ƃ��Ӗ����Ă���B���̂悤�ȏ@���I�ȍl�����͂��ׂċ��\�ƌ���˂Ȃ�Ȃ����낤�B�����炱���l���E�����E��j�čs���Ă��A�_�̖��ɂ����Đ�����������ƌ����悤�ȋ����Ȏv�z�����R�̂��Ƃ��Ɍ���Ă���̂ł���B
���ꂪ�����^�����̂��̂������\���Ă���̂Ȃ�A���R�̒��a�𗐂��悤�ȍl���͈�؏o�ė��Ȃ��͂��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���E��j��s�ׂ͌��ǎ����Ŏ����������鎖�ɊO�Ȃ�Ȃ�����ł���B�_���v�l����ƌ������Ƃ́A�����Ă�������t�Ƃ��ĂƂ炦�鎖�ł͂Ȃ��B����������̌��t�ɂ���Ďw�������ꂽ���݂̒��ɍs�����Ƃ���ӎu���K�v�Ȃ̂ł���B���̂Ƃ��l�͐_��I�v�l���ł��������ő̌����Ă��邱�ƂɂȂ�B�����Ă�����z�����Ƃ��A
�l�͎��o�̐��E����o���ւƎ���ł��낤�B���Ȃ킿�����ɂ��v�l�̐��E�܂�v�_���v�l�̒��ɓ����čs���̂ł���B
�×���艽�l���̏@���҂����̒n�_���z�����B�����Ă��̑̌������ꂼ��̕��@�ŕ\�����A�㐢�ɓ`���Ă���̂ł���B�����́A�\����̈Ⴂ�����ŁA�`���悤�Ƃ��Ă���{���͓������̂��Ǝ��͍l����B
�i�����I�v�l�E�|�p�I�v�l�j
��O�v�l�ł���ɕt�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͊����I�v�l�ł���B�����I�v�l�̍ł������ʒu�Ɏ��͌|�p�������B
�Ƃ���Ŋ����ƌ������t�������������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ƌ����̂����͂����ň�ʂɎg���Ă���̂Ƃ͏���������Ӗ��Ŋ����Ƃ������t���g���Ă��邩��ł���B
���͊������A���o���ꂽ���o�Ƃ����Ӗ��łƂ炦��B
���B�͐���������ɊO�E����̎h�����Ă���B�܂��̓��ɂ����ẮA�����̊������G�l���M�[�̔g���������N�����Ă���B������Ƃ������Ƃ͂��̂悤�ɁA�g�̂̓��O�ł̂���݂Ȃ��^���ł��邪�A����ɉ����Ċ��o��������B
���_���̊��o�ɘA�����Ċ����~�]�����܂�A���G�ȐS�̐��E�����グ��̂����A���͂��̐��E�̂����A���o���Ė��m�ȔF���̓��Ɏ��グ��ꂽ�����������ƌĂԂ̂ł���B���������āA���o����Ȃ����o�̐��E�������o�ƌĂ�Ŋ����Ƌ�ʂ���B
���Ƃ��Ύ��o���Ƃ��Ă݂��Ƃ��A���B�͖ڂ��J���Ă���Ԓ����������Ă���͂��ł���B���������̎��o���Ԓf�����F�����Ă��邩�ƌ����Δۂƌ��������Ȃ����낤�B
���A�ڂ��J�����Ƃ��悤�B�Ƃ���ɐ��E�����������ė��Ď��o���h������B�l�X�ȊŔ̗������ԊX���݂������Ă���B���͐l�ʂ�̑����X�H�ɗ����Ă���̂ł���B���̂Ƃ����������ړI�̌�����T���Ă���̂Ȃ�A�h�����ꂽ���o�̒�����r����ŔȂǂ��I��F���ɂ̂ڂ邾�낤�B����Ǝ��o�̒��̑��̗̈�͖����o�̐��E�ɉ�������鎖�ɂȂ�B���Ȃ킿�����o�̂܂~�܂�B���Ƃ����̎��A���̖ڂɒʂ肪����l�X��H��̐��낪�f���Ă����Ƃ��Ă��A�����̎��o�͔F������鎖�Ȃ������o�̂܂����čs���̂ł���B
���邢�͎d���ɔ�ꂽ���̐S�ɂӂƎ��R�ɗ����Ԃ肽���~�����o�Ă���A���͈�u�X�H�̕��������A����ɑ������ɖڂ������邩���m��Ȃ��B����Ƃ��̂Ƃ����o����I���̂͂����ɂ��鎩�R�̑����ł����āA�r����G���Ȃǂ͌����o�̂܂ܖ����o�̐��E�ɏ�������B
���̂悤�Ɏ��B�͓���A���ӂ��悤�Ȏ��o�̗ʂ������Ȃ���A�����F�����Ď��o�̐��E�ɕ\���̂͂ق�̋͂����ƌ����Ă������낤�B�قƂ�ǂ̊��o�͖����o�̂܂~�܂��Ă���̂ł����
���o�̒����牽��I�Ԃ̂��͂��̐l�ɂ��B�����Ƃ͂܂��ɂ��̂悤�Ɏ��o���ꂽ���o�̐��E�Ƃ���ɔ��������~�����w���̂ł���B�������A�����A����̊�����̂��́A�܂��ɂ��̐l�̊����ɂ��̂��B
���Ă��̊����͌����܂ł��Ȃ����t�ȑO�̑̌��Ɋ�Â����E�ł���A���B�͂������炱�̑̌������t�ɕϊ����ĕ\�������݂�B
�@������Ĉ�u���������ꂽ�悤�Ȉ������o����B��������ꂢ���Ƃ��A�C���������Ƃ������悤�ɁA�ł��ӂ��킵�����t�ɒu�������Ďv�l���A�\������̂ł���B����𗝔O�v�l�ƌĂB
�@���������ہA���B�͂��̌��t�̑O�ɁA�����ł��̂��l���Ă���̂ł���B��߂Ă����Ƃ肵�Ă���B���̂Ƃ��l�͌��t�ȂǕs�K�v�łނ���ז����Ɗ����邾�낤�B����Ȃ��̂Ɍ��肳��Ȃ������Ƒ傫�Ȉ��炩�Ȑ��E�������Ɍ��Ă���̂ł���B����͂܂��Ɏ��o���ꂽ���o�̐��E�A���邢�͔F�����ꂽ�̊��̎v�l�ł���B
�@���͂���������I�v�l�ƌĂԂ̂��B
�@�����Ƃ͎��o���ꂽ���o�̂��Ƃł���A����ɔ����ċN���銴���~���̑��̂Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ��o����B�܂��Ɋ����͎��B�̓���I�Ȋ��o�ƐS�̐��E�����o���Ă���ƌ����Ă����̂ł���B
�@���̂Ƃ��늴���I�v�l�͎��B�̓��퐶���̒��ŁA�ł��傫�ȗ̈���߂Ă���ƍl������̂ł���B����͘_���v�l�̔w��ɂ����āA��ɂ��̎v�l�̗�����x���Ă���ƌ����Ă������ł��낤�B
�@�Ƃ���Ŋ����I�v�l�̎����������Ȃ��čs���ɂ�āA�����ő̌�����鎖���́A����Ɍ��t�ŕ\�����邱�Ƃ�����Ȃ��Ă���B�����܂ł��Ȃ�����́A���t�����肳�ꂽ�Ӗ��Â������邽�߂Ȃ̂ł���B�����ł��̂��l����ƌ����̂́A�^�������̂܂ܑ̌����Ă���ƌ����Ă������̂ł��邪�A��������t�Ō����\�����Ƃ���ɂ��̐^���͌��t�ɂ���Đ�������Ă��܂��̂ł���A���̊i���͍L�����čs������ł���B
�@�����Ř_���v�l��r�����悤�Ƃ��闬�ꂪ���܂��B�|�p���_�����z���悤�Ƃ��闝�R�͂����ɂ���̂ł���B������������߂���ƌ����̂́A���o�ɑ��鎩�o��p���[�܂鎖���Ӗ����Ă���B�@���o�͎����̐g�̂��F���ƂȂ����Ă��邻�̐ړ_����n�܂��Ă���Ǝ��͍l���邪�A���o�����̂悤�Ȑg�̂̌��n�ɂ܂ŋy�Ƃ����̊����͍ō��̂��̂ƂȂ�A���̂Ƃ����B�͉F���Ƌ��ɂ��邽����̑��݂ł��邱�ƂɋC�Â��̂ł���B
�@�Ƃ����ꊴ�o�ɑ��鎩�o��p���L���鎖�Ŋ����͍��߂��čs�����낤�B�l�͎��݂Ƃ��Đ����Ă���B���̓��I�ȑ̌������o��ʂ��Ď��o�����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�܂�����Ől�Ԃ͂��̑̌���F�����A�\�����悤�Ǝ��݂�B�����Ɍ��t�����܂�_���v�l�����B���čs���̂��B�_���͂��������݂ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B����͂ǂ��܂ōs���Ă����݂̐����ł����Ȃ�����ł���B
�@�����Ɋ����I�v�l�Ƙ_���v�l�̑傫�ȈႢ������B�������������[�܂�ΐ[�܂邾���A���t�ɂ������͓���Ȃ�B�_���v�l��i�߂���ꂾ���Ŏ��݂͕s���R�ɘc��ł��܂����낤�B
�@�����I�v�l�����܂�A�K�R�I�ɐl�͂��̖��ɒ��ʂ���悤�ɂȂ�B�����łȂ�ׂ��_���v�l������ĕ������l����悤�ɂȂ�̂ł���B�����Ɍ|�p�I�v�l������ƌ����悤�B
�@���͂��̌|�p�I�v�l��_��I�v�l�Ƃقړ������x���ōl����B�����傫���Ⴄ�Ƃ���͌|�p�I�v�l�̕������I�ŌǍ��̎v�l�̈�ɓ���₷���Ƃ������ł��낤�B���_����ɂ͈ȉ��̂悤�ȗ��R������B
�@�_��I�v�l�́A��{�I�ɂ͌��t���g�����v�l�`�Ԃ���������A�|�p�I�v�l�͊��S�Ɍ��t����������悤�Ƃ���v�l�ƌ����邩��ł���B���_���t���g���|�p�����邪�A���̏ꍇ�A���t�͉�ƂɂƂ��Ă̊G�̋�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ďg����B�܂茾�t�̂������𗘗p���Ȃ���A�����ɓƎ��̈Ӗ��Â�������̂ł���B
�@���t�̑���Ɍ|�p�Ƃ͎��琶�ݏo�����l�X�ȕ\����i��p����B���̕\����i�ɂ͌��t�̂悤�ɎЉ�I�ɐ��ꂽ���͉̂����Ȃ��̂��B
�@�����t���猾�����̌|�p�Ƃɂ���č��o���ꂽ�\���́A�ޓƎ��̑n���ł����āA�����ċ��L�o������̂ł͂Ȃ��B�Ƃ������邾�낤�B���t�̐��E���猩��A���̕\����i�ɂ��v�l�̓`�B�͂قƂ�Ǖs�\�̂悤�Ɏv����̂������ł���B
�@���������t�Ƃ��������k��E���̂Ă邱�ƂŁA��Ƃ͎���̓��I���E�����R�ɕ\������Ƃ����͂�g�ɂ��鎖���o����̂ł���B�@���̍l���ł́A���̂��Ƃ͔��ɏd�v�ȈӖ����܂�ł���B�l�͂�������V���Ȑl�ԑ��݂Ƃ��ẴX�e�b�v�ނ̂ł���B
�Љ�A���t���������T�O�̂��߂ɂ�����߂ɂ��ꂽ�l�X�́A���̗͂ɂ���Ă��̊����̊ϔO��ł��j���čs���\����̂��B
������ϔO�͒m��ʊԂɎ������`����čs���A����Η��̊k�̂悤�Ȃ��̂ł���B�����ė��O�v�l�͂��̊k�ɒ��菄�炳�ꂽ�I���Ȓm�I�l�b�g���[�N�ł���B
�@���̈���Ől�Ԃ͂��̊k��ł��j���ĐV���Ȑ�����a�������邾���̗͂������Ă���B���̊k��j���ďo�ė����V���̐l�Ԃ̎v�l�͂܂��ɂ��̌|�p�I�v�l�̉�������ɂ���̂ł���B
�@���_�A����̌|�p�Ƃ����ׂĂ��̕����ɐi��ł���Ƃ͌����������Ƃ��낪����B
�@�Ⴆ�ΊG��Ɍ���A�ʎ��悩��S�ۉ�A��ۉ悩�璊�ۉ�A����ɂ̓L�����o�X���̂��̂�ے肷��G��ƌ����悤�ɁA�\����i�͌���̉�������Ƃ߂ĕϑJ���ė����̂ł��邪�A���������܂��|�p�͐l�ԑ��݂̊j�S�ɍs�������Ă͂��Ȃ��̂ł���B
�@���̎�ȗ��R�͕\����i�ɂ���B�l�X�Ȍ`�Ō|�p�Ƃ͗��̊k��ł��j���ė������A�����ɐ��܂�o�����̂́A���x�͎����̕\����i�ƌ����k�����Ă����̂ł���B�����������̌|�p�Ƃ͂����Ŏ~�܂��Ă���ƌ����̂����낤�B
�@�\����i����ɂ��Ă������A�v�l�͊��S�Ɍl�̒��ɕ����ꂽ�܂܂ł���B����ǂ������̍��o�����\����i�Ɍ��t�̂悤�ȋ��L�����Ȃ��͓̂��R�̎��ł��邽�߂ɁA��Ƃ͂���ȏ�Njy���Ȃ��ƌ����̂����ԂȂ̂����m��Ȃ��B
�@�������Ȃ���|�p�̉^���͌����Ă����ŏI���Ȃ��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�|�p�Ƃ͎����̊����I�v�l�𑼂ɓ`���邱�Ƃ��o���Ȃ��ׂɑ��ς�炸�ǓƊ���@����Ȃ�����ł����
�Ƃ��낪�|�p�����߂���ƁA���̌ǓƊ��͂���Ɏ����̐[���Ƃ���ƌW���Ǎ����ւƔ��W���čs���̂ł���B�����Ă₪�ẮA����̕\����i�����ł��j��Ȃ���Ȃ�Ȃ��n�_���K������ė���ł��낤�B
�Ȃ��Ȃ�|�p�I�ȕ\����i�Ƃ͌����A���ꂪ���\�ł��鎖�ɂ͕ς�肪�Ȃ�����ł���B���_���t�����������Ƃ����Ӗ��͑傫�����A�ˑR�Ƃ��Ė��͎c���ꂽ�܂܂Ȃ̂ł���B
�@���̎�i�͌��t�̂悤�ɎЉ�L�̂��̂ł͂Ȃ��A�ɂ߂Čl�I�Ȃ��̂ł��邽�߂ɁA�|�p�Ƃ͎��R�ɓ��ʂ̐��E�ɓ����čs�����Ƃ��o����B�|�p�I�v�l�ɂ���Đl�X�́A���R�ɁA���t�̘g����͂ݏo�������傫�Ȑ��E�������n�߂�B���t����������邱�ƂŐl�͖{�����玝���Ă��鎩�R�ɋC�Â��̂ł���B
�@���������Ƃ����t���������ꂽ�ƌ����Ă��A���̕\����i���̂��̂ɕ߂炦���Ă������́A�\����i�͌��t�Ɠ��������Ɏ~�܂�̂ł���B���̕\����i���ז������Ďv�l�����݂̒��ɓ����čs�����Ƃ͂Ȃ��̂��B
�@�|�p�Ƃ͎��s������J��Ԃ��Ȃ���₪�Ă��̂��Ƃ�m��悤�ɂȂ�B���Ȃ킿�|�p�͕\���Z�p�����ł͐������Ȃ����Ƃ𗝉�����̂��B�����čX�ɂ��̐��ڎw�����̂������A�₪�Ă����ɉ����̂����������ꂽ���g�̐��E���A���Ȃ킿���R�̐��E�ƗZ�������P�Ȃ鑶�݂Ƃ��Ă̎��g������̂ł���B
�@�D�ꂽ�|�p�Ƃ͂����Ɏ��݂��_�Ԍ���B�����ɋN�����Ă���|�p�I�v�l�͎��݂��̂��̂Ƃ��Ă̑̌��ƂȂ�̂��B
�@���̐��E�͐_�ƍ��v����B�����ɑ��݂���|�p�́A���͂�\����i����Ȃ��B�\�����悤�Ƃ����s�ׂ��ӗ~�������ɂ͂Ȃ��B�����Ă��̎҂̎��݂��̂��̂��|�p�ƂȂ�̂ł���B����̂܂܂ɐ����邱�ƂŎ��R�ɐ��ݏo�����G��S�́A����������ɍ炭�Ԃ̂悤�ɐL�т₩�ɍ炫�ւ邾�낤�B���ݑ��|�p�Ƃ����n�_�ł���B�����Ɋ����v�l�̋ɒn������̂��B
�@�@���Ƃ͐_�̐��E�����߂邱�ƂŎ��݂ɂ߂��荇���A�|�p�Ƃ͎��Ȃ̐��E�����߂邱�ƂŎ��݂ɂ��ǂ蒅���B���̂�����̓���i��ł��A���݂ɂ��ǂ蒅�������̎��ɂ́A���t�ɑ������̂��͎̂̂ċ����Ă���B���Ȃł������̗�O�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���݂͂����̌����鎖�ɂ���Ă��������o���Ȃ��B�����Ő��܂��v�l�͂��͂⌾�t�ł����̂ǂ�ȕ\����i�ł���蓾�Ȃ����Ƃ�m��̂ł���B
������ɂ���A�@���I�v�l�ɂ��Ă��|�p�I�v�l�ɂ��Ă��A���̍ł����������Ɏ�������ɖv�_���v�l�ւ̐��E���J���Ă���̂ł���B���̖v�_���v�l�͎��ɏq�ׂ�B
���łɌ����A�����o�̊��o���Ȃ킿�����o�ɂ��v�l�͌�Ŏ��グ��g�̓I�v�l�̗̈�ɓ����čs�����ƂɂȂ�B�t�ɂ܂������v�l�͊o�����邱�Ƃɂ���Ďv�l�̎����Ƃ��čł������v�_���v�l�Ɏ���B�܂芴�o�͐g�̓I�v�l�Ƃ����ł��Ⴂ��������A�ł������v�_���v�l�̎����Ɏ���܂ł́A���ꂼ��̎v�l�̗v�f�Ƃ��Ĉʒu�t������̂ł���B�@�����܂ł��Ȃ����o�͉F���̍����ł���ӎ����琶�ݏo���ꂽ���̂ł���A��̘_���́A�v�l�����̊��o��y��ɂ��Đ��藧���Ă��鎖����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@����܂Ō��ė����悤�ɁA�v�l�͋��\�����o�����A���̎v�l���̂͂��̂悤�Ɋ��o�ɂ���Ċт���A�F���ƈ�̂ɂȂ��Ă���̂ł���B�����ɂ͎��݂�����B
�@�A�v�_���v�l
�@�@�i�����E�F���ӎ��j
�@��O�v�l�̒��ł��A�_���ł͕\�������Ȃ��v�l��v�_���v�l�ƌĂڂ��B
�@�v�l�������Ă���ɂ�������炸������ǂ��\�����Ă����̂�������Ȃ��ƌ����̌��͒N���������Ă���B���̒��̂����炩�͒m���s���̂��߂ɂ��̍l����_���ő�ُo���Ȃ��ƌ������Ƃ����邾�낤�B�܂����̒��̂����炩�́A�����̎v��������Ɏ����Ȃ��炻��������\�����t���Ȃ��Ƃ�����������B�����čł��܂�ɂ͐^���ڑ̌����Ă���悤�Ȏv�l�����݂���B
�@���x�����ė����悤�ɁA���Ƃ͎��݂���ꕔ��������ė������̂ł����āA����͌����Ď��݂��̂��̂ł͂Ȃ������B���Ƃɂ���đg�ݗ��Ă�ꂽ�v�l�͂��̈Ӗ��ł��ׂċ��\�ł���Ǝ��͎咣����̂����A����͍l���Ă�����e���̂��Ƃ͎��݂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�i�Ԃ̂��Ƃ��l���Ă��A�l���̒��̉Ԃ͎��݂ł͂Ȃ��j
�@�������܂�ɂ́A������z����v�l�����݂���̂ł���B���ꂪ�����ł���B
�@�����ɂ��Ă͂���܂ʼn��x���q�ׂė������A���t����Ȃ��Œ��ڎ��݂������Ă���B����͎��݂�S��Ƃ��ĂƂ炦�闝���ł���A�v�l�ƌ������͎��݂��̂��̂ɓ����čs�����ł���B���݂Ƃ��Ắu���v�ɋC�Â����Ƃ��Ȃ킿�o�����邱�Ƃł���B
�@�@���Ō�����肪���̎����ɓ����邾�낤�B
�@���������_�A�����͂��̊o���̐��E�ւ̓�����ɉ߂��Ȃ��B�����Ă��̌������ɂ��[���v�_���v�l�̐��E���L����̂��B
�@���_���̎v�l�͎��B�̓���̂��̂ł͂Ȃ��B���͂��ꂪ�\���ƍl���邪�A�_���v�l�Ɋ��ꂽ���B��������̂ĂĖv�_���v�l�ɓ���̂͗e�ՂłȂ��̂������ł��낤�B
�@����Ŏ߉ނ�L���X�g�̂悤�Ɋo�������l�X�̏o�����������Ǝ��͎v���̂ł���B
�@�Ƃ���Ŏ��B���܂�ɑ̌�����v�_���v�l������B����͂Ђ�߂��ƌĂ����̂ŁA�����̈�ł���B
�@��������l�������Ă��āA�_�����s���l�܂����Ƃ��A�����̂��������łЂ�߂����N����A������������B����ȗ�͊�����邪�A���̂Ђ�߂��͘_���ւ̎��������邫�������Ŋɂ݁A�v�l���u�ԁA���ڎ��݂ɐG��鎖�ɂ���ċN������̂ƍl������B
�@�Ђ�߂��͂��̂悤�ɏu�ԓI�Ɍ���钼���ł���B���̒��������\�̒��ɐ�����l�Ԃ����݂̒��Ɉ�������铭�������Ă���̂��B�@���ہA�_���i���Ƃj�ɂ͌��E������ �B���B�͂��̘_�����g���Đ��E�����ɂ߂悤�Ƃ��邪�A���R�̂��ƂȂ��炻�̎��݂͌��E���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B���̂Ƃ��_���̊O�ɏo�Ď��݂����ޓ���������̂������Ȃ̂ł���B�����Đl�Ԃ͂��̒����̂��^����_�����g���Č����\���H�v������B�������ĉ�X�͈�������݂̒��ɔF�����鐢�E���L���čs���̂ł���B�����ɉȊw�╶���̔��B���čs���d�v�ȗv��������̂��B
�@��{�̖ɗႦ��A�_���͖̒��S�𐬂��ؕ��ɂ�����A�����͖̐����_�ɂ�����B�l�ԎЉ�͂܂��ɂ��̖���������悤�ɊO�֊O�ւƐ��E���L���čs���̂ł���B
�@�����͎��݂̐��E�ڗ�������v�l�ł���B��Ɍ����@���I�v�l�͂��̎��݂�_�Ƃ������t�ɒu�������Ďv�l��g�ݗ��Ăčs�����A�v�l�����^���Ɍ��������Ƃ���ƁA�K�R�I�ɂ��̐_�ƌ������݂ɑ���Ƃ炦�����ς���Ă���B
�@�܂�A�_�����t�Ƃ��ĂƂ炦�鎟������_�Ƃ������t�̎w���������̂ւƈӎ��̌������Ώۂ��ς���Ă���B���̕����͖��炩�Ɍ��t����n�܂�A�₪�Č��t�̎w���������̂��̂��̂Ɍ������B�����Ă��ɂ͌��t���̂��̂��z����n�_�ɂ���Ă���̂ł���B
���邢�͊����I�v�l�ɂ��Č����A���t���������ꂽ��莩�R�Ȑ��E��B�l�͂��̒��Ŏ����̓��ɋN�����Ă��銴�������̂܂ܑ̌����A���E��F������̂ł���B
�@����������ł��A�����ɂ͂����炩�Ȃ�Ƃ����݂���̋���������B����͎��݂��̂��̂Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B
�@���B�����݂��̂��̂ɗ����������Ƃ��A�����ɂ͎��݂ƔF���̊Ԃɂ��������̌��Ԃ��Ȃ��B�����ł͎��݂��F���ł���A�F���������݂ł���悤�Ȋ��S�Ɉ�̂ƂȂ������݂Ɏ���̂ł���B
�@������̋L�q�ɂ͊ԈႢ������B���̂Ƃ���͎��݂ƔF������̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�F�����̂��̂���������̂ł���B
�F���́A���Ƃ̊W�ŔF���Ώۂ𗝉����邱�Ƃł��������A���̎��Ƃ������݂����݂̒��ɏ����Ă��܂��̂ł���B�����ɂ���͎̂��Ƃ̊W�ł͂Ȃ��A�������݂��̂��̂ƂȂ�̂��B
�@�܂�v�_���v�l�ɂ����ẮA�F����̂��̂��̂������Ȃ��Ă��܂��̂ł���B���������Ă����ł́A����ԂƂ������E�����݂��Ȃ��Ȃ�B�����ɂ͂�������Ԃ݂̂̐��E���������ł���B�@�F����̂̂��Ȃ��v�l�ȂǂƂ����̂́A�v�l�Ƃ͔F�߂����������m��Ȃ����A���͂����Ă�����A�l�Ԃ��B���鎖�̂ł���ō��̎v�l�ƌ��Ȃ��B
�@�v�_���v�l�ɂ���āA�l�͎���Ԃz������ԂɎ���B���������ۂɂ͌���ԂɎ���̂ł͂Ȃ��B���B�͊��ɂ��Ƃ��Ƃ������Ԃɂ������̂ł���B��������Ԃ��������邱�Ƃɂ���Č���Ԃ������ė����Ƃ����ɂ����Ȃ��B
���̌���Ԃ̒��ł́A���B�͂ǂ�����ǂ��܂ł��������ƌ����悤�ȋ�ʂ����S�Ɏ����A�S�Ă���̑��݂ɉ��������B����͂������݂������Ă���̂ł���B
�@���݂͂���܂łɈ�x�����܂ꂽ���Ƃ��Ȃ��A�܂����ʂ��Ƃ��Ȃ��B���Ȃ킿���݂͎n�܂���I�����Ȃ��S��̑��݂Ȃ̂ł���B�@���̎��݂̏�ɔF����̂����܂�A����Ԃ����o���B����͂��邢�͎��݂����閲���ƌ����Ă������낤�B�v�l�̋��\���͂܂��ɂ��̂��Ƃ𗠕t���Ă���̂�������Ȃ��B
�@�������n�߂����݂͂₪�Ă��̖�������߂Ď��݂��̂��̂ɋA���čs���B���̗���̒��ʼn����N�����Ă���̂��낤���B�����ɖڂ����A�����o�����o���o���Ƃ����ӎ��̕ω��ɋC�Â����낤�B
�@�ŏ����݂͂��������̒��ł����߂��Ă���B���̂����߂����ꎩ�̂������Ă���u�����v�����o�Ƃ��Ď��o����悤�ɂȂ�ƁA���ꂪ���ݏo���v���ƂȂ�B���������̖����A�₪�Ă͊o������B�ڊo�߂ɂ���Đl�͎������̂��̂𗝉�����悤�ɂȂ�B
�@���̈�A�̗���́A�����̎��݂Ɍ������Ă��A�₪�Ă��̎��݂����B�̋C�Â��̂��ƂɌ���o�邻�̉ߒ��������Ă���̂ł���B�@�����l���Ă���Ǝ��B�ɂ́A�͂邩���݂��z�������ɋC�Â��Ƃ������݂������Ă���B���̓_�ɂ��Ă͎��͂Ŏ��グ�邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@�Ƃ�����A���̎��݂̖��̉ߒ������A���B�������ǂ��Ă���v�l�̂��ꂼ��̌`�̒��Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B
�@�̂��Ă�Ă�n�F���̍\�����猩��ƁA���̎n�܂�͎��݂̒��ɐl���`���G�l���M�[�̑��������܂ꂽ���_�ƍl������B
�@���̑����̗͂ƉF���̗͂̓����ɂ���āA���������F���̖A�̂悤�ɐ��E���番������`�Ŕ����I�ȉo���オ�����B���ꂪ�l�ł���B���݁��F���Ɛl�̐ړ_�Ɋ��o�����܂�A��������o���邱�ƂŐl�́u���v�����o���čs���B���Ȃ킿�F����̂����܂��̂��B�@�F����͖̂������n�߁A�₪�Ă����Ɏ���Ԃƌ����傫�Ȗ���Ԃ��`���̂ł���B����͂܂��Ɏ��݂̌��閲�ƌ�����ł��낤�B�@�v�l�ɂ���Ė��͂������������Ă��邲�Ƃ��ɓ����o���B����Ԃ͐�������������̂��B
�@�Ƃ��낪���̎v�l���E�Ƃ������鎄��ԂɉB���ꂽ���\���ɋC�Â��n�߂��Ƃ�����l�͊o���̓�����ݎn�߂�B
�@�^�������߂悤�Ƃ���M�ӂ́A�₪�Ė�����葱���Ă���u���v�A���Ȃ킿�F����̂̑��݂ɋC�t���悤�ɂȂ邾�낤�B�^�������߂Ȃ��炵�������̐^������l���������Ă������̂́A�������낤������͎������g�ł������̂��B
�@�����Ɏ����Đl�͊o������B�o���Ƃ͎��݂̖ڊo�߂ł���B�o�������ӎ��͎��݂Ɛ키���Ƃ���߂邾�낤�B�����͎��͎��݂��̂��̂ł������̂�m��A���ɂ͎��݂ɋA���čs�����낤�B�����ɂ͋�Y����ɂ��Ȃ��A�~�]�����������������E�������c�邾�낤�B
�@���S�Ɂu���v�͎����A���݂̂܂܂ɂȂ�B���܂ŗ~�]�Ǝv���Ă������́A���Ƃ��ΐH�~��~�Ȃǂ��A�{���̂Ƃ���͎��݂̈�̂����߂��ł������̂��B��������̗~�]�Ǝv���n�߂Ė������ݏo���ꂽ�̂ł���B
�@�l�͊o���Ɏ����āA���͂��̂��̂ɋ�ʂ�����K�v���Ȃ��Ȃ�B�������琶�܂��v�_���v�l�́A���ʂ͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��A�܂��ɖ����ʂ̐��E�Ƃ��Ă̗�������n�܂�B
�@ �v�_���v�l�́A�F����́������̂��̂����݂��Ȃ��v�l�ł���A���������Ďv�l�͂��͂⎄���z�����A���݂��̂��̂̎v�l�Ƃ�������B����Ώ����Ȉӎ��A�o�������ӎ��Ƃ��ė������邱�Ƃ��o���邾�낤�B���̖v�_���v�l�̂��������́A���܂������F���Ƃ̂Ȃ�����������v�l�ł���B����͌���Ύ��̉e���c�����v�_���v�l�Ȃ̂ł���B
�@���邢�͂�����������B���Ȃ킿�����ɂ���ĕ����ꂽ�l�Ƃ��Ă̑��݁A���Ȃ킿�P�Ȃ鑶�݂Ƃ��Ă̊o���ł���B�P�Ȃ鑶�݂ł��鎄�̐g�̂ɐ��܂�銴�o�̑S�ʂɂ킽�鎩�o�Ȃ̂ł���B
�@�v�l�̐����͂₪�Ď��̎����ɓ��B����B���Ȃ킿�������܂߂��F���S�̂Ƃ��Ă̊o���ł���B�����ł͂��͂⎄�͊��S�ɏ��ł��A�i���̖��ƂȂ�B���ꂱ�����F���ӎ��ł���A���B�̏I���_�ƂȂ���̂ł���B
�@�F���ӎ��ւ̊o���ɂ���āA�n�߂Ď��B�͎��������҂ł���������m��B�����ɂ͎����ȊO�̂Ȃɂ��̂����݂��Ȃ��B
�@���B�͂����ɁA�v�l�����܂��O�̖������݂Ƃ͈Ⴄ�傫�Ȋu��������邱�Ƃ��o���邾�낤�B
�@�܂���݂���v�l�����܂�A�o�����Ď��݂ɋA�邱�̓����́A���Ƃ̖؈���ɂȂ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B
�@���݂͎v�l�̉ߒ����ւĂ悤�₭�o������B�o�����Ȃ����݂͂����ł̒���忂��Ɏ~�܂�A�G�l���M�[�̊������J��Ԃ��B�o�����Ȃ�������݂͖����̂܂ܑ��݂��邵���Ȃ��B�o���Ɏ���Ȃ����͉��x�����܂�ς��A�����悤�ȋ�Y���J��Ԃ��ƌ����悤�ȏ@���I�ȍl���́A���̎������������̂��Ǝ��͍l����B
�@���Ď��B�͂��������C�ɉ��~���Ė����̎��݁A���Ȃ킿�v�l�����ݏo�����n�_�ւƖڂ������čs�����B���B�����ǂ��ė����v�l�̂��̓�����Ƃ������ׂ��A���݂̐��E�A�����ɐg�̓I�v�l�����݂���B
�S.�g�̓I�v�l
�@�g�̓I�v�l�͖{���A�v�l�ƌĂтɂ��������o�̗̈�ɂ�����v�l�ł���B�������v�l���G�l���M�[�̔g���Ƃ��ĂƂ炦��Ȃ�A�������܂���A�̎v�l�ł���ƍl���č����x������܂��B
�@�Ƃ���Ŗ����o�̎v�l�̒��ɂ��A���̎����ɂ���Ċ���̌`�ɕ����邱�Ƃ��o����B
���̈���K���ɂ��v�l�ł���B��̎v�l���K�������邱�Ƃɂ���Ė����o�̗̈�ɑމ�����B������K���I�v�l�ƌĂڂ��B
�@��߂ɂ͖����o�̊���ɂ��v�l�ł���B������������͎������g�̑̓��ɐ��܂��u���E�s���v�̉�������ɐ��ݏo�������̂ł������B�g�̓I�u���E�s���v�͎��������݂�����萶�܂�o�Ă���̂ł����āA�܂肻���ɂ͓��R�Ȃ��疳���o�̊�������݂����ł���B�u���E�s���v�͐l�Ԃ����܂��Ɠ����ɑ��݂����̐����𑣂��čs�����̂Ől�Ԃ����藧���{�����̌���Ƃ�������B�����ł���ɕt������v�l��g�̎v�l�Ɩ��t���邱�Ƃɂ��悤�B
�@�O�ɂ͊��o�ɂ��v�l������B�����܂ł��Ȃ�����͑̊����邷�ׂĂ̊��o�ɂ���ē�����̌��Ƃ��Ă̎v�l�ł���B���o���ꂽ���o�������ƌĂ�Ŏ��o����Ȃ����o�Ƌ�ʂ������A�����ł͂܂��ɂ��̖����o�̊��o������B����������o�v�l�ƌĂԁB
�@�����čŌ�ɖ��I�v�l��������B����͎��B����O���Ō��ė��������ɑΉ�����B���Ȃ킿�����ƕs�����̊Ԃɑ��݂��閳���Ƃ����̈�ɂ��v�l�ł���B
�@���͂Ƃ肠�����A���̎l�̎v�l�`�Ԃ��o����B������ȉ����čs�����Ƃɂ��悤�B
�i�K���I�v�l�j
���B�̓�����悭�ώ@���Č���ƁA���o�Ȃ��ɓ����Ă��邱�Ƃ��v���������������ƂɋC�Â����낤
�m���Ɏ��B�̐����̂قƂ�ǂ̕����͏K���ɂ���ē����Ă���B�@�������܂肫�����悤�ɒ��̐��ʂ����A���܂������ԂɐH�������ĉƂ��o��B�����ς��ʌ��i�����Ȃ���E��ɓ�����Ɍ������B���܂������ԂɑގЂ��āA�����������ǂ��ĉƂɋA��B���̐����̃��Y���̒��Ŏ��B�͈�̂ǂ�قǂ̎��o�������Ďv�l�����Ă��邾�낤���B
�@���邢�͓��̒��������̐S�z���ň�t�̂��߁A�J��Ԃ����̐S�z����������ł���B�C�������炢�̊Ԃɂ��w�̃v���b�g�z�[���ɗ����Ă����ƌ����悤�Ȍo���͂�����ł�����B
�@����Ȃ��Ƃ��o����̂́A�Ƃ���w�܂ł̊���e����������ł���B���ꂪ���߂Ă̓��ł������Ƃ���Ȃ�A�ނɓ����S�z�����������Ƃ��Ă��A���ӂ͓����̂ق��Ɍ������ĐS�z���͓�̎��ɂȂ邾�낤�B�����ԈႦ�Ȃ��悤�Ɉ��ڕW���m�F���Ȃ���A�i��ōs���ɈႢ�Ȃ��B�ނ͂��̂��߂ɐS���g���A�v�l�͂��ׂ̈ɒ��Ӑ[�������Ă���͂��ł���B�ނ̎v�l�͌��݂��̏u�Ԃ̎����̍s���ƒ������Ă��āA���m�Ȏ��o�̂������ɗL��B
�@����Ɠ����悤�ɁA���B�͉����ł��ŏ��͒��ӂ��W�������Ă��̎��ɑΉ����A�v�l�����B�����Ă����ɂ͎v�l�ɑ��閾�m�Ȏ��o�����݂��邾�낤�B
�@�������������Ƃ��J��Ԃ��Ƃ��ꂪ�K��������A���̎v�l�ɑ��Ĉ�X���ӂ��Ă��Ȃ��Ă��A���m�ɍs���o����悤�ɂȂ�B�܂�Đ��ōs������悤�ɂȂ�̂ł���B
�@����Ɠ��R�A�v�l�͕ʂ̊S���ƂɌ������o�����낤�B�l�͕����Ȃ���C�ɂ�����d���̂��Ƃ�A������̂��ꂱ����l���n�߂�B�����̏u�Ԃ��������������Ă��邩�͂������̂��ŁA�v�l�͂���Ƃ͖��W�ɓ����n�߁A�l�X�ȋ�z�����炷�̂��B���̂Ƃ������o�̕��ɉ��������v�l���K���I�v�l�ƌĂԂ̂ł���B
�@�����K���I�v�l���v�l�Ƃ��Đ��藧�̂��ǂ����ɂ��ẮA�����c�_���K�v���낤�B
�M���͐ԂŎ~�܂�A�Ői�ށB����͎��B���q���̂��납�狳�����܂ꂽ�Љ�̎�茈�߂ł���B�����Ŏ��B�͓��H������Ă���ƕK���M���@�̑O�Ŕ��f�𔗂���B���Ȃ��Ƃ��M���̐F�f���Ȃ���Έ��S�ɓ��H��������Ƃ͏o���Ȃ����낤�B�Ƃ��낪�l���������Ă��Ēm��Ȃ��ԂɐM����ʂ蔲���Ă��܂��Ă��鎖������B��ŋC���t���āA�ǂ̂悤�ɂ��ē��H�����f�����̂��ǂ����Ă��v���o���Ȃ��ƌ����悤�Ȃ��Ƃ������Ē��������Ƃł͂Ȃ����낤�B�Ƃɂ���������������͐g�߂ɂ�����ł�������͂��ł���B
�@�ʂ����Ă��̎��A�v�l�͓����Ă��Ȃ������̂��낤���B���͂������A�v�l�������Ă��Ȃ������Ƃ͂ǂ����Ă��v���Ȃ��̂ł���B�����v�l�������Ă��Ȃ��Ƃ�����A�l�͂ǂ����ĐM���@�f�o���邾�낤�B�ǂ����ē����ԈႦ���ɐi�߂邾�낤�B
�@�K��������������ƍl�����Ƃ��Ă��A����Ŏv�l�̑��݂�ے�o���Ȃ��͂��ł���B�Ȃ��Ȃ炻�̎��͏K�����v�l�̓��������Ȃ����蓹�𐳊m�ɐi�ނ��Ƃ��o���Ȃ�����ł���B�܂�v�l���K���Ƃ������t�Ō���������ꂽ�����̂��Ƃł����āA�c�_�Ƃ��Ă��܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ����낤�B
�@�܂��M������������̂́A�P�Ȃ�����Â��ł����Ďv�l�ł͂Ȃ��ƌ����l�����o�Ă��邾�낤�B�ނ͂��������o�̂����ɏ������˂��Ă��邾�����Ƃ�������̂ł���B
�@���͂����ے肷����̂ł͂Ȃ��B�t�Ɏ��͏������˂��܂��v�l�̈���ƌ��������̂ł���B�@���������v�l�͏������˂̐ςݏd�˂�ꂽ���̂��Ǝ��͍l����̂��B�Ⴆ�Θ_���I�Ȏv�l���������邽�߂ɂ͏������˂��Ȃ��Ă͍l�����Ȃ��B�`�Ȃ�a�A�a�Ȃ�b�A�b�Ȃ�c�A�_���͂��̂悤�Ɏ��X�Ə����f���Ȃ��猋�_���o���B���̒��ɂ͖��炩�ɏ������˂��܂܂�Ă���̂ł���B�@�Ⴆ�`�Ȃ�Ή��̋^�����Ȃ������I�ɂa�Ƃ����l�������܂��ƌ����悤�Ȏ���͂�������B�Ȃ�i�݁A�ԂȂ�~�܂�Ƃ��A��l�̒j�ƌ��������Ă��̎҂����l�j�q���v�������ׂ�ȂǁA��������肪����܂��B���̑Đ��I�Ȏv�����݂̎v�l�́A�������˂Ƃ����Ă������Č����߂��ł͗L��܂��B
�@�v�����݂̋����l���́A���������Ƃ���ŊԈ���Đ������������o���Ȃ��ƌ����悤�Ȃ��Ƃ������B����́A���̎v�����݂̕����ŏ������˂��Ă��邩��ɊO�Ȃ�Ȃ����낤�B�ł������I�ł���͂��̉Ȋw�҂ł����A���̌����̒��ɂ��̂悤�Ȏ�������o�����Ƃ͂���������Ƃł͂Ȃ��B
�@�܂�����ɂ���Ďv�l�������Ă����ł����āA�����l����Ȃ猋�ǂ̂Ƃ���������˂͎v�l�̈�`�Ԃ��ƌ�������̂ł���B
�@�������˂����K���I�v�l�̌���ƌ������Ƃ��o����̂ł���B
�@���̌���Ƃ���A�K���Ɋׂ��Ă��A�v�l�͓����Ă���̂��B�������̎v�l�͎����I�ɓ����Ă��邽�߂ɒ��ӂ͂ǂ����Ă��ɖ��ɂȂ��Ă��܂����낤�B���̂��߂ɋ����͎��R�A�ʂ̍l�����Ɉڂ��Ă��܂������ɂȂ�B�������Ē��ӂ��O�Ɍ��������߂ɁA���̏K���I�v�l�͎��o����Ȃ��܂܁A�܂��Ɏ����I�ɓ����Ă����̂ł���B
�@�������ĉ��x���J��Ԃ��ďK���I�ɂȂ����v�l�́A���o���Ȃ��Ă��K���ǂ��蓭���̂��B
�@���߂Ď����̎v�l�ɖڂ������Ă݂�A�K���������v�l�̑������Ƃɋ������낤�B�����Ȃ����Ă��铮��┻�f�̂قƂ�ǂ͏K���I�v�l�ƌ����Ă������낤�B�ӂƂ������ƂŎ����̂��Ă��邱�ƂɋC�t������A�ڂ��肵�ċ��邤���ɂӂƉ�ɕԂ����肷��B����Ɨ[�H�����ɂ��邩�l���Ă��������ɋC�t���Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂�����ł����邾�낤�B
�@����͋C�t�����Ƃ��ɓˑR���̎v�l���n�܂�Ƃ����̂ł͂Ȃ��͂��ł���B���̂悤�ȍl�����͂��܂�ɂ��s���R�ł��邵�A�����I�ł͂Ȃ��B�������Ƃ���Ǝv�l�͊m���Ɏ����̋C�t���Ȃ����ł��N�����Ă���̂ł���B�@
�@�킽���̌���Ƃ���A�K���I�v�l�͏������˓I�ł���A�������_���I�ȗv�f�������Ă���B�܂�K���I�v�l�͗��O�v�l�̒��ԂȂ̂ł���B���O�v�l���K�����������o�̓��ɐi�߂���v�l�����K���I�v�l�ƌ����邾�낤�B
�T���ė��O�v�l�́A�^���ɑ��Ă���𐳖ʂ���������悤�Ƃ���v�l�ł���B����䂦�ɂ܂��^������ł������v�l���Ƃ��������̂ł���B���O�v�l�͂����^�����w���������Ƃ����o�����A�����Đ^�����̂��̂ɐ�����Ă��܂��悤�Ȏv�l�ł͂Ȃ������B
�@�Ƃ���ł��̏K���I�v�l�ɑ��Ă��܂��������Ƃ�������̂ł���B���o��Ȃ��v�l�ł͂����Ă��A����͌��Ǘ��O�v�l���K�����������̂ɉ߂��Ȃ��̂ł����āA���ӂ̌������Ȃ��Ƃ���Ŏv�l�͑������Ă���̂ł������B
�������܂����̎v�l�͌����Ă���ȉ��̎����ɂ͉���čs���Ȃ��ƌ������Ƃ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ȉ��̎����Ƃ����͎̂��ɏq�ׂ�g�̎v�l�̂悤�ɁA���]�̓����Ƃ��Ă͂Ƃ炦���Ȃ��v�l��O���ɂ����Ă���B
�@�܂肱�̏K���I�v�l�͗��O�v�l�ƂȂ����Ĉ�̎v�l�̗̈�����̂��B���ǂ̏��A����͓��]�̓����ɂ��v�l�̈�Ȃ̂ł���B
�@���邢�͂����������邾�낤�B���Ȃ킿�K���I�v�l�����͗��O�v�l�Ȃ̂ł����āA����͎��o���Ă��邩�����o���̈Ⴂ������ɉ߂��Ȃ��B���O�v�l�������������悤�ɁA�K���I�v�l���܂��T�^�I�ȋ��\�̋�Ԃ����o���̂ł���B���������ďK���I�v�l�͗��O�v�l�������ł������悤�ɁA�����ċ��\�̐��E����o�邱�Ƃ͂Ȃ��B�܂���݂Ɏ��鎖�͂Ȃ��̂ł���B
�@���̗̈�̎v�l�͍ł��l�ԓI�Ȏv�l��ԂƂ������A�{���A�v�l�ƌ������̗̈���w���͓̂��R�����m��Ȃ��B
���ۂ��̗��O�v�l�����t�����o�����̂ł���A���̂��Ƃ��w�������T�O�⒊�ۓI�Ș_���ݏo���A���ׂĂ̂��̂�����\�Ȑ��E�ɕς��悤�Ɠ����B���t�ɂ���Đ��E���敪���A�ی����������ȒP�ʂɐ��E�ʂ��čs���̂ł���B���ꂪ���O�v�l�̍ł��傫�ȓ����ƌ������Ƃ��o����B
�@�����Ă��̂��Ƃ��t�ɋ��\���̌��ƂȂ��Ă��鎖�����B�͌��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@���̎v�l�͐g�̂Ƃ͂������Ȃ��A�����ɐ��_�I�Ȏv�l�ƌ������Ƃ��o���A�ł��l�ԓI�Ȏv�l���E�����グ�Ă���̂ł���B
���ǏK���I�v�l�͗��O�v�l�̈ꕔ�ł���A���������o�̈ł̒��ɉ�������Ă��邾���ł����āA���ӂ�������������Ăі��m�ȗ��O�v�l�Ƃ��ĕ����яオ��v�l�Ȃ̂ł���B
�i�g�̎v�l�j
�K���I�v�l�����O�v�l�̈ꕔ�Ƃ��čl������v�l�������̂ɑ��āA�g�̎v�l�͊���I�v�l�̈ꕔ�Ƃ��ė������邱�Ƃ��o����B
���Ȃ킿�g�̎v�l�͎��o����Ȃ�����ɂ��v�l�Ȃ̂ł���B�������g�̎v�l�́A����̍\�����̂��̂ɑΉ����A�ŏI�I�ɂ͎��݂��̂��̂ł���ӎ��ɒ������čs���v�l�ƌ������Ƃ��o����̂ł���B
���B�͂���܂łɊ���ɂ��āA�G��ė����B�i��R���j����ɂ��Ί���́A�F����̂ƁA�F���ΏۂƂ̑��݊W���琶�ݏo�����P�������̔��f�����̊�{�ƂȂ�B�����Ă��̊W��������邽�߂̍ł����{�I�ȑ��u�́A���̓��ɐ��܂������ƁA�s���Ƃ�����̑�����������������̂ł���B��������B�͐g�̓I�u���E�s���v
�ƌĂB
���̐g�̓I�u���E�s���v�Ȃ�����́A�l�������Ă�������Ɏ����̐g�̂Ɋ�������̂ŁA����ΐ������Ƃ������邾�낤�B�܂��ɂ���͐��������ɑ���g�̂̊����Ȃ̂ł���B����͕\���ȑO�̑̌����̂��̂ł���B�l�͂�����u�����v�Ƃ��Ď��̂��B
�u���E�s���v�̌����d�g�݂́A�F���̉^���Ɛg�̂̐��������Ƃ�����̃G�l���M�[�̑����ɂ���B
�����������F���̗���ɏ]�����ɂ͉��������܂�A����ɔ�������̂ɑ��Ă͕s�����Ƃ��Ď������������݂���B���̉����ƕs�����̓V�[�\�̂悤�Ɍ��݂Ƀ��Y�������Ȃ��猻��A���̌��ʐV��ӂ��i�݁A�g�̂��������čs���̂ł������B
���̐g�̓I�u���E�s���v�͂₪�Đ��_�I�u���E�s���v�ɔ��W���A�F���Ƃ����܂��Ċ���ݏo���̂ł���B
����̔w��ɂ́A�܂��ɂ��̂悤�Ȑl�ԑ��݂̍ł������I�ȕ����ɘA�Ȃ��čs�������̃V�X�e�����B����Ă���̂ł���B�����̒��ɂ͎��o����Ȃ��܂܂ő��݂��Ă���g�̓I�u���E�s���v���\���l������̂ł���B
�����Ŋ���ɂ��v�l�ɂ́A���B������I�ɑ̌����邢���銴��I�v�l�ƁA�����o�Ȋ���̗̈�ɑ��݂���v�l���l������B
���̂�����҂�g�̎v�l�Ɩ��t����̂ł���B�g�̎v�l�̍ł��[�������ɐg�̓I�u���E�s���v�����݂���B����́A�������ێ�������������ׂ̂����Ƃ���{�I�ȑ��u���ƍl������B
���������Ă��Ƃ����ꂪ�����o�̒��ɂ������Ƃ��Ă��A�g�͎̂��琬�����邽�߂̐����̎������u���E�s���v�Ƃ��Ĕ��ʂ��Ă���ƍl������̂��B���͂�����܂��v�l���Ǝ咣����̂ł���B
�Ⴆ�ΐ��܂ꂽ����̐����ɂƂ��āA�u���E�s���v�̔��f�͖��炩�ɖ����o�̈ł̒��ɕ�����Ă���B����͑S���̖����o�̂܂܂ɉc�܂�鐶���������̂��̂ł���B
���́u���E�s���v�͂܂����_�I�u���E�s���v�����ݏo�����O����A���̎��𐳂������ɓ����čs�����Ƃ��Ă���A�����ɂ͊m���ɉ����̕��ɐi�����Ƃ���g�̓I�Ȕ��f������B�܂��ɐg�̓I�Ȏv�l�ƌ����ׂ��Ȃ̂ł���B
�����͂��̖{���Ƃ��āA�����ƕs�����ƌ�����̎��������B�g�̂͗l�X�ȊO�E�Ƃ̌��������Ȃ��琬�����čs���B���̉ߒ��ɂ����Đg�̓I�u���E�s���v�͋x�ގ��Ȃ������^���𑱂���̂��B�����Ɏv�l�����܂�Ă���̂ł���B
���̎v�l�͗��O�v�l�̂悤�ɁA���_�I�Ȏv�l�Ƃ͌����Ȃ��B�������A�����̐g�̂ɐ��ݏo���ꂽ�����ʂ��I�����Ȃ��琬�����čs���ߒ�������Ȃ�A�����ɂ͖��炩�Ɏv�l�̌`�Ԃ����݂��Ă���̂ł���B�������̎v�l�����o���Ă��Ȃ������̂��ƂȂ̂��B������v�l�Ƃ��ĂƂ炦��͓̂��R�̎��ł��낤�B
�g�̓I�u���E�s���v����b�ɂ��Ă��邱�Ƃ���A���̎v�l����ɐg�̎v�l�ƌĂ̂ł���B
�Ƃ���ł��̐g�̓I�u���E�s���v�������ɍl����Ȃ�A���̍\���̒��ɂ��łɋ��\���������Ă���B�Ȃ��Ȃ炻��́A���ɏq�ׂ��悤�Ɂu���E�s���v���̂��̂����������ɂ�����g�̂̊W�������Ă��邩��ł���B
�W�͂��̂��Ƃ̏�Ԃ��������̂ŁA���ꎩ�̂͐^�����̂��̂ł͂Ȃ��B�^���͂��̊W�ݏo���Ă���g�̂̕��ɂ���̂ł����āA�g�̂̎������W�Ƃ��Ĕc������n�߂鏊���狕�\�������ݏo����ė���̂ł���B
���_�A�F���������܂�Ă��Ȃ������ł́u���E�s���v�͎��B���l���Ă���悤�Ȍ`�ő��݂����ł͂Ȃ����낤�B���̎����ɂ́u���E�s���v�ƌ������t���̂��̂��܂����ݏo����Ă��Ȃ��̂ł����āA�܂��ɂ��̈Ӗ��ŊW���̂��̂������Ƃ��Ċ����Ă���ɉ߂��Ȃ����낤�B���������Ă�������\�Ƃ����̂͌����߂���������Ȃ��B
����ǂ��A���������ɉ��炩�̔��f�A���邢�͑I��������Ƃ���Ȃ�A�܂���������߁A�s�����������Ƃ����悤�ȃV�X�e�������݂���Ȃ�A�����ɂ͊m���ɋ��\���̉肪���܂�Ă���ƌ���ׂ��ł��낤�B
�����Ă����A�t�ɂ��̂悤�Ȕ��f����ؑ��݂����A���ׂĂ������I�ɓ����Ă��邾���̊����������̂��ׂĂ��Ƃ���Ȃ�A���̂悤�ȍ\���̒����琸�_�I�Ȏv�l�̐��ݏo����鎅���������������Ƃ͂قƂ�Ǐo���Ȃ��̂ł���B
�S�Ă������I�Ȑ����^������͒m���͐��܂�Ȃ��B�l�Ԃɒm�������ݏo�����̂́A���̐g�̓I�u���E�s���v�̒��Ɋ��Ɍ̂Ƃ��Ă̑I�f����V�X�e�����萶���Ă��邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�g�̎v�l�ɂ����鋕�\���́A�܂��ɂ��̐g�̓I�u���E�s���v�̍\���ɂ��̂ł���B�g�̓I�u���E�s���v�͂₪�Ēm�����A���_�I�u���E�s���v�ݏo���A�g�̎v�l�_�v�l�ւƔ��W������̂ł���B
�u���E�s���v�̐��܂��O�ɂ͂����ӎ��������������B�i��Q���j
�ӎ��͐����̍ł��[�����ł������̂ł��邪�A�g�̓I�v�l�͂₪�Ă��̈ӎ��Ɏ����Ď��݂ɗn������ōs���B���邢�͂������l�Ԃ̓�����Ƃł������邾�낤���B�܂��ɂ����͉F���Ɛl�ԂƂ̐ړ_�Ȃ̂ł���B
�v�l�͎��̂Ƃ��낱�̐ړ_���琶�܂�Ă���ė����B�v�l�Ƃ̓G�l���M�[�̌����ƕϑJ���̂��̂ł���A�s�ׂ̈�킾�ƍl���鎄�̕K�R�I�Ȍ��_�������ɂ���̂ł���B
�{���v�l�͋��\�Ƃ��ĂƂ炦����B�������B�͗l�X�Ȏv�l�̌`�Ԃ̒��ɋ��\�������Ă����̂ł������B�������Ȃ���A�����Ɏ����Ďv�l�����\�Ƃ��Ă����ł͂Ƃ炦��Ȃ���肪�o�Ă���B
�ӎ��Ƃ������݂��̂��̂̒�����m�������ݏo�����B����͓����ɔF���̔����ł�����̂����A����͌����Ă݂�Ύ��݂��n�Ɍ����Ă��Ƃ��A�����ɋ��\�ݏo���v�l���o�t�̂悤�ɉ���o���ƌ����悤�ȃC���[�W�Ƃ��ė��������B���̎����B�͎v�l�Ƃ����o�t���������o���čl���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂��B���ɂ�������Αo�t�͌͂�Ă��܂������Ȃ��B��n�������đo�t�͉��̈Ӗ��������Ȃ��B���̂Ƃ��뗼�҂͈�̂̂��̂Ȃ̂ł���B
�v�l�͋��\�������B���\�����̉e���Ɨ�������Ȃ�A���̉e����肾�����̂������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ꂱ�������݂Ȃ̂ł���B
�܂��Ɏv�l�Ƃ͎��݂̉e�Ȃ̂ł���B
���݂̒��ɌƂ��Ă̑��݂������ƁA�����ɗl�X�ȊW�����ݏo�����B���̊W�������݂̉e�ł���A�v�l�̏o���_�Ȃ̂ł���B
���̈Ӗ����猾���ΐg�̎v�l�͋��\�Ǝ��݂��ł��ڋ߂��Ĉ�ɂȂ�n�_�Ƃ��ė������邱�Ƃ��o���邾�낤�B
�v�l�͂܂��ɂ�������n�܂�̂ł���B
���B�͐g�̎v�l�����čs�������ɁA�v�l�̍ł����n�I�ȕ����ɗ����������B���̗̈�͉F����Ԃ���l�Ԃ����܂�邻�̏u�Ԃ��܂�ł���̂ł���B
���̎v�l�̌��_�́A���Ɍ��錴���o�v�l�Ɩ��I�v�l�ɂ������͂��ł���B��i�����B
�i�����o�v�l�j
�����o�v�l�͂��łɌ��������I�v�l�ƈ�̂܂Ƃ܂�����B
�܂�����ŁA���̎v�l�̊�{�I�ȗv�f�͐g�̂Ɍ����l�X�Ȋ��o�Ɋ�Â��Ă���A������܂��g�̓I�v�l�ł���B
���o�Ƃ͑̂̊e���ɂ��銴�o�킪�O�E�̎h���Ɋ������āA���E���������̌����鑕�u�ł���B���B�����܂��Ɋ����Ă��鑶�݊��A�������A�g�̊��ƌ������̓��o���͂قƂ�ǂ��̊��o�ɂ���Ă���ƌ����Ă����ł��낤�B
���̂������o���ꂽ���o�v�l�������I�v�l�ƌĂB����͂��łɌ��ė����悤�ɏ�O�v�l�̈�ł����āA�v�l�̍ł����������Ɏ���A���B���o���ɓ����čs���\���������Ă����̂ł���B
������o����Ȃ����o�v�l�����̊����I�v�l�Ƌ�ʂ����B�����Ŏ��グ�錴���o�v�l�͂܂��ɂ��́A�����o�̊��o�v�l���w���Ă���̂ł���B����Ό����o�v�l�́A�̓��ɐ��܂�Ă��Ȃ��疢�����o����Ȃ��v�l�Ȃ̂ł���B
�Ƃ���Ŋ��o�͎��o�̂悤�ɖ��m�ɐ��E���w�������悤�Ȑ��_���̋������̂���A�Ɋo�̂悤�ɋɂ߂Đg�̓I�Ȃ��̂܂ŁA�l�X�ȍL����������Ă���B����͑S�g�ɑ��݂���̊��ƌ����悤�B
����́u�W�v�ƌ������\�̉�����̓��Ɏ����Ă������A���o�͂��ꎩ�̈�̎����Ƃ��ĂƂ炦����B�܂芴�o�͐g�̓I�u���E�s���v�Ƃقړ������ɑ��݂���g�̂̎������x�[�X�ɂ��Ă��Ȃ���u���E�s���v�̂悤�ȑΗ�����T�O�������Ȃ��B�܂��Ɏ������̂��̂ƌ������Ƃ��ł��悤�B���̈Ӗ��Ŋ��o�͊���ɔ�ׂĂ����݂ɋ߂��ƌ������Ƃ��o����̂ł���B
�Ƃ���Ŏ��o�⒮�o�́A���o��̎h���ɂ������������ɐ��E��F��������B����͊��o���u���ɁA���O�v�l�ƂȂ����Ă��鎖�������Ă���̂����A���B�͂���������āA���o�����o�Ƃ��Ă����A
���E�̔F�����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂��X�������邾�낤�B
�����������o�v�l�ɂ����ẮA���������킯�ɂ͂����Ȃ��B���o�͂�����������Ȃ����Ƃ��ĂƂ炦���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�Ƃ����Ă��ƂƂ͔F�������A�Ԃ����Ă��ԂƂ͊����Ȃ��ڂ���Ƃ������o�B�ڂɂ���Ă�����i�͂����Ӗ��̂Ȃ����̏W�܂�Ƃ��ĂƂ炦�������ł���B�����ɏ����Ȋ��o�Ƃ��Ă̎��o�̎���������̂ł���B���邢�͊��ɗᎦ�����悤�ɁA�F���̎��ӂŎ��o����Ȃ��܂����čs�������o������B
���̂悤�Ɍ����o�v�l�́A�ڂɂ���Ă�������F������Ȃ��܂ܑS���̖������łƂ炦����ׂɁA��������̌��i�Ƃ��ĂƂ炦���邱�Ƃ͂Ȃ��B
�܂�ڂɂ�����͉̂��ł���A������R���ƌ����悤�Ɏ��o�ɍL����w�i��l�X�ɋ敪���Č��Ă���̂ł͂Ȃ��A���i�̂��ׂĂ��������̂܂܁A������̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�����ł���B
�Ӗ��t�����Ȃ����ɂ�銴���������g�̂ɂ����āA����������͎��o����Ȃ��܂ܑ̓��Ɏc����Ă���B���ꂪ�����o�v�l�ł���B
���������̑̓��ɐ��܂ꂽ�����o�̎��o�́A���o�����ƁA�Ƃ���ɈӖ���^����ꕪ�����N����B���E���F�������̂��B�������Ď��o�͂��̂܂���Ԃ��L���čs���̂ł���B
�Ӗ����^������ƌ����̂́A�����ɔF����̂������Ă��鎖��\���Ă���B���������u�Ӗ��v�ƌ����̂́A��́����ɂƂ��Ă̊W�A�Ӗ��t���̎��ł����āA��̂��Ȃ���ΈӖ������������ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���E�͂����N�����Ă��邾���ł���A�����ɈӖ��ȂǑ��݂��Ȃ��B�����u���v�Ƃ�����݂̂̂��Ӗ���K�v�Ƃ��邾���Ȃ̂ł���B���̂��Ƃ����B�͏[���ɗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
���̂��Ƃ��猾���A�����o�̊��o�Ƃ����̂́A�F����̂����������ɐ��܂��������ƍl������B�܂茴���o�v�l�͔F����̂ł���u���v���܂����ݏo����Ȃ����̑O���瓭���Ă���v�l�ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B
�Ƃ���Ŏ��B�͕��ʁA�ڂɂ������̂����ł��邩�F�����悤�Ƃ���B���ꂪ���̂̒m��Ȃ����̂Ȃ�A���ӂ͈�w���̕��Ɉ����t�����邾�낤�B����͉��Ȃ̂��ƌ����₢���������o��ʂ��Ĉ����N������₪�ĐV�������ꂽ���̂ɖ������邾�낤�B
�V���Ȑ������Ȃ�A���ꂪ���ނɑ�����̂��A�ǂ�Ȑ��Ԍn�����̂��A�ώ@�ƌ����������A���̓��̂̒m��Ȃ����̂����ɐl�Ԃ̒m���̈�[�ɉ�������B
���̉ߒ��̒��ŁA���o�̓����͌Q���Ă���B���o�������Ċώ@�͂��蓾�Ȃ����A���̐������̑��݂���m�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ����Ƃł���B�������Ď��o�́A���t���g�����O�v�l�ɍł����ڂɂȂ����čs���̂��B
�l�͌������̂�^���ƍl���鋭���X��������B�������̂͌��t�����͂邩�Ɍ����I���ƍl����B�܂��Ɉꌩ�͕S���ɔ@�����ƌ����邾�낤�B
���_����ɂ͗��R������B���Ƃ��ƌ��t�͐l�Ԃ����o�������̂ł��邪�A���o�͍ŏ����玩�R�ɔ�����Ă���l�Ԃ̓���������ł���B���������Ċ��o�͂��ꎩ�̂ł��łɑS�Ă�\���Ă���ƍl�����邪�A���t�͂���������ɂ͍s���Ȃ��B
���o�⒮�o�ȂǗl�X�Ȋ��o�������āA�l�͎����Ƃ�������͂ސ��E���������čs���B����������A���t�͂��̎������ꂽ���E��������A�\�����悤�Ƃ��Đ��ݏo���ꂽ��i�̈�ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�O�҂͎����̑̌��ł���̑��āA��҂͒P�Ȃ�\����i�ł���Ƃ������̈Ⴂ�͑傫���B���悻��u�̑̌��ł����Ă��A�����S�����ĕ\�����Ƃ������̂��ł͂Ȃ����낤�B
���t�͂��Ƃ��Ɛ^���Ƃ͖��W�ȋL���ł����Ȃ������B���������Č��t�͌������̂̈ꕔ���͓`���邪�A�����������Ă��ׂĂł͂Ȃ��B�l�͂��̂��Ƃ��[���m���Ă���̂��B
�܂肱���������Ƃ��o����B�l�Ԃ����̉F���ɐg�̂��Ƃ��A
�����Ɋ��o���������āA���E�Ǝ�����̌����n�߂�B�F���G�l���M�[�̂������ɐg�̂����ݏo����A���̑̂ɂ���߂�ꂽ���o�킪����Ă���l�X�ȃG�l���M�[�Ɋ��������̑��݂���������B�l�Ԃ͂��̂悤�Ɏ�������芪�����E�̂���悤���A���o��ʂ��đ̌�����̂ł���B����́A�܂������̌��ł����m�蓾�Ȃ��A�m�o�ȑO�̎v�l�Ȃ̂ł���B
�₪�Đl�Ԃ͎����̑̓��ɐ��܂�銴�o�����o���n�߂�B�ڂɉf����i�⎨�ɕ�������l�X�ȉ��A���Ɋ����鈳�͂�ɂ݁A�L�C�□�o�A�����̎h���͎���̐����ɒ��ړI�ȊW�������A���o�����l�ԂɂƂ��Ă̍ł��g�߂Ȓm�o�̑ΏۂƂȂ��čs�����낤�B
�m�o�������n�߂�ƁA���E�ׂ͍����敪����čs���B���t�͂܂��ɂ��̋敪�������\�����߂ɐV�������o�����B�Ⴆ�ΉԂƌ������t���ו������ƁA�Ԃт��ԕ��ƌ������悤�Ȍ��t�����ݏo�����B����ɋ敪���i�߂���ƁA�זE�A�^���p�N���A�j�_�A���q�A
���q�ƌ����悤�ɁA�V���Ȍ��t�������ɐ��ݏo���ꑱ����̂ł���B
���t�͂��̂悤�ɒm���ɂ���Č���Ȃ����o�����l�H�̎Y�����Ƃ������邾�낤�B
�����Ō����o�v�l�ƌ����̂́A���̌��t�����ݏo�����O���瑶�݂��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�l�Ԃ͌̂Ƃ��Đ��ݏo���ꂽ���̏u�Ԃ���A���E�Ǝ����Ƃ������E�̐���ŌJ��L�������̐��E�̃G�l���M�[�̌𗬂�������������B�����A�����A�Z���A�Η��A�}���A�����A�l�X�ȊW�����E�Ɛl�ԑo���̊ԂŌJ��L������B���o�͂܂��ɂ��̉F���G�l���M�[�̔g�����A�������ᔻ�̂܂܂Ɏ�����������̂ł���B�����o�v�l�͂����ɂ���̂ł���B
�l�Ԃ��F���Ƃ������삩�猩��ƁA��C�ɐ��܂ꂽ��̖A�̂悤�ȑ��݂ł������B
��C�ɊC�����������ӂ�Ă���悤�ɁA�F���ɂ̓G�l���M�[���[�����Ă���B���͂��̃G�l���M�[���F���ӎ��ƌĂB�����đ����̓����ɂ���āA���̉F���ӎ��̒��ɂP�Ȃ鑶�݁A���Ȃ킿���B�̐g�̂����グ��̂ł���B
�g�̂͂��̓����ɉF���ӎ�����荞�݁A�����ɊC�ɕ����ԖA�̂悤�Ȏ��Ȉӎ��̗̈�����̂ł������B�i��O���j
�����Ċ��o�͂��̖A�̕\�ʂɂ����镔���ɑ������āA�����ƊO�̐��E���Ȃ킿�F���ӎ��Ƃ̊Ԃɐ��܂�鑊����߂炦��B�܂芴�o�͎��Ȉӎ��ƉF���ӎ��̍U�ߍۂɐ��܂��G�l���M�[�̑��ݍ�p���̂��̂ł���A�l�͂�����u�����v�Ƃ��Ď~�߂�̂ł���B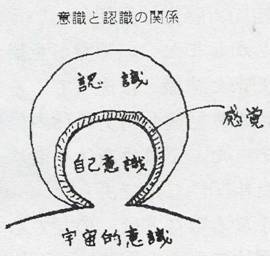
���o�Ƃ͂��̂悤�ȃG�l���M�[�̔g���ɊO�Ȃ�Ȃ��B
�����Ƃ����o�͐g�̂̕\�ʂɂ��邱�̂悤�Ȏ��������Ɍ�����̂ł͂Ȃ��B�܂�g�̂̓����ɋN����G�l���M�[�̌����Ɨh�炬�ɑ��Ă������Ƃ��ĂƂ炦��̂��B���̎����́A�g�̂������ɍ݂�Ƃ������݊��ł���A������g�̊��o�ł���B
���̑��݊��͎��Ȉӎ������o���B����͐��������ɔ������Ȉӎ��̗h�炬�A���Ȃ킿�G�l���M�[�̔g���ł���A�����Ă��̔g�����̂��̂������Ƃ��đ̌������B�����Ɏ�������ƌ������o�́A���̔g���ɑ���������̂��̂Ȃ̂ł���B�������������ɑΉ����āA�g�̎v�l��������Ǝ��͍l����B
�Ƃ���ł��̂悤�ɁA�����o�v�l�̓G�l���M�[�̔g�����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦����B����Ƃ����ł́A���\�͑��݂��Ȃ��ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B�Ȃ��Ȃ炻��̓G�l���M�[�Ƃ������݈ȊO�̉����ł��Ȃ�����ł���B���݂��̂��̂�̌�����B���̑̌��̒��ɋ��\�͂���ė��Ȃ��̂��B
�v����Ɍ����o�v�l�͎��݂��̂��̂ł���B�����Ă����Ől�������Ƃ��đ̌����Ă���̂́A�ϓ�������݂̗h�炬���̂��̂��ƌ�����̂ł���B
�O�߂ł͐g�̎v�l�͉F���Ɛl�Ԃ̐ړ_���琶�ݏo�����Ə��������A�����Ō��������o�v�l�́A�܂��ɂ��̐ړ_���̂��̂��ƌ�����̂ł���B
�����ŕt�������Ă����Ȃ�A��O���ł͎��͐g�̂̕\�ʂɌ���銴�o�A�����銴�o��ɂ���đ̌���������݂̂����o�Ƃ��ĂƂ炦���̂������B
���������đ̓��̎����������g�̓I�u���E�s���v�Ƃ��ė��������̂ł��������A���͂����ł���Ɋ��o�̗̈���L���Ă���B�܂芴�o���A���o��ɂ��̌��Ɏ~�܂炸�A�g�̎��g�������Ă���̓��̎����ɂ܂ʼn����L�����̂ł���B�����g�̊��ƌĂB
���o�Ƃ̓G�l���M�[�̔g�����̂��̂������Ă��邤���߂����A�u�����v�Ƃ��ĂƂ炦�����̂ƍl����Ȃ�A���o�͓��R�Ō�ɂ͑̓��̃G�l���M�[�̗h�炬���̂��̂ɍs�������Ă��܂��B����͊��o�����Ȉӎ��ƉF���ӎ��̑����ɂ��h�炬�����ɂ͎~�܂炸�A���Ȉӎ����̂��̂̔g���ɂ܂ŋy�Ԃƌ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���B
���̂悤�Ɋ��o�̗̈���g�������̂́A���o���o�̊��o�������o�ɂ܂ōL���čl��������ł���B
���Ȃ݂ɐg�̓I�u���E�s���v�͂��̐g�̊���P�������ŐF�����������̂ƍl������̂ł���B�g�̊��͑̓��ɑ��݂��鎩�Ȉӎ��̗h�炬��̌��Ƃ��ĂƂ炦�����̂ŁA����Ύ��Ȉӎ����ꎩ�̂̑��݂������Ƃ��Ď�������̌��Ȃ̂ł���B
�����o�v�l�́A���̂悤�ɃG�l���M�[���ꎩ�̂������Ƃ��Ď��A�����ɉ��炩�̑��݊���̌�����B����Ƃ��̂��Ƃ́A���Ȉӎ��̑̌��Ƃ��Ă̐g�̊��Ɏ~�܂炸�A���ɂ͐g�̂��z�����F���ӎ��ɂ܂Ŏv�l���y��ōs���\�����͂��ł���̂ł���B
�����Œ��ӂ��ׂ����Ƃ́A�����̎v�l�͖����o�̐��E�ōs���Ă��鑶�݂̎������ƌ������Ƃł���B
�킽���͂��̈Ӗ��Ŏ��݂Ƃ������t���g���B�v�_���v�l�ŏq�ׂ��o���Ƃ́A���̐g�̎v�l�Ƃ��Č������݂����܂Ȃ����o���邱�Ƃɂ���Ď�������ƌ����Ă������̂ł���B
�i���I�v�l�j
�v�l�̌`�Ԃ̍Ō�ɁA���͖��I�v�l�ɂ��čl���Č������B
���̌��t�͂��������t���I�Ȋ��������邪�A�����������ɂ͎v�l�S�̂��x����d�v�ȓ��e���B����Ă���̂ł���B
���I�v�l�Ƃ́A�v�l�Ǝv�l�̌��Ԃƍl����Η������₷�����낤���B�v�l����̍s�ׂƌ��Ȃ��Ȃ�A���I�v�l�͕s��ׂ̎v�l�ƌ������Ƃ��o����̂ł���B
��ɓ������{�[���͊Ԃ��Ȃ����ɗ�������B���̎��A�㏸�Ɨ����Ƃ�����̉^���̐ړ_�ɁA�S�������Ȃ���_�����݂���B���̂ł�������̂ł��Ȃ��B��������ɐÎ~�����u�Ԃ������ɂ���B
���I�v�l�͂��̐Î~�����{�[���Ɏ��Ă��邾�낤�B
���̃{�[���̐Î~�͒ʏ펄�B�ɔF������Ȃ��悤�ɁA���I�v�l�͂��Ƃ����o���ꂽ�v�l�̒��ɍ݂��Ă��A����݂̂����o���ĔF�������悤�Ȏ��͂܂��Ȃ��̂ł���B
���\���̂����Ƃ��������O�v�l�ɖڂ������Č���Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�v�l�͎��X�Ɠ��̒��ŕϓ]����B��̌����ɖv���������]�łȂ�����A������̂��Ƃ��l�������邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�v����B����قǎv�l�͖ڂ܂��邵����щ���Ă���B����͎����̓����U��Ԃ��Č���A��������[�����鎖���ł��낤�B
���B�͂`�ɂ��čl���Ă��鎞�ł��A�ӂƉ������ڂɎ~�܂��āA�ˑR�a�ɂ��čl���n�߂鎖������B����Ƃ�������b�Ƃ����l���������N������A�܂����≽���̎h�����Ăc�ɂ��Ă̍l�����N�����ė���B���̂����ɉ�ɕԂ��āA�܂��`�ɂ��Ă̎v�l�ɖ߂�ƌ������悤�ɁA�v�l�͖ڂ܂��邵���ϓ]���čs���̂ł���B
�Ƃ���Ŏ��̌��������̂́A���̎��A���ꂼ��̎v�l������čs�����̍��Ԃɂ́A��ɖ��I�v�l�����݂��Ă���ƌ������ƂȂ̂ł���B
�e���r�̃`�����l�����ւ��鎞�ɁA��u��ʂ������Ă��܂��悤�ɁA�v�l�ɂ���čL�����Ă�������Ԃ͈�u�Ԗ��ƂȂ�B���̎v�l�������ɂ���ė��邽�߂ɁA���B�͂قƂ�NjC�Â����ɐ����Ă��邪�A���͂܂��ɂ��̏u�ԁA����Ԃ͏��������Ă���̂ł���B
�����ɖ��I�v�l�����݂���̂ł���B
�������B�����̖ڂ܂��邵���v�l���~�����邱�Ƃ��o�����Ȃ�A���̂Ƃ������ɂ͎���Ԃ̑��݂��Ȃ����E���o�����邾�낤�B�����͂܂��Ɏ��݂��̂��̂Ƃ��ẮA����Ԃ��o�����Ă��鎖�ɂȂ�̂��B
����͌���Ύv�l�̗��Ԃ��Ƃ��ė������邱�Ƃ��o���邾�낤�B���Ȃ킿�v�l������Ԃ����Ƃ���Ȃ�A���I�v�l�͌���Ԃ��̂��̂̎v�l�Ȃ̂ł���B�����ɂ͔F����̂��鎄���̂��̂������̂��B
���������Ė��I�v�l�͎��o����邱�Ƃ��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ疳�I�v�l���̂����łɎ��o�̎�̂���u���v��Ȃ�����ł���B���o�Ƃ́A���̎��������Ŏ����̎v�l��m�鎖�ł��邪�A�����m��ׂ������̂��̂����݂��Ȃ����莩�o�͂���悤���Ȃ����낤�B
�`�Ƃ����v�l�ɂ��Ă��A�a�ɂ��Ă̍l���ł����Ă��A���B��������v�l�͂ǂ�ł��A�����Ɏv�l�����̂Ƃ��Ă̎������݂���B
�������`�Ƃa�̎v�l�̊Ԃƌ����̂́A�`�̎v�l�̏I���ƁA�a�ɂ��Ă̎v�l�̎n�܂�̐ڂ��镔���ł����āA����͂ǂ��l���Ă݂Ă����ł������蓾�Ȃ��B�������炩�̎v�l�����݂���Ƃ���A����͂����`�Ƃa�̊Ԃɂo�Ƃ����v�l������Ƃ��������ŁA�����Ȃ�`�Ƃo�̎v�l�̊ԂƂ���������肪�o�Ă����ł��邩��A���ǂ`�Ƃa�̊ԂɐV���Ȏv�l�����݂���Ƃ͍l�����Ȃ��̂ł���B�����ɂ�����̂́A���ł����Ȃ��B
�v�l�̓G�l���M�[�̔g�����Ǝ��͍l����B����Ƃ��̖��͔g���̂O�̒n�_���Ӗ����Ă��鎖�ɂȂ�B�v�l���F���ɐ��܂ꂽ��̃G�l���M�[�g���Ƃ���Ȃ�A���̔g�̃G�l���M�[�I�ɂO�̒n�_�͕K�����݂���B����͎v�l�Ǝv�l�̊Ԃɂ���A���o�̐��ݏo����邻�̈����O�ɂ���A���ƕs���̒��Ԃɑ��݂���̂ł���B
���̂��Ƃ���̓I�Ɍ��Ă݂�ƁA���Ƃ��Ί��o�I�v�l�ɂ��Ă̓G�l
���M�[�̊W�͉E�̐}�̂悤�ɂȂ邾�낤�B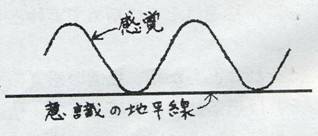
���o�͎h���������đ傫���Ȃ����菬�����Ȃ����肵�Đ}�̂悤�ɔg�����J��Ԃ��B�i��O���j
���̂Ƃ��̖��Ƃ͐}�̈ӎ��̒n�������w���B����͐g�̂̓����ɑ��݂��鎩�Ȉӎ����̂��̂ƌ����邾�낤�B
���邢�́u���E�s���v�ɂ��Ă݂�A����͉����ƕs�����̒��Ԃɑ��݂���B���ƕs���̓���ւ�邻�̒��ԁA����͐U��q�̉^���Ɏ��Ă��邾�낤�B���ƕs���̗��[���s�������U��q�͉�����s���Ɉڍs����Ƃ��A���邢�͕s��������ɕς�낤�Ƃ��邻�̏u�ԂɐU��q����~����B���̒n�_�������Ȃ̂ł���B���B�͑�O���ŁA
�����ƕs�����̊Ԃɖ����ƌ������̂�ݒ肵�����A�܂��ɂ��̖������w���̂ł���B
�������Č���Ȃ�A���I�v�l�́A���B������܂Ō��ė����l�X�Ȏv�l�̑S�Ă̌��Ԃߐs�����悤�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ��������Ă��邾�낤�B���������F���͕��̌��Ԃ���Ԃ����ߐs�����Ă���悤�ɁA���I�v�l�͐��܂ꂭ��S�Ă̎v�l�̌��Ԃɏ[�����Ă���̂��B
�����Ă���͉����Ɩ₤�Ȃ�A�����ɂ�����͈̂ӎ������Ȃ��̂ł���B����͌����܂ł��Ȃ��F�������Ă���ӎ����̂��̂��w���B���͂�����F���ӎ��ƌĂB
���̂Ƃ���l�Ԃ͂��̉F���ӎ���̓��Ɏ�荞��Ŏ��Ȉӎ������B���̂Ƃ��F���ӎ��̔g���Ǝ��Ȉӎ��̔g���ɂ͂��邸�ꂪ�����Ă���̂ł���B
���̔g���̈Ⴂ���A���o��u���E�s���v�̐��̂ł������̂����A�����͂��̗��҂̔g�����������邱�Ƃɂ���āA���Ȉӎ����F���ӎ��̒��ɗn������ōs�����Ƃɂ���ē���������Ȃ̂ł���B
���Ȃ킿�����Ƃ͉F���ӎ����̂��̂̎������ƌ����Ă����̂ł���B���ǂ̂Ƃ���A���I�v�l�͎��Ȉӎ����z���ĉF���ӎ��ɗn������ł����v�l�ƌ����Ă��悭�A�܂��Ɍ���ԂɋN�����Ă���v�l�Ȃ̂ł���B
�����Ƃ����̂悤�Ȏv�l�͂������݂���Ƃ��Ă��A����ɂ��m���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������O������B
���ہA���I�v�l���F���ӎ����̂��̂̂��Ƃ���Ȃ�A���̎v�l�ɂ͂����S��I�Ȃ��̂̂ق��ɂ͎v�l�����̂͑��݂��Ȃ����ƂɂȂ�B�܂��Ɏ��͖��I�v�l�����̂悤�ɋK�肵���̂ł���B�ʂ����Ă��̂悤�Ȏv�l�����B�͗������邱�Ƃ��o����̂��낤���B
�T�ł��ґz���d���A�������疳�ɓ��邱�Ƃ�������B���͂��̖������I�v�l�ɋ߂��ƍl����B
���̖��I�v�l�𗝉�����̂́A���O�v�l�Ɋ���e�����B�ɂ͓�����Ƃ�������Ȃ��B���������̖��I�v�l�Ɋo�������҂͎߉ނ�V�q��L���X�g�̂悤�ɂ�����ł�����Ǝ��͍l����̂ł���B
�l�Ԃ͂����A������܂܂Ŏ~�܂��Ă���̂ł͂Ȃ��B�l�Ԃ����O�v�l�������������Ȃ��ƍl���鍪�����Ȃ��̂ł���B����������́A�l�Ԃ͂܂��Ɏ��Ȉӎ�����F���ӎ��ւƐ��܂�ς���čs���ߒ��ɂ���̂��ƐM����B
���̉ߒ��́A�܂����̖��I�v�l����n�܂�B����͉F�����̂��̂̂Ƃ��ĂƂ炦����B����C�Â��Ȃ��܂܂ɐi�߂��Ă���F���̎v�l�Ȃ̂ł���B�������玩�Ȉӎ������ݏo����l�ԂƂ��Ă̎v�l���W�J�����悤�ɂȂ�B���̎v�l���ŏ��͖����o�̈ł̒��ɐg�̓I�v�l�Ƃ��Č���A�₪�Ďv�l�ɑ��鎩�o�����܂��B�����Ɉ�ʓI�ɂƂ炦����v�l�����݂���̂ł���B���̎��o������ɖ����o�̗̈�ɐZ�����A�₪�Ė��I�v�l�܂ł����o����Ɏ������Ƃ��A�l�͎������܂މF���S�̂Ɋo������̂ł���B�����ɂ͊��Ɏ��Ƃ�����̂͏�������A�l�͂����S��̉F���Ƃ��Ċo������̂ł���B
���̉ߒ�������ɓ������Ď��B�͗l�X�Ȏv�l�̌`�Ԃ����ė����̂��������A����͂��������������ɎG���ɂ߂��悤�ł�����B���X�ƐV�������t�������ꂽ���߂ɁA���ꂼ��̌��t�̊֘A������킵���Ȃ��Ă��܂�����������Ȃ��B
���������ׂɎ��͎��ɂ��ꂼ��̎v�l�̊W��\�����v�l�n�}��\���Ă݂��B
����͏c���ɖ�����o���Ɏ��鐸�_�I�ȕϑJ���Ƃ�A����ɑΉ�������`�ł��ꂼ��̎v�l�̐�߂�ʒu��\���Ă݂����̂ł���B
����ɐ}�̉����ɂ́A���\���̋������̂���A�ア���́B���Ȃ킿���\������݂Ɍ����������ɑ��āA�O�̃u���b�N�Ɏv�l���敪���Ĕz���B
���̒n�}�̑S�ʂ����Ă���͖̂��I�v�l�ł���B����͌���ԂƊ��S�ɏd�Ȃ��Ă���B�ł�����̉F���ӎ�����o���Ɏ��鐢�E�A���̒��Ԃɑ��݂��鎄��Ԃ̐��E�ɂ����A���I�v�l�͓����Ă���̂ł���B���B�ɂ��ꂪ�����Ȃ��̂́A���Ԃɐ��������Ȃ��悤�ɁA����Ԃ̑N�₩���ɉB����Ă��邽�߂ł���B
�g�̓I�v�l�E��O�v�l�E���O�v�l�Ƃ����O�̎v�l�Q�́A���I�v�l�̒��ɕ����Ԃ悤�ɑ��݂��A�݂��ɊW�������Ď���Ԃ����o���Ă���̂ł���B
�����܂ł��Ȃ��A���B���ʏ�A�v�l�Ƃ������t�Ŏw���̈�́A�}�̒��̗��O�v�l�����O�v�l�̈ꕔ���Ɏ��鏬���ȋ��ł���B���͎v�l���G�l���M�[�̔g���Ƃ��ĂƂ炦�邱�ƂŁA���̗̈���F���̗̈�ɂ܂ōL�����̂ł���B(���\)
���B�͍l����Ƃ����A�l�ԂɂƂ��čł��_��I�Ȍ��ۂ��A����ɋ敪���Č��ė����B�v�l�Ƃ͉����Ƃ����₢�Ɍ������āA��������̃L�[���[�h�ɏƂ炵�Ȃ��瓥�ݍ���ōs�����Ƃɂ���āA���B�͑O�߂Ŏ������v�l�n�}����ɓ��ꂽ�̂ł���B
�@�����������ł��炽�߂Ċm�F���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̎v�l�n�}�������Đ�Ύ����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃł���B
�@�����łȂ���Ύ��B�͓��X��������邱�ƂɂȂ邾�낤�B����܂ł��ǂ��ė��������A������ΓI�ɐ��������̂Ƃ��Č��t�ʂ�ɂƂ炦��Ȃ�A���B�͊m���Ɏv�l�̖��H�ɖ������ނ��ƂɂȂ�B�@�Ȃ��Ȃ玄�B�̂��̍�Ǝ��̂��v�l�ɊO�Ȃ炸�A���̘_�����̂��̂����t�őg�ݏグ��ꂽ�A�����闝�O�v�l�̎Y��������ł���B
�����͐^�����w�������͂��邪�A�^�����̂��̂ł͂Ȃ��B��������t�ʂ�ɂƂ炦�Ă��܂��A���B�͎���̂����ۂ�H��������ւ̂悤�ɂȂ��Ă��܂����낤�B
�@������ɂ��Ă����B�̂��̍l�@�́A���t�Ō���Ă���B�����ɂ���̂͌��t�����Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ��낪���t�͋L���ł���A��̂��Ƃ��ɉ߂��Ȃ��B���̈Ӗ��ł��̎v�l�n�}���܂��S���������R�Ő^�����̂��̂ł͂Ȃ��B
�@�܂�A�����q�ׂė��������́A���݂Ƃ����^�����Î����邽�߂̗Ⴆ�b�ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�@���B�����ڂ��ׂ������͐^���ł����āA�Ⴆ�b���̂��̂ł͂Ȃ��B�@�^���͌��t�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�̌����̂��̂Ƃ��Ă���B�l�͂��̑̌���\�����悤�Ƃ��Č��t���g�����A�����̏ꍇ��������t�ʂ�Ɏ���ėv�_���Ă��܂��̂��B���Ȃ킿���B�͌��t�̗��ɑ����ꂽ�^���ɖڂ�������ׂ��ł����āA�����Ɏg��ꂽ���t���̂ɐS��D���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���ۂɎv�l�́A���B�����ė����悤�ɐ荏�܂�đ��݂���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����͈�̂��̂Ƃ��ď��߂Đ����Ă�����̂Ȃ̂ł���B
�@�v�l�̍\���́A���Ɍ��ė����悤�ɁA�l�X�ȕ������猩�邱�Ƃ��ł��邯��ǂ��A���̎��Ԃ͒P���Ȃ��̂��Ǝ��͍l����B�܂肻��̓G�l���M�[�̗h�炬�Ƃ�����_�ɏW��čs���̂ł���B�����Ă����Ɍ����Ă��鐢�E�͖����Ƃ��������悤�̂Ȃ��F���Ƃ���������̑��݂����Ȃ��B�l�ԓI�Ƃ�����������͉F���I�ł���A���_�I�ƌ�����蕨���I�ȍ݂���������Ă���̂ł���B
�@�v�l�����_�I�ł͂Ȃ��ƌ����ƁA�٘_�̔�ь����̂�������悤�����A�����������ł͂Ƃ肠�������̂悤�Ɍ��_�t���邵���Ȃ����낤�B
�@���_�I�ƌĂѓ����Ԃ́A���͂����ƕʂ̎����������ė���Ǝ��͌��Ă���B���̓_�ɂ��Ă͎��͂�݂��Ę_�������ł���B�@�Ƃ�����A�v�l�͂��̂悤�ɁA���݂��̂��̂̔g���Ƃ��ď�ɑ��݂��Ă���B���̎v�l�����o����A���]�̓����Ƃ����܂��āA�l����Ƃ����s�ׂ����܂��B�@�@
���B�͉��X�ɂ��ē��]�ɂ��v�l�������Ƃ炦�Ă��܂������ł��邪�A�v�l�̍\���͌����Ă��̂悤�ȏ����ȗ̈悾���ł͐����̂��Ȃ����̂Ȃ̂ł���B
�v�l�������F���ɂ�������݂Ƃ��Č���Ȃ�A����͂܂��ɉF���G�l���M�[�̔g�����̂��̂ƌ����邾�낤�B
�@�G�l���M�[�Ƃ͈ӎ����Ƃ����_���͊��Ɏ��B�̌��ė������Ƃł��������A���̂��Ƃ��猾���Ȃ�A�v�l�͈ӎ��̗h�炬�ł���ƒ�`�Â��邱�Ƃ��o����̂ł���B
�@�����Ă����͊m���ɁA���̂ł͂Ȃ���Ԃł���B���́u��ԁv�����̂ƌ���Ƃ���ɁA�v�l�̋��\�����������̂ł���B
�v�l�͂��̂悤�ɁA�ӎ��̕ϓ��Ƃ����G�l���M�[��Ԃ�������Ƃ��Ď�鎖���琶�ݏo�����B�����Ɏv�l�̌��_������ƌ����邾�낤�B
���́@�o��
��P�߁@�ӎu
�@
�O�͂Ŏ��͎v�l�������I�ȍ݂�������Ă���Əq�ׂ��B�v�l�̖{���̓G�l���M�[�̗h�炬���̂��̂ɂ����āA�����ɂ͐��_�I�ȗv�f�����邱�Ƃ��o���Ȃ������B����Ɛl�Ԃ̓��{�b�g�Ɠ��������݂Ȃ̂��낤���B���_���͂����͎v��Ȃ��B���������͍����炭���̕����ɏ]���v�l�̌`�����Ă��������B
�@�Ƃ���Ől�Ԃ̐��_�����ے��Â�����̂Ɉӎu������B�l�Ԃ͂��̈ӎu�������ēƎ��̍s���l�������肵�A���炱�̍s���ɑ��ĐӔC�����B
�@���̍l�����ɂ́A�ӎu�͎��������R�ɑ������̂��Ƃ��������ϔO�����݂���B�������͂����Ă������낤���B���͂��̎v�����݂ɂ͂Ȃ͂��^������̂ł���B
�@�͂����Ė{���Ɉӎu�͎��̎��R�ɂȂ�̂��낤���B
�@�m���Ɏ��B�͎���̈ӎu�������Ďv�l���R���g�[�����邱�Ƃ��o����B���ꂱ��̖����l���悤�ƁA�v�������点�A���邢�͗F�l�Ɏ莆���������ƃy��������B���̂悤�Ɉӎu�͎��̍s�������肵�Ă���B�����l����͎̂��Ɏ��R�Ŗ��A�����̎��̂悤�Ɏv���邾�낤�B
�@���������̎����Ǝv�����������ɐ[���Njy���Ă݂�ƁA�����Ă���͊m���Ȃ��ƂƂ͌����Ȃ��̂�������̂ł���B
�@�Ⴆ�A�����Ɉ�̂͂�����Ӑ}���ꂽ�v�l������Ƃ��悤�B����͂ǂ�Ȃ��ƂɊւ���v�l�ł����Ă����܂�Ȃ����A���R�����ɂ́A�u���ɂ��Ă̍l�@�v�ƌ������悤�ɖ��m�Ȉӎu�������Ă���B�܂�ӎu�Ƃ͂��̎v�l���N�����A���[�h���铭�������Ă���ƍl�����邾�낤�B
�@����ƁA���������̍l�����N�����Ƃ��A������l����Ɩ�����ӎu���܂�����ɐ旧���đ��݂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃł���B
�@�������������Ƃ���ƁA���̈ӎu�͈�̂ǂ����琶�܂�ė����ƌ��������̂��낤���B
�@�����ӎu�������A�����Ă��̈ӎu�ɏ]���Ďv������̂��Ƃ���Ȃ�A���̎����Ă��邱�̈ӎu�͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂�ė����̂��B���ɂ��ꂪ�O�ӎu���琶�܂ꂽ�ƌ����Ȃ�A�Ƃ���Ɏ��B�͂��̑O�ӎu�͑O�O�ӎu���琶�܂ꂽ�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邾�낤�B
���ǂ̏��ӎu�͖����ɐ摗�肳��čs�������Ȃ��B�������Ƃ���ƁA�ӎu�ȂǂƂ������̂͂��Ƃ��Ƒ��݂��悤���Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@������ӎu�̑��݂�F�߂�Ƃ���Ȃ�A���B���ӎu�ƍl���Ă�����̂͂��ׂāA���̉F�������܂ꂽ�u�Ԃ�����ɑ��݂��Ă����Ƃ����悤�ȍl������������܂��B�����N���O����A�����̎��̍s�����ӎu�Ƃ��Ċ��Ɍ��肳��Ă����ƌ����̂ł���B
�@���R�����ł́A�ӎu�͌�ʂ�z���đ��݂��A�F���̓����̂��ׂĂ����̈ӎu�ɂ���ē�������Ă���ƌ������_�ɍs�������B�����ł͐�ΐ_�̂悤�ȑ��݂����z�肷�鎖���o���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炱�̈ӎu��_�Ɉς˂��Ƃ��Ă��A�_�̈ӎu�ݏo���ӎu���܂�����K�v�ɂȂ邩��ł���B
���̍l��������́A�ӎu�Ƃ͉F�����������I�@�����̂��̂��ƌ������ƂɂȂ邾�낤�B���̍l�����͏d�v�ŁA����Ɋւ��Ĕے肷�����͂Ȃ��B���������������Ă��܂��A�Œ肳�ꂽ�^���_�̗ނ����o�ė������ŁA���B���C���[�W����ӎu�Ƃ͗���߂��Ă��܂��C������̂ł���B
�@�P�ɕ\���̖��ł͂��邪�A���͈ӎu�ɂ��āA���������l�ԓI�Ȏ��삩�璭�߂Ă݂����̂ł���B����ƌ��ǂ��̂悤�ȕ����ňӎu�𗝉����邱�Ƃ͏o���Ȃ����ɂȂ�B
�@�ł͈ӎu�Ƃ͉����ƌ������ƂɂȂ邪�A���̍l�������_���猾���A����͋������o���ꂽ�v�l���ƌ������ƂɂȂ�B�������͂��̎��o���ꂽ�v�l���ӎu���ƍl���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�@���Ȃ킿�ӎu�́A�v�l�������ł������悤�ɁA�����炪���ݏo���̂ł͂Ȃ��A���̒��ł������R�̖@���̂܂ܐ��܂�ė�����̂Ȃ̂ł���B�܂���Ɍ��ė����悤�Ɏv�l�͎��̒��ɐ��܂�o��G�l���M�[�̗���ł��������A���̒����玩�o���������ӂ������t����v�l�����B�Ɉӎu�Ƃ��Č����Ă���ƍl������̂ł���B
�@�_���I�Ȏv�l�ł�����O�ł͂Ȃ��B
�@�Ⴆ�Έ�̖����l�������Ă���w�҂�����Ƃ��悤�B�ނ͋����ӎu�ł����ē��ɒ���ł���悤�Ɍ����邵�A�{�l���܂������F�����邾�낤�B
�@���������Ӑ[�����Ă݂�ƁA���̔ނ̎v�l�͔ނ����o���Ă���̂ł͂Ȃ�����������B�ނ����̂�������A���̎v�l�����グ��O����ނɂ��̐v�}���p�ӂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�v�l���n�߂�O������ɂ��̖��̓�����m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂ł���B
�@�����������ɂ́A�v�l�͂���Ӗ��ňł̒��Ɏ�T��œ����čs���悤�Ȃ��̂ł���B�����ɂ͏��߂���v�}������̂ł͂Ȃ��A�܂��ɖ��̒�����^����T�蓖�Ă��ƂɊO�Ȃ�Ȃ��B
�@���������Ă��̎v�l�͔ނ����o���Ă���̂ł͂Ȃ��B�ނ̎v�l�͂����Ò��͍��̏�Ԃœ����Ă��邾���Ȃ̂ł���B�v�l�͔ނɂ͊W�Ȃ��ނ̒��œ����Ă���B�ނ͂������̐��܂�o��v�l�����o���]������Ɏ~�܂�B���B�͂�����������l���Ă���Ɨ������Ă��邾���Ȃ̂ł���B�@
�@��̖����l�������邱�Ƃ��o����̂́A���̎v�l�ɑ��鎩�o���������߂ł����āA���ӂ����̈�_�Ɍ������Ă��邩��ɊO�Ȃ�Ȃ��B���̂��߂Ɏv�l�͎��X�ƘA�������I�Ɉ�̖����l��������̂ł���B���ꂪ���B�ɂ͈ӎu�����݂��邩�̂悤�Ɍ�����̂ł���B
�Ƃ�����ނ������������I�Ɍ��肵�Ă����悤�Ȉӎu�ȂǂƂ������̂͂��Ƃ��Ƒ��݂��Ă��Ȃ������̂��B����̂́A�ނ̓����Ŏ��R�ɐ��ݏo����Ă���v�l�ɑ��鎩�o�Ȃ̂ł���B
�����Ō��_���J��Ԃ��Ă��������B
�@���Ȃ킿�ӎu�Ƃ͎��o���ꂽ�v�l�ł����āA�ŏ�����ނ̒��ɔ������Ă�����̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�����l�ɂ���Ĉӎu�̎��������Ⴄ�̂́A���܂�ė���v�l�̈Ⴂ�����邪�A���̎v�l�ɑ��鎩�o�ƁA���o���ꂽ�v�l�̂Ƃ炦���ɑ���ԓx�̍��قɂ��B
��Q�߁@�����E����
�@
�@�v�l��ӎu�����ݏo���ꂽ���̂ł���ƌ����_���ɗL�͂ȏ؋��Ƃ��āA���͊����Ƌ��������グ��B
�@�l�X�͗l�X�Ȃ��̂ɑ��Ċ�������������B���������̂�������A�|�p��l�X�̍s���Ȃǂɑ��āA���B�͊������ė܂𗬂�����A�S�g�̐k�����o�����肷��B���̂悤�Ȋ������o�����Ȃ��l�͂܂����Ȃ��ƌ����č����x������܂��B
�Ƃ���Ŋ���������璭�߂�ƁA���B�͂��炩���ߊ������������āA������N�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�������B�����͓ˑR����ė���̂��B���B�͊��������R�ɃR���g���[�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ͑̌���N���������o���鎖�ł��낤�B�l�͒N�������̍D���ȂƂ��Ɋ���������A�������ĐS�k���Ă���Œ��ɂ�������������肷�邱�ƂȂǏo������̂ł͂Ȃ��B�����͎����̓����ł����N����܂܂ɂ��Ă������Ȃ��̂ł���B
�@���ׂĂ̊����͐^���ɐG�ꂽ�Ƃ��ɋN����B����͋N�����̂ł͂Ȃ��N����̂ł���B
�@�������ۗ����Ă���̂́A���B�̓��킪�_���I�v�l�Ƃ������\�̐��E�Ɏ�芪����Ă��邩��ɊO�Ȃ�Ȃ��B���B�͎���Ԃ������̐��E���Ǝv������Ő����Ă���B���̎v�����݂�˂��j���Đ^�������ɂ���ė���B�����͂����ɋN����̂��B�����Ƃ͎��݂ł��鎄�����̎��݂ɂ��̂܂ܐG��邱�Ƃ���N������d���ۂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B
�@�Ƃ���Ŋ����͈ӎu�ƒ�������B�����͋����⊴�����ĂсA���łȈӎu�ݏo���B���邢�͂�������^�Ȃ���̂ւ̖ڊo�߂��N����B���R��������A���̎҂̐l���̕����������ݏo�����B���Ȃ킿��苭�łȈӎu�����l�i���`�������̂ł���B
�@�����͏�Ɉӎu����������B���̃V�X�e���́A�ӎu���v�l�̎��o���Ƃ����l������ȒP�ɋL�q�ł��邾�낤�B�����͎v�l�̍ł��N���Ńh���}�`�b�N�Ȏ��o�ɊO�Ȃ�Ȃ�����ł���B
�@���łɏq�ׂ����A�����͎��B�̑̌��ɂ���Ė��炩�Ȃ悤�ɁA�����Ď��������̎��R�ɂ���č��o�����̂ł͂Ȃ��B�����͂���ė���̂��B
�@�����Ɋ����͎��̐S��h�蓮�����A�ӎu�ƒ�������B���Ȃ킿�����Ȉӎu���܂��������琶�܂�ė���Ƃ݂Ă����̂ł���B
��R�߁@�C�Â�
�@���łɉ��x�����グ�ė������A�����ł��炽�߂ċC�Â��Ƃ����������グ�Ă��������B
�@���͂����ɐl�Ԃ̍ł��{���I�Ȃ��̂�����Ɗm�M����B�����ɐ��_�I�Ȃ��̂��A���̋C�Â��̒����猻���̂ł���B
�@�������̋C�Â��ƌ����̂́A��Ɏ��̑O�Ɍ���Ă��Ȃ���A�������ł�����������݂ł���Ƃ��������܂������Ă������B
�@�C�Â��𗝉����邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��v�l�ɂ��Ă̐�����������g�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�v�l�͐�̂悤�ɗ����ӎ��̔g���ł���ƌ������Ƃ�̌��Ƃ��Ēm��K�v������B
�@�����łȂ���A�C�Â��Ǝv�l�����������܂܂ŁA���B�̗����͋C�Â��Ƃ����[���Ȃ�^���ɍs���������Ƃ͂Ȃ����낤�B
�C�Â��Ǝv�l����������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��A�܂����̂��Ƃ�������čs�����Ƃɂ������B
�@���B�͗l�X�Ȏv�l�����ė������A���̂Ƃ��낻���œW�J�����v�l�ɂ��Ă̋c�_�́A�قƂ�ǂ̏ꍇ���̖������������ė����̂ł���B�v�l�������I�ȑ��ݘ_�Ƃ��ċL�q�o�����̂́A�v�l�ɖ������Ă���C�Â��̗v�f�����グ�Ȃ���������ɊO�Ȃ�Ȃ��B
�@�Ƃ���ŕ��ʁA�����l����ƌ����Ƃ��A�����Ɏv�l�̓������������o���Ă����������������ƂɂȂ�Ȃ��B
�@�Ⴆ�Η[�H�͉��ɂ��邩���l���Ă���Ƃ��悤�B���͗①�ɂ̒������Ă��ꂱ��v�������炵�Ă���B���̂Ƃ����R���͂��̎v�l�̉ߒ���m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ���Ύ��͖��V�a�҂ł����Ȃ��̂ł���B
���炩�Ɏ��͂��̉ߒ������o���Ă���B���̎v�l�̓����́A�H�ނ�F�����A�������琶�܂��A�z�ɂ���ė����̃��j���[��g�ݗ��Ăčs���A�����闝�O�v�l���s���Ă���ƌ����邾�낤�B
�Ƃ���Ŏ������̂悤�ɍl���Ă���Ǝ��o����̂́A�܂��ɂ��̎v�l�ɑ��Ă̋C�Â��������ď��߂ĉ\�ɂȂ�B�܂莄�B�͋C�Â��������ď��߂Ă��̎v�l��m��̂ł���B
�@���̈Ӗ��ŁA�����o�̂܂܂œ����Ă���g�̓I�v�l�ƌ����̂́A���͋C�Â����Ȃ��܂ܐi�s���Ă���v�l�������̂ł���B
�@���B�͏K���I�ɁA�C�Â��Ǝv�l����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂����A����͑�ςȌ��ł���Ǝ��͎咣�������B�����Ă��̌�������͋C�Â��Ǝv�l�̖����ƌĂԂ̂ł���B
�@�������̖�����F�߂Ă��܂��Ȃ�A���B�ɂƂ��Ă̎v�l�͗��O�v�l�ƈꕔ�̏�O�v�l�̗̈�Ɍ����Ă��܂����낤�B�܂�C�Â��̂Ȃ��v�l�͎v�l�Ƃ͂Ƃ炦��ꂸ�A�P�Ȃ銴�o�Ƃ��ď�������Ă��܂����낤�B�������ł͂��A���̖����͐l�ԑ��݂̐^�����������B���Ă��܂��̂��B
�@�C�Â��͌����Ďv�l�̈ꕔ�ł͂Ȃ��B����͊��S�Ɏv�l�Ƃ͕������ꂽ���݂Ȃ̂ł���B
�@�①�ɂ��J����ƐH�ނ�����ł���B���͂��ꂪ�j���W�����Ƃ��������Ƃ����ʂ�����B���̎��ʂ͊T�ˎ��o�ɂ�邪�A���o�⓪�]�̓��������ł͂��ׂĂ͂����ł̂܂܂ł���B�����ɋC�Â��������ď��߂ė①�ɂ�`���Ă��鎩����m�邱�ƂɂȂ�B
�@�C�Â��͎v�l�����Ɏ~�܂炸�A���������A�C�Â��Ă��鏊�̈�̂��̂��ΏۂɂȂ�B�����A��������芪�����̂��ƁA���E�̂��ׂĂ͎��R�̂܂ܑ��݂��Ă��邪�A�����͋C�Â��ɂ���ď��߂Č������Ă���̂ł���B�C�Â��Ȃ���Ύ��͐��������̑��݂�m�邱�Ƃ͂Ȃ��B�����͈łɕ����ꂽ�܂܂Ȃ̂ł���B
�@�����Œm��ƌ����Ă���̂́A�����̓�����m��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�܂������ɒm�낤�Ƃ���ӎu���K�v���Ƃ����̂ł��Ȃ��B�������ɋC�Â��Ƃ������Ƃ̊O�ɈӖ��͂Ȃ��̂ł���B���ƌ����Ƃ��A�����ɂ͂��łɎ��ɑ���C�Â������݂��Ă���̂ł���B
�@����ɂ��Ă����̋C�Â����������͓̂���B�v�l�Ƃ̖��������܂�ɂ���������ƌ����̂����邪�A����肻����X�g���[�g�ɕ\���o���Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�C�Â��͂��ꂼ��̒��ɑ��݂���ŗL�̑̌��ł���A���t���z�������݂ł��邩��ł���B
�@�����ł͒P���ɁA����v�l�����܂�Ă��A����ɋC�Â��Ȃ���Ύ��͂��̎v�l��m�蓾�Ȃ��Ƃ��������Ɏ~�߂Ă������B
�@�Ƃ���ŁA��v���̂ɉ䂠��Ƃ����������͐^���ł͂Ȃ��B�����ɂ͖��炩�Ɏv�l�ƋC�Â��̖���������Ǝ��͎咣����B�@�䂠��Ƃ͋C�Â��̏�Ԃ������B��ɋC�Â��A���̎v���ɋC�Â����Ƃ��Ȃ���Ή䂠��Ƃ͌����Ȃ����낤�B�Ȃ�Ή�v�������ł͉䂠��Ƃ͌����Č����Ȃ��̂ł���B
�@��v���A���̂��ƂɋC�Â��Ă�����̂̑��݂������ď��߂Ď��B�͂����ɉ䂠��ƌ�������̂ł���B���B�͂��̋C�Â��̑��݂ɂ����ڂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B��������͓̂�����A���������̂Ƃ���C�Â��Ƃ́A���B�̍ł��g�߂Ȗ��Ȃ̂ł���B�Ȃ��Ȃ玄�B�́A���̓�����C�Â��Ƌ��ɐ����Ă��邩��ł���B���B�͂������ꂪ�A���܂�ɐg�߉߂��ċC�����Ȃ������Ȃ̂��B
�@���ʎ��B�͏n�����邱�ƂŎ��o�������B�������₪�Ėڊo�ߎn�߂�Ɠ����ɁA���B�͎����Ɛ��E��F�����n�߂�B�܂��Ɏ����������Ă��邱�ƂɋC�Â��̂ł���B
�@�ł͋C�Â��͔F�����̂��̂��ƌ����邾�낤���B
�F���Ƃ͎����Ƃ̊֘A�ŕ����𗝉�����Ƃ������Ƃ��������A���̂��Ƃ���l����Ȃ�A������̂�F�����邽�߂ɂ͂܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B���Ȃ킿�䂠��ƌ����C�Â����F���̂܂��ɑO������ɂȂ�̂ł���B�C�Â����Ȃ���ΔF�����̂��̂����������Ȃ����ƂɂȂ邾�낤�B
�@�������ł͂Ȃ��A���B�͔F���̐�������ߒ������ɏڂ������Ă��邪�A���̉ߒ��̑S�Ăɂ킽���ċC�Â������݂���B�����ɋC�Â����Ȃ���A���B�͔F������Ώۂ������̂��B
�@�������܂����R�̂��Ƃł͂��邪�A���̔F���̉ߒ����̂��̂́A�v�l�̉^���ł����āA�C�Â����̂��̂ł͂Ȃ��B�C�Â��͂������̎v�l�����߂邾���̑��݂��ƌ������Ƃ��o���邾�낤�B
�@�v����ɔF���́A�v�l�̓����ƁA����ɑ���C�Â��ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł���B
�@�J��Ԃ��A�F���́A���̂��̂ɑ��锻�f�̉ߒ��ł���A������̉ߒ���ʂ��ď�ɋC�Â��͑��݂��Ă����������Ă���̂ł���B���邢�͂܂��A�������l���A�������Ă���̂��B���������A�������Ă���̂��Ƃ����悤�ȁA�ڊo�߂Đ��E�̒��ɂ��邱�̎��̎v�l��s���⊴�o�̂��ׂẮA����ɋC�Â����ƂŎ��o�����B���̑S�ĂƂ������鎄��Ԃ͂܂��ɋC�Â��ɂ���Ď��̂��̂ƂȂ��Ă���̂ł���B
�@���ہA�C�Â��͎v�l�ɑ��Ă�������̂ł͂Ȃ��B�ڊo�߂Č������������A���łɂ����ɋC�Â�������B�����Ĉ���̐����������čĂі���ɗ�����܂ŁA���̊����̈�͋C�Â��ɂ���Ė���݂ɏo��B
�@���̂悤�Ɍ��ė����Ƃ��A���B�ɂ͋C�Â��ɑ����̍l�����܂Ƃ܂��ė��͂��Ȃ����낤���B
�@�܂��l����Ƃ������Ƃ��v�l�ƋC�Â��ɕ������ꂽ�Ƃ������Ƃ���A���Ƃ͉��Ȃ̂��Ƃ�����肪������x����Ă���B
�@��v���A���Ȃ킿�����l����ƌ����Ƃ��A�����ɋC�Â�������B�l���Ă��鎄�ɋC�Â����߂Ă���u���v���Ȃ��Ă͂��̎v�l�͐��藧���Ȃ��B���藧���Ȃ��̂ł͂Ȃ��m�蓾�Ȃ��B
�����ɂ݂������Ă���Ƃ��A���̒ɂ݂ɋC�Â��Ă���u���v���Ȃ��Ă͂���͂�݂̒��ɕ����ꂽ�܂܂ł��낤�B
�@���邢�́A���ꂢ�Ȍ��i�ɐS�D���Ă���Ƃ��A����ɋC�Â��Ă���u���v�Ȃ����ẮA�����̕����I���ۂɉ߂��Ȃ��Ȃ�B
�@���͐����Ă���ƌ����邷�ׂĂ̂��Ƃɑ��āA����ɋC�Â��Ă���u���v�Ȃ����Ď��͖��ɓ��������낤�B
���ǎ��Ƃ͉����ƌ����₢�́A�ŏI�I�ɂ͂��̋C�Â��Ă�����̂ɍs�������Ă��܂��B���̔w��ɂ͂��̋C�Â��̑��݂�����̂ł���B
�@�Ƃ���őO�͂̌��_�Ƃ��āA���͎v�l�����ɕ����I�ł���Əq�ׂ��B�v�l�Ƃ��������̂ǂ������Ă��A�����ɂ͕����ɂ������Ŏ���������肵�������ė��Ȃ������B�������v�l�͎������ݏo���Ă���̂ł͂Ȃ��A�����F���̗h�炬�ɑ����Đ��܂�Ă���̂��Ƃ������Ƃ������Ɍ��ė����̂ł���B
���ǂ̏��A�v�l�͎��̑̓��ƉF���̑��֊W�ɂ���Ď��R�ɐ��܂�o�Ă���G�l���M�[�̔g���ł���B���ꂪ���̌��_�������̂ł���B
�@����Ɠ��R�̂��ƂȂ���A���̕����̖@���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�v�l�ɂ͎��炻�̎v�l�ɋC�Â��Ƃ����v�f�͂ǂ��ɂ��܂܂�Ă��Ȃ��B�����ɋC�Â��̔\�͂�F�߂��ɂ͍s���Ȃ��̂ł���B�ǂ��܂ōs���Ă������ɂ͋C�Â������܂�Ă��鎖�͂Ȃ��B
�@���͂����ɖ�����萸�_�����������Ă��܂��悤�Ȑ_���`�҂ł͂Ȃ��B�����܂ʼnȊw�I�ɐl�ԑ��݂�T���čs���Ȃ�A�l�Ԃ̎v�l���܂��A�Ȋw�I�ɋL�q�ł���F���̖@���̂܂܂ɗ���Ă���̂ł���B
�@�������܂�����ŁA�P�ɉȊw�I�ȕ��͂����Ől�Ԃ����悤�Ƃ���Ȃ�A�������͌����Đ^���ɍs���������Ƃ��Ȃ��̂��ƌ������Ƃ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ɂ��߂��ꂸ�Ȋw�I�ɂ��̂��Ƃ��l����A���̂��Ƃ��܂������ł��邱�Ƃ��������Ă����낤�B
�@���Ȃ킿�A�����ɉȊw�I�ȕ��͂ł����Ă��A���ꂪ�v�l�ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��B���������Ďv�l�Ƃ͉����Ƃ����₢�͂��̎v�l�̒��ł������X������J��Ԃ������Ȃ����ƂɂȂ�B���B�͎v�l�̓�������A���̎v�l���̂��̂��q�ϓI�Ɍ���藧�Ă������Ȃ��̂��B�������v�l�̓����ɂ͋C�Â��Ƃ������_�������ݏo�����悤�ȗv�f�͂ǂ��ɂ��Ȃ��̂ł���B
�@�Ȋw�ɂ�镪�͂ł́A���ǂǂ��܂ōs���Ă����_�����L�q���邱�Ƃ��o���Ȃ��B�Ȋw�̓��{�b�g����邱�Ƃ��o���邪�A�����m�炵�߂�C�Â���������邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂��B
�@����ł��������Ɍ��R�Ƃ��Ď�������B��v���܂��ɂ��̎������݂��Ă���̂ł���B���Ƃ��Ȋw�ł͋L�q�ł��Ȃ��Ƃ��Ă����������ɂ���̂͊m���ł���B���������͉��̓w�͂������ɁA���������Ă��邾���Ŏ����������ɂ��邱�Ƃ�m��B���͂������݂��邾���Ŏ����ɋC�Â��Ă���̂ł���B
�@�����܂ŗ���ƁA�Ȋw���Ύ����邽�߂ɁA�Ȋw�ŋL�q�ł��Ȃ������Ӗ��Ȃ��̂ƒf�肵�A�_��I�Ŕ�_���I�Ȃ��̂ƌ����悤�Ȍ����͔ᔻ����˂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�^�ɉȊw�I�ł���Ȃ�A�Ȋw�ŋL�q�����Ȃ����݂��܂��F�߂邱�Ƃ������ӂ��킵���Ǝ��͍l����̂ł���B�Ȋw�I�ɐ����������̂������^���ł���ƌ����l�����͕Ύ��I�ł����āA�����ĉȊw�I�Ƃ͌����Ȃ����낤�B
�@�܂��ɂ��̎��_�Ől�ԑ��݂̌��_�́A�Ȋw���z����̂ł���B���̉Ȋw�ŋL�q�����Ȃ����̂��A�C�Â��̑��݂ł���B
�@�Ȋw�͉F���̉^����A�����̎d�g�݁A�l�Ԃ̋N����v�l�̂��炭���������������낤�B���̗������S�ɐ������������Ƃ����\��������Ȃ��B���������Ƃ��Ȋw���A���̋��ݐs�����Ȃ��F���̑S�̂���������Ƃ��Ă��A����͂ǂ��܂ōs���Ă��łɕ�܂ꂽ�܂܂ł��낤�B���I�ȃ��{�b�g�������̑��݂�m��Ȃ��悤�ɁA���x�ȉȊw�̐��ʂ��A���ꂾ���ł͂��̐��ʂ��̂��̂̑��݂�m�邱�Ƃ��o���Ȃ��B�܂��Ɉłɕ����ꂽ�܂܂Ȃ̂ł���B
�@�����Ɍ��Ă�̂́A�Ȋw���z�������݂ł����Ȃ��B���ꂱ�����C�Â��ɊO�Ȃ�Ȃ��B
�@���炩�ɁA���ɋC�Â��Ă���u���v�����݂���B���́u���v�͋C�Â��Ƃ��������悤�̂Ȃ����݂ł���B���̎��݂��Ȃ���Ύ��͂��Ƃ����݂����Ƃ��Ă����ɓ������B�܂��ɏn�����Ă��鎞���C���[�W����Ε�����悤�ɁA�����ɂ͈ł����Ȃ��̂ł���B
�@�J��Ԃ����A�C�Â��͎v�l�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�Č����Ȃ�C�Â��͌��ł���B�ł̒�������݂��Ƃ炵�o���B����������͏Ƃ炵�o�������ł����āA���f���邱�Ƃ͂Ȃ��B���f�͎v�l�̗̈�ł����āA�C�Â��͂��̔��f�����Ƃ炵�o���B�܂��ɏ����ȋC�Â����̂��̂Ȃ̂ł���B
�@����ɂ܂��A�C�Â��͔F���ł��Ȃ��B����͔F���̏�ɂ����āA���̔F���̑��݂�m�炵�߂�B����͎����z���������ł���B
�@�C�Â��͉������Ȃ��B�������߂Ȃ��B�C�Â��̒��ɂ͐^�P���Ƃ����悤�Ȑl�ԓI�ȊϔO�����Ȃ��B���������ɂ����āA�����C�Â�����̂ł���B
�@���Ƃ͉����ƌ����₢�ɑ��āA���͕����ł���Ƃ��������ɖ�������Ƃ����Ȃ�A���͊��S�ɉF���̂Ȃ��ɗn������ł��܂����낤�B�Ȃ��Ȃ玄�B�͕̑̂����I�ɓ��O�̋��E���������Ȃ�����ł���B���������ł���Ƃ�����������́A���͌Ƃ��đ��݂����Ȃ��B����̂͂�����̉F���Ȃ̂ł���B
�@����A���͐��_�I���݂ł���Ƃ���������F�߂�Ȃ�A���͏����ȋC�Â��Ƃ������݂ɏW���B���͋C�Â��̒��ɏ����čs�������Ȃ����ƂɂȂ�B�C�Â��͌��z�������݂ł���A���R���̒��ł͎��Ƃ������̂͐������Ȃ��̂ł���B
�@��������͂ǂ̂悤�Ɍ��Ă����݂����Ȃ��ƌ������ƂɂȂ��Ă��܂����낤�
����͎��B�̘_��������Ă��邩��Ȃ̂��낤���B
�@���͂����͎v��Ȃ��B�ނ��뎄�B�̘_���̋ؓ��͐����������̂ł���B���̎������݂��Ȃ��Ƃ������_�́A�Â�����@�����^���Ƃ��Ď����ė��������Ɗ��S�ɕ�������B
�@�T�̋�ς�A�_�Ƃ͈��ł���Ɖ������L���X�g��A�F������������镧�ɁA�����̋������X�A�\���͈���Ă��A�����Ɍ���Ă�����e�͎��B�̒B�������_�ƕς��Ȃ��Ǝ��͍l����̂ł���B
�����@���́A���B�̂悤�Ɏ��s���낵�Ȃ���i�܂Ȃ��B�@���̂����͒��ڂ��̐^���̒��ɔ�э���ōs�����Ƃ���B����͑T�̈ꊅ�����ŏ\���Ȃ̂ł���B����͍ł��ߓ��ł͂��邪�A�������t�ɖ}�l���勓���Ă����Ɏ��铹�ł͂Ȃ��B���͒m�����̂ē��錫�҂݂̂��킸���ɓ��B�o���铹�Ȃ̂ł���B
�@���B�����������Ȃ���i�ނ����Ȃ��̂́A���N�ɂ킽���Đg�ɂ����m�����̂ē��Ȃ�����ɑ��Ȃ�Ȃ��̂��B�����Ă��̒m���͂���ɖ₢������B
�@����������ł����͑��݂���ł͂Ȃ����ƁB���݂��Ȃ����̂��ǂ����Đ��܂��̂��A�ƁB�@
�������܂��̂́A�����ɂ��B�����Ɛ��_�̖����A�v�l�ƋC�Â��̖����ɂ���āA���͐��ݏo�����̂��B
�@���̓X�N���[���ɉf���o���ꂽ�f���Ɠ������݂ł���B�f���̎��̂̓X�N���[���ƌ���ł���悤�ɁA���̎��́A�v�l�ƋC�Â��ɂ���ĉf���o����Ă���ɉ߂��Ȃ����݂Ȃ̂ł���B
�@���̏؋��Ƃ��āA���͖��������グ��B�X�N���[���ɂǂ�ȉf���ł��ʂ��o����悤�ɁA���͂ǂ�ȑ��݂ɂ��Ȃ蓾��B�����v�������ŁA���͍������ɂł����܂łƐ����̂����o���邵�A�v��������̈��s���P�s���s����B������E�����Ƃ����ĉ\�ł��낤�B�@���̖����͎��Ƃ������̂����݂��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�l�͂܂��ɂ��̎��̖̂�������Ԃ̒��ō��������̂��Ƃ��ɕY���Ă���B��Y�͎��̂��Ȃ����炱�����ݏo�����̂ł���B
�@��������x��������ڂ����点�A�^���ɖڂ�������ƁA�����Ɏ��݂�����Ă��Ď��͋�Y�Ƌ��ɏ�������B���̎��݁A���Ȃ킿�����ȋC�Â��́A�����ėh�邪�Ȃ��Â��Ȃ����ē����ȋ�C�̂悤�ɍL�����Ă���B����͐��܂�������A���ɂ����Ȃ��i���̑��݂ł���A�ł��Ƃ炷�����Ȃ̂ł���B
�@���̓����ɏƂ炵�o�������̂́A����Ȃ������̕��V���鐢�E�ł���A�����ł̓G�l���M�[�ۑ��̖@�����x�z���Ă���B���Ȃ킿���������Ȃ�����������Ȃ��i���ɕs�ł̐��E�����O����B
�@�C�Â��͌��ł���A�����͈łł���B���͂܂��ɂ��̌��ƈł̒����琶�ݏo���ꂽ�ꎞ�̌��z���Ƃ�����̂ł���B���z�����炱�����܂ꂻ���Ď��ʂ̂ł���B
�@���B�͒a������сA�����������B�������ӂƋC�����ƁA�����̉f�������Ă�����݂�����B���̕s���ɑł��̂߂���Ă����̂̓X�N���[���ɓ��e���ꂽ���ł����āA�f�悩����߂��҂̂悤�Ɏ��݂͂����ɂ��葱����B��ŏq�ׂ�o���Ƃ͂��̂��Ƃւ̖ڊo�߂������̂ł���B
�@�C�Â��ɂ��Ă����������������čl���Ă݂悤�B
�@�ڂ̑O���K�N����֍炢�Ă���B���̂Ƃ����͋C�Â��̒����K�N��F������B�����ڂ����ƂƂ���Ɉł�����ė����K�N�͌����Ȃ��Ȃ�B���������̈ł��܂��C�Â��̒��ɂ���B�����K�N�Ɠ����悤�ɂ��̈ł�F������̂ł��邪�A���Ƃ��F���͕ς���Ă��A����Ȃ��̂ɂ͂������Ȃ��C�Â��͑S���������Ȃ����݂��Ă���̂������邾�낤���B
�@�ڂ��J���Ă����Ă��A�����ĕς��Ȃ����̂�����B����͎��̕ω������ߑ�����C�Â��ɊO�Ȃ�Ȃ��B�����ǂ��ω����čs���Ă��A���Ƃ������낤���A�l�X�Ȏv�l�����炻�����A��ɕς��Ȃ��Ŏ�������������̂����͑̌����邱�Ƃ��o����B����͎����ǂ�ȏ�Ԃł����Ă������ł���B���̏�ɋN����l�X�ȕω��ɖڂ�D���Ȃ���A�C�Â��͏�ɂ����ɂ���B
�@����͂��Ƃ������Ă��鎞�ł����A�C�Â��͑��݂��Ă���̂��B�������B�͖��𗝉������Ȃ����߂ɁA���ɑ���C�Â��̑��݂𗝉��o���Ȃ������Ȃ̂ł���B
�@�C�Â��̑��݂͎��̕ω��ɂ͈�؊W���Ȃ��B�ނ��낻�̕ω����̂��̂����߂Ă���B���̍l�����������čs���A�������ʂƂ������ߑ����Ă���̂������邾�낤�B
�@���̋C�Â��Ƃ������݂͎������܂�悤�����̂����������ߑ�����B
�@���ƌ������݂͕����I�Ɍ��Ă��A���_�I�Ɍ��Ă����݂��Ȃ��f���̂悤�Ȃ��̂��Ɛ�ɏ��������A���̂��Ƃ��l�����킹��Ȃ�A���̎��݂͂��̋C�Â����̂��̂��������Ƃ�������̂ł���B
�@�C�Â��Ƃ͎��̖{���ł���A���܂ň�x�����܂ꂸ���ɂ����Ȃ��ő��݂������Ă���A�h�邪�Ȃ�������̐^�����ƌ�����̂ł���B
���͂��̋C�Â��̑��݂��ϏƎ҂ƌĂт����B
�@����Ǝ��Ƃ͉����Ƃ����₢�ɑ��āA���͊ϏƎ҂ł���ƌ���������Ԃ����Ƃ��o����B
�@���������̂Ƃ��낻�̓����͐������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�₢�ɑ��ē����邱�Ǝ��̂��A���łɌ��t�̗̈�ɑ��ݍ���ł��邱�ƂɂȂ�B�ϏƎ҂ƌ������Ƃ���A�C�Â��͂��̔��ɕ����߂���B�ہA�����߂��Ǝv�������̒��ɂ͂����̋����邾���ŁA�C�Â��͑��ς�炸���̊O�ɂ����āA���̊ϏƎ҂ƌ������ߑ����Ă���ł��낤�B
�@�������͂��̋C�Â��̑��݂ɑ��āA�ǂ̂悤�Ȗ��O�łł��Ăѓ���B�_�ƌĂڂ����A��ƌĂڂ����A���邢�͐^���╧�ƌĂڂ����A�����ɉ��̖W�����Ȃ��B�܂茾�t�Ƃ͂��̌���̂��̂Ȃ̂ł����āA�v�l�̎����Ɏ~�܂���̂Ȃ̂��B
�@�������C�Â��͂��͂₱�̌��t�̎����ł͂Ȃ��B���̎������z���ċC�Â��͎v�l���̂��̂����ߑ�����B�܂��ɊϏƎ҂Ȃ̂ł���B�@���B�͍��܂��ɁA���̋c�_�����X���肵�Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ւ������̂����ۂ����ݍ���ōs���āA���͂₱��ȏ�i�܂Ȃ��n�_�ɂ���ė��Ă���B�ւ͂��͂��̏����ȉ~�ł����Ȃ��̂��B���̉~�̒��Ŏ��B�̋c�_�͂��邮�����Ă���̂ł���B
�@�����C�Â��̑��݁A���邢�͊ϏƎ҂ƌ����Ƃ��A����͂��͂⌾�t�ł͂Ȃ��B���̉~���щz���āA�V���Ȏ����ɓ����čs�����̏��ł����Ȃ��̂ł���B��������t�Ƃ��Ď��Ȃ�A�Ăю��B�͐V���Ȍ��t��ݒ肵�Ē��z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������z�Ɋׂ邵���Ȃ��̂��B
���B�͂͂����Ă��̎��݂̒��ɓ����čs�����Ƃ��o����̂��낤���B���̖�͎����̂Ă邱�Ƃ��o���邾�낤���ƌ����₢�ɘA�����邪�A�ނ���Ř_������ł͂Ȃ��B
�@��ɐi�����B
��S�߁@���_
���̖��ɓ���O�ɁA���͂��������C�Â��Ɋ֘A���ďq�ׂĂ����������Ƃ�����B
�@����͈ӎ��Ƃ������t�̂Ƃ炦�����ɂ��Ăł���B���͑�R���A��Q�̖͂`���ŁA���ꎫ�T����ӎ��̐��������p���āA�����ɔF���̗v�f���������Ă���Ƃ��āA�{���̈Ӗ���ނ��A�ӎ���P���ɃG�l���M�[���݂Ƃ��ċK�肵�����A���̌��������Ŏw�E���Ă��������B
�@���͂����Ŏg�p�����F���Ƃ������t�ɂ������B�����Ŏ����g�����F���Ƃ������t�́A���炩�ɋC�Â��ƔF���̖����������̂Ƃ��Ď�舵���Ă����̂ł���B�܂�ӎ���������Ď��T�ɋL���ꂽ�Ӗ������ɂ͏��߂���F���̗v�f�Ȃǂ͓����Ă��炸�A����͈ӎ��ɑ���C�Â��̑��݂�\���Ă��������Ȃ̂ł���B���͂��������ĉ��߂��Ď����Œ�������Ƃ����Ƃ葊�o���Ƃ����ɉ߂��Ȃ��B
�@���͂����ʼn��߂Č×����`��������t�̑쌩�����������Ă��������B�ƌ����̂��A�{���g���Ă���ӎ��́A�ӎ��ƔF�������݂��Ă���̂ł͂Ȃ��A���͈ӎ��ɋC�Â����h������Ԃ��w���Ă����̂ł���B�C�Â��͂܂��ɂ��̂悤�ɁA�ӎ��̏�ɏh���Ă���̂��B���邢�́i�ӎ����C�Â��j�ƕ\�����Ă�������������Ȃ��B
�@�o�����ċC�Â��̒��ɓ����čs���Ƃ����ɂ͈ӎ�������B���Ȉӎ�����F���ӎ��ւƗn������ōs���A�C�Â��Ƃ��Ă̑S��̐��E�͂܂��Ɉӎ��ƋC�Â��̉������������E�Ȃ̂ł���B
�ӎ��̓G�l���M�[�ł���B�����ɋC�Â������݂���B�ӎ����u�C�Â��Ă��邱�Ɓv�Ƃ��ĂƂ炦��l�Ԃ̒m�b�͂܂��ɂ����ꂽ�c���������̂ł���B
�@���Ė{��ɓ��낤�B
�@���B����Ɏ������v�l�n�}�ɂ́A������o���Ɏ���c�����`����Ă���B����͐l�ԑ��݂_�I�ȑ��ʂ��猩���݂����i�K�I�Ɏ��������̂ł���B�����Ɏ��������o�Ƃ͂ǂ̂悤�ɐ����ł���̂��A���邢�͎��o�Ɗo���̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��A����������A�̖��͂܂���t�����ɂ���B�����Ă����ɂ͐��_�ƌ�����肪�҂��\���Ă���B
�@����܂Ŏ��͐��_�̖��ɗ�������̂�����ė������A���₻���ɖڂ������鎞�������̂ł���B
�@�����ł͋C�Â��̑��݂ƕ����̐��E�̊W���琶�܂�鐸�_���E�Ɏ��_�ĂāA�l�Ԃ������ɐ��_�I�ɏ����čs���̂������Ă݂����B
�@�P�D�����F���ӎ�
�@�ŏ��F���������������B�ψ�ȏ����F���̐��E�͋�ԂŖ�������Ă����B�₪�ăG�l���M�[�̉^�����N���蕨��������n�߂��B�����ƕ����݂͌��Ɉ��������A���邢�͔����������āA���E��n�߂�B�����ɓ����Ă��镨���Ԃ̃G�l���M�[�̔g�������͉F���ӎ��ƌĂ̂ł���B
�@�����ɊϏƎ҂͍ŏ����瑶�݂��Ă����B�ϏƎ҂Ƃ͂��̉F���ӎ��ɑ���C�Â��̗v�f�Ƃ��čl������̂ł���B�ϏƎ҂͂����F�������l�ߑ����鑶�݂Ȃ̂ł���B
�@�����������\����������ƌ����āA�����ɐl�ԓI�ȃC���[�W�������������Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�����ȋC�Â��̗v�f�������ɂ���Ƃ����Ӗ��ł���B
�@���̋C�Â��́A���܂�邱�Ƃ����ʂ��Ƃ��Ȃ����݂ł���Ɗ��ɏ��������A����͎��B�̘_���ł́A���̏��߂��I�����A�ǂ�����L�q�ł��Ȃ��ƌ������R�ɂ��B
�@���B���F���ł���̈�̒��ł́A�C�Â��͊m���ɑ��݂���B�������Ȃ��玄�B�͂��̎n�܂�ƏI����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B����͋t���猾���A���̋C�Â��Ƃ������݂����Ƃ��ǂ����Ŏn�܂�A�ǂ����ŏI���Ƃ��Ă��A���B�ɂ͂��������̂������������Ȃ����݂��ƌ����邾�낤�B
�@���Ȃ킿�A�C�Â��̗v�f�Ƃ��Ă̊ϏƎ҂͂���܂ň�x�����܂ꂽ���Ƃ��Ȃ��A���������Ď��ʂ��Ƃ��Ȃ����݂��̂��̂��ƌ����ق��͂Ȃ����ɂȂ�B
���������ĊϏƎҁ��C�Â��͏����F���Ƌ��ɂ��łɑ��݂��Ă����̂ł���B
�@���������E�͂��̋C�Â������グ��\�͂��܂����ݏo���Ă��Ȃ��ׂɁA�ϏƎ҂͐[�����荞��ł���B�����ɂ���͉̂F���ӎ������ł����āA���̂����߂����A�����ł̒��Ɏ~�܂��Ă���̂��B
�@�����ɂ͂܂����_�I�Ȃ��͉̂�������Ă��Ȃ��B���̐��E�͖��Ƃ����\�����悤���Ȃ��̂ł���B���������������̂ł͂Ȃ��B���E�͖�������āA�����Ȃ������Ȃ��[���������E�ƌ�����̂ł���B�����ɂ͂�����̐Â��Ȍ���Ԃ������L�����Ă������Ȃ̂ł���B
�Q�D���o�����_
�@�₪�ĉF���Ɍ����܂��B�F���ӎ��̈ꕔ����荞��ŁA�A�̂悤�ȑ��݂������̂��B���ƕ��̑��݂̊W����ψ�ȋ�Ԃɕs�ύt�����܂�F���Ɍ������^�����N����B����Ȕw�i�̒�����P�Ȃ鑶�݂��Ȃ킿���a������̂ł���B
�@�G�l���M�[�̕��z�ɓ��ƊO�ƌ����قȂ������������B�͊O�E�i��ԁj�Ɏ��͂܂�āA�Ǝ��̉^�����n�߂�B�����ɌƂ��Ă̐��E�i�g�́j�����n�߂�̂ł���B�����̂����܂ꂽ�̂��B
�C�Â��͂��̏�ɂ����āA���������̊�{�I�Ȋ��o�ł���u���E�s���v��I�ɂ���B���B�͂��́u���E�s���v�ݏo�����̂����Ȉӎ��Ƃ��ė������ė������A�C�Â��͂܂��ɂ��̈ӎ��̑��݂��Ƃ炵�o���̂ł���B
�����ɗ��Ď��B�̋c�_�͑�O���̖`���ɖ߂��ė��Ă��邱�ƂɋC�Â������낤���B
�킽���͂����ŁA�u�ӎ��͐g�̂̓������Ƃ炵�o���v�Ƃ����l�����ɖ��������邱�Ƃ��q�ׂĎ��̂悤�ɏ������B
�@�u�Ƃ炷�v�Ƃ����C���[�W�́A�Ƃ炷���̂ƏƂ炵�o�������̂Ƃ�����̗v�f���琬���Ă���B���B�͂܂��ɂ��̏�ɗ����Đg�̂ƈӎ��̊W��_�����̂ł��������A�������悭�l���Ă݂���́u�Ƃ炷�v�Ƃ����C���[�W�̒��ɂ͂���ɂ�����̗v�f���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɋC�Â��B���Ȃ킿�Ƃ炵�o���ꂽ���̂��u���Ă���ҁv�̑��݂ł���B�E�E�E�E�E�l�ԑ��݂̍��{�Ɉӎ���ݒ肵�Ȃ���A�i����Ɉӎ��Ƃ͕ʂ̑��݂�����Ƃ����j�����ݏo�����ƂɂȂ�̂��B�ƁB
���͂��̂悤�ɕ\�����Ĉӎ��ɂ��Ă̍l�@�ɓ����čs�����̂ł������B����͂Ƃ������A�������̎�������ƍl�����̂́A�C�Â��̖����܂��悭�������Ă��Ȃ���������ɊO�Ȃ�Ȃ��̂��B���́A�v�l�ƋC�Â��̖������܂��悭�w�E�����Ȃ��������߂ɁA�u���Ă���ҁv�̑��݂��͂�����ƔF�߂鎖���o���Ȃ������B
�@���������₱�́u���Ă���ҁv�Ƃ́A�ϏƎҁA���Ȃ킿�C�Â��ł������Ɨ�������̂ł���B
�Ƃ���ł��̎��Ȉӎ������܂�邱�Ƃɂ���āA�l�Ԃ͓Ǝ��̈ӎ���Ԃ����n�߂�B����͎��̌�������ԂƏd�Ȃ�̂ł���B
����Ԃ͎��o���ꂽ���E�Ƃ��Đݒ肵�����E�ł��������A�����o������Ԃ̗\���I�Ȑ��E�ƍl����A����Ԃ��o�̐��E�ɂ܂ōL���邱�Ƃ��o����B����Ǝ���ԂƂ͎��Ȉӎ��̍��o�����E�Ƃ��čl���邱�Ƃ��o����ƌ������Ƃł���B
�@����͂Ƃ������A���̎��o�Ɩ����o�̋��E�����_���̐��܂��ꏊ�ł͂Ȃ����Ǝ��͍l����̂ł���B
�@�v�l�͎����I�ɓ����Ă���B����͎��̌����������l���ł͂��邪�A����������ł͂ǂ��܂ōs���Ă��A���_�I�Ȃ��̂͐��܂�ė��Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�����I�ƌ����̂͂`����a�֕������i�ނƂ��ɁA���̂`�Ƃa�ɂ͑��݂ɂȂ�̊W�������Ȃ��ƌ������Ƃ��Ӗ�����B�����I�ȗ���ɂ͂`�͂a��F�߂�K�v���Ȃ��A�a���܂��`��F������K�v���Ȃ��̂ł���B��ɂ`�͂`�ł���A�a�͂a�ł���ƌ����Ǘ��W���������ɂ͐��藧���Ȃ��̂ł���B
�@�`����a�Ɏ���Ԃɉ�㈂����݂���ƌ����Ă��A�܂��������Ƃ�������B���Ȃ킿���ꂪ�����I�ł���ȏセ���Ɍ���Ă��鉉㈎q�͒P�ɋK���I�ȓ��������Ă��邾���ŁA�����ɜ��ӓI�Ȕ��f�������ł͂Ȃ��B�R���s���[�^�[���v�������ׂ�Ώ\�����낤�B
�@���̂悤�Ɏ����I�Ȃ��̂́A�܂��ɂ��̏u�ԏu�Ԃ��Ɨ����ė���čs���̂ł����āA��������͂��̗���̑S�̂����n���悤�ȍ\���͂ǂ��ɂ������ė��Ȃ��B�܂��Ɉłɕ�����Ă���ƌ��������Ȃ��ł��낤�B
�ł͐��_�͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂��̂��A�����܂ł��Ȃ������ɋC�Â��̑��݂��K�v�ƂȂ��Ă���̂ł���B
�@���_�������A���_�Ƃ͋C�Â��Ɨ��O�v�l�̕����̂��Ƃ������Ƃł���B
�@���_�͐��܂�Ď��ʁB�ނ���Ɗw�K�ɂ���Đ��_�͐l�ԎЉ�̒��Ŏp����čs���s�ł̂悤�Ɍ�����ꍇ�����邪�A����͂������������Ă���ɉ߂��Ȃ��B����͐��_���ɓ��݂���A���炪��ΓI�ł���Ǝv�����ތX�����痈�Ă���̂��B���_��������╶���ɂ���ĈقȂ��ė���̂́A���_�̕��Ր��ɂ������锽�ł��낤�B������ɂ��Ă��A�Â��ɂ��̐��_�I�Ȃ��̂߂�A����͎��Ƌ��ɐ��܂ꎄ�Ƌ��ɖłтčs���̂��������Ă���B
�@����͂����炭���_���̖{�̂��A���O�v�l���Ƃ������Ƃ��痈�Ă���̂��B���_�͎v�l�Ƌ��ɐ��܂�A�����ď�������B
�@�����łтȂ����̂́A�ϏƎҁ��C�Â������Ȃ̂ł���B
�@�C�Â��ɂ���āA���ɋN�����Ă���l�X�Ȏv�l�Ɍ������Ă���B���̂��Ƃɂ���ď��߂āA�l�͂��̎v�l���A���̎v�l�̒��Ɏ�荞�ނ��Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B���̂��Ƃ���������������₷����������ƁA���̂悤�Ɍ����邾�낤�B
�@�Ⴆ�Ύv�l�͐�̂悤�ɗ���Ă���B���̎v�l���`���a���b���c���d�Ƃ��������Ő��܂�Ă���Ƃ��悤�B���̂Ƃ��C�Â��ƁA���̋C�Â�����荞�ލ�p���Ȃ������Ȃ�A���̎v�l�̗���݂͌��ɊW���������ɂȂ�̕ω����N�����Ȃ��B���������I�ɓ����čs���������낤�B
�@���̍l���ł́A�C�Â��͏�ɂ���B��荞�����Ƃ�����̎v�l�̗���͏�Ɍ���̒��ɂ���Ƃ�������̂ł���B���͂��̋C�Â�����荞�ޔ\�͂����a�����邩�ƌ������ƂɂȂ邾�낤�B�@���̎�荞�ޔ\�͂Ƃ́A�F�����Ȃ킿���O�v�l�ɊO�Ȃ�Ȃ��B���O�v�l�Ƃ͓��]�ɂ��v�l���Ɗ��ɏq�ׂ����A���ǂ͓��̓����ɍs�������B���̔F�������܂�Ă���ߒ��͂��łɁi��j�Ŏ��グ�Ă���B
�@�v�l�`������Ă���Ƃ��̂`�͋C�Â��ɂ���Č������Ă���B����Ƃa�̎v�l�͂`�̉e�����āA�a�f�ɕω�����B���ɂ͓��R�b�̎v�l���a�f���邢�͂`�̉e�����Ăb�f��b�h�ɕ������n�߂�̂��B�ȉ����̂悤�ɂ��ė��O�v�l�͎������荞�݂Ȃ��玩�ȑ��B���čs���̂ł���B���̗̈�͂܂��Ɋj����̂悤�ɔ����I�ȍL��������悤�ɂȂ�B�܂��ɋ��\�̓a���ƌ�����B
�@���̂悤�ɁA�l�Ԃ͋C�Â��Ǝv�l�����̂����Ƃ�����v�l�̐��E���L���A����Ԃ����グ�čs���̂ł���B
���Đ��_�Ƃ͂��̎v�l�̗���Ɍ��o������̌X�����w���Ďg�����t���Ǝ��͍l����B
�N�w�҂͐^���ƌ����L�[���[�h���Ƃ炦�Ďv�l�̘A����������Ă�B�����w�҂͐ۗ����A�|�p�Ƃ͔����A�_�w�҂͐_������ǂ�̎��Ƃ��Ďv�l��g�ݗ��Ă�B���������`�Ŏv�l�ɂ���ǂ�̌X�������܂�ė���̂ł���B�����ɐ��_�������݂���B
���o�Ƃ͂܂�A�C�Â��Ǝv�l�̍��̂�����Ԃ������B�����Ď��o�͈ӎu�������ɂ����A���_�ݏo���B�ł��l�ԓI�ȗ̈�͂܂��ɂ��̎��o�Ɋ�Â��Ă���̂ł���B
�@
�@
�@�@�R�D�����o���g�̓I
���o�𗝉�����ƁA�����o�͂���ȂɎ�����v���Ȃ��B���̊T�v�͑O�͂ł��q�ׂĂ���ʂ�ł���B
�@������ɂ��Ă��C�Â��͌��R�Ƃ��đ��݂���B�����o�͂��̋C�Â��ɑ��Ă̔F�����܂�������Ԃ��w���̂ł���B�����������ł͊��Ɉӎ��𐢊E���番�������Ď��Ȉӎ������������Ă���B���o�ւ̏����������Ă���̂ł���B
�@�@�S�D�o�������z
�o���͎��o���o�ď��߂Ă����ɍs�������n�_�ł���B����͌����Ė��Ɠ������̂ł͂Ȃ��B�����Č����A��������Ȃ̂ɑ��Ċo���͖��肩��̖ڊo�߂Ȃ̂ł���B�����Ă��̊Ԃɂ��鎩�o�͂܂��ɖ��ƌ������ƂɂȂ邾�낤�B����͂܂��Ɏ��B���[�����肩�珙�X�ɖڊo�߂čs���ߒ��Ƃ悭���Ă���B�l�͖ڊo�߂̑O�ɂ悭��������̂ł���B
�@�o�����邽�߂ɂ́A������o�߂�K�v������B����������͂ǂ��������Ƃ��Ӗ�����̂��낤���B
�@�����ɂ��Ȃ���Ėڂ��o�߂�ƁA�����Ɍ����̎��������Ăق��Ƃ��鎖������B����Ƃ��̎��ɂƂ��āA���͉��̉��l���Ȃ����̂ƂȂ�B�����ɂ������댯�͌����瑶�݂��Ȃ������̂�m��B���͂������薲�̐��E���̂ċ���A�����̎������n�߂�̂ł���B�@���ɑ��Č����͏d�݂�����A���B�͋���Ȃ������̂Č��������B�ہA�������疲�߂�A����͂��������̂Ƃ����ʂ�Ȃ��̂��B
�@�o�����������Ƃ�������B���O�v�l�̍��o��������o�߂��Ƃ��A�����ɂ���͎̂��݂��̂��̂ł���B
�@���͊ϏƎҁ��C�Â��������݂ł���Əq�ׂ����A�l�͂܂������o�����Ď����͊ϏƎ҂ł��������ƂɋC�Â��̂ł���B
�@���̊ϏƎ҂͂��͂⌾�t�ł͕\�������Ȃ��B
�@�����ЂƂ��ꂪ�\���Ƃ������͔ے�`�ŕ\������Ƃ��݂̂ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�E�E�E�ł͂Ȃ��ƌ����Ƃ��̂݁A���̕\���͐������ƌ����邩��ł���B
�@�����Ŕے肪�d����̂͂��̂��߂ł��낤�B���Ȃ킿�ϏƎ҂͑S�\�̐_�ł���Ȃ��̂��B
���������Ď��B�́A�ϏƎ҂����͂₱��ȏ��Njy���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ϏƎ҂Ƃ͉����ƌ����₢�͗��Ă邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ł���B�t�ɂ���͉����Ɩ₤�����������A���̎҂͂��܂��Ɏ��o�̐��E�ɗ����Ă���Ƃ������ƂȂ�̂ł���B
�@�_�ɂ���Ď��B������ė�����̂͂����܂łł���B�����Ă��������͐[���R�ƂȂ��Ă���B�o���̗̈�͂��̊R�̌������ɂ���B��̐��E�͊��S�ɕ�������Ă���̂��B
�@���B�ɂ͂����Ɏ��邽�߂́A�����Ȃ鋴���˂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł����āA�o���Ɏ��邽�߂ɂ́A���ǂ��������щz���邵���Ȃ��B���z���邱�Ƃ����A�o���Ɏ��邽����̓��Ȃ̂ł���B
�@���z�͋C�Â��Ǝv�l����������������n�߂���B���̖����̍\���𗝉����āA���Ӑ[�����̂��̔F������C�Â����������o���A���̋C�Â��ɐg���ڂ����Ƃł���B
�@���z�Ƃ͂��̋C�Â����̂��̂ɓ����čs�����Ƃ��Ӗ�����B���Ƃ������\���Ȃ킿�v�l�̐��E���璵�āA�C�Â����ϏƎ҂ƂȂ邱�ƁA���ꂪ�o���ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�ϏƎ҂Ƃ��Ď��߂�Ƃ��A���܂ŋ^�������Ȃ��������ƌ������݂͂܂�Ŗ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B���Ȃǂƌ������̂͂ǂ��ɂ����݂��Ȃ������̂ł���B
�@�����ɂ���͎̂��ł͂Ȃ��A�����L��̂܂܂̐l�Ԃ������ɐ����Ă���̂��B���Ƃ����̂́A���̑f�̂܂܂̐l�ԑ��݂ɔ킹���S�����̂悤�Ȃ��̂ł���A���R�ɔ�������\�͂�c�ߐ������铭���������Ȃ������������Ă���B����������͋C�Â��Ǝv�l�̍��o�������������̂ł���B
�@���̐��̒��ōł����l�̂�����̂́A�L��̂܂܂̎p�ł���B���B���^��������̂́A�S�̒�ɂ��̎v��������ł��邩��ɊO�Ȃ�Ȃ��B�����ɂ͍ł��������ɂ���v�z������B�v�z�ƌ������A���ꂱ�������R�̐��ƂȂ̂ł���
�@�Ƃ���Ŏ��B�͊o���Ǝ��o�̋��E�ɂ���v�l�Ƃ��āA�@���I�Ȏv�l�ƌ|�p�I�Ȏv�l�����グ���B
�@�@���͐_�Ƃ����T�O�𗘗p���āA���邢�͂����łȂ��Ƃ��_���I�ɔފ݂𗝉����Ă����ɔ�шڂ낤�Ƃ���B�����ɂ͋C�Â��Ǝv�l�̖������ɂ߂Č������ԓx�Œf���낤�Ƃ���B����ΐ��_�̎��E�����݂���̂��ƍl������B
�@����|�p�́A�l�Ԃ̎��R�ɔ�������\�͂�ʂ��Ĕފ݂Ɏ��낤�Ƃ���B
�@��ɏq�ׂ��悤�ɁA�o���������̂��ڂɂ���̂́A���ׂĂ��L��̂܂܂ɐ����鐢�E�ł���B
�@���\�͂ȂǂƂ����l�����͎v�l�̂����c�t�ȕ��ނɓ��邪�A���̒��\�͂Ȃ�͂����݂���ƁA�l�X�ɐM��������悤�ȏ����͊m���ɂ���B�����܂ł��Ȃ�����͖{���̗͂����߂Ă��܂������̑��݂ɊO�Ȃ�Ȃ��B������{���̔\�͂�������ꂽ�Ƃ��A������������l�X�ɂƂ��ẮA���ꂪ���\�͂Ɍ�����ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�|�p�Ƃ͂���������ɒu��������B���Ȃ킿������ʂ��Ď����̉\�����ő���ɒT���čs���B�����ɐ^�̈Ӗ��̌|�p������Ǝ��͍l����̂ł���B
�@�|�p�Ƃ����A��_���v�l�ɂ���āA�����̉\����T������Ƃ������Ƃ́A����F�߂Ȃ���A���̎��̒��ɐ^�������߂悤�Ƃ���ԓx�ł���B����͂���Ӗ��Ńu���[�L�������Ȃ�����݂ɔ����čs���悤�Ȃ��̂ł��邪�A�@���̂悤�ɐ��_�̎��E����������悤�Ȍ��������ł͂Ȃ��B
�@�����͒������A�������K�^�ɂ��A���̓��ɂ���Ď��g�̋Ɍ��ɂ��ǂ蒅�����҂́A�����ɖ{���̎����̎p�����A���݂ɋC�Â����Ƃ��o����̂ł���B�����Ől�͐^���̐��E�ɓ���B
�@�|�p���Ǝ�������ꐫ���d�A�����̂��̂ɒǐ����邱�Ƃ����߂�̂͂����ɖ{���̗��R������Ǝ��͎v���B�@
�@�o���Ɏ��邽�߂ɂ́A�_���I�ȗ����͂��܂���ɗ����Ȃ��B�_���Ŕ�����̐�͕K���s���~�܂�ɂȂ����R�������B���̐�͏@���I���K�v�ɂȂ�B
�@�����������͎��݂̑̌��ɊO�Ȃ�Ȃ��B���̑̌��͘_���ʼn��߂������Ȃ������͂܂��Ɏ��݂��̂��̂Ȃ̂ł���B����͊o���̒��ɂ����݂���B����Ӗ��Ŋ����͎��ɂ���Ęc�߂��Ȃ�����A����͗L��̂܂܂̐l�ԑ��݂��f���Ă���̂ł���B
�@��Ɋo���Ɏ��铹�ɂ͋����Ȃ��Ə������̂́A�����܂ł��Ȃ��_���ɂ�铹�ł����āA�����̐��E�͂܂��ɗ������Ȃ̂ł���B�����ɋ��Ȃǂ͕K�v���Ȃ��̂ł���B
�@�o���Ɏ��邱�̓�̓��݂͌��ɑ������钷���ƒZ���������Ă���B����Ȃ���̓���g���邱�Ƃɂ���ĕ₢�����Ȃ��炢���炩�ł��e�ՂɊo�����邩������Ȃ��B���������͂����ŕ��@�_�ɂ͗����������͂Ȃ��B
�@�o�������ӎ��͂��͂⊮�S�ɘ_���v�l�𗎂Ƃ��Ă���B�����ɍL����͖̂v�_���v�l�ł���B���͂₱���ł͋C�Â����v�l�Ɩ�������悤�Ȃ��Ƃ͖����B����͖����ł͂Ȃ��A������ɂȂ�̂ł���B�v�_���v�l�͓����v�l�ƌ������t���g���Ă��邪�A����͊��S�Ɏ����̈�����v�l���w���Ă���B����͌���ΊϏƎ҂��̂��̂̎v�l�ł���B�ϏƎ҂̖��ł͂Ȃ��A�ϏƎ҂̌����I�Ȏv�l���Ƃ�������B������ɂ��Ă��C�Â��́A�v�_���v�l���̂��̂ƂȂ�̂ł���B�����ɂ͂��͂��Y�ݏo���悤�ȁA���������̂��̂͑��݂��Ȃ��B�����Ă܂���Ȃ���̂��������āA�������݂̒��ɓ���̂ł���B�@
��O�́@�ϏƎ�
��P�߁@�����̎v�l�ƊϏƎ�
�@�Ō�Ɏ��͊ϏƎ҂ɂ��āA�G�ꂽ���B���_�ϏƎ҂ɂ��Ē��ژ_���ɂ������͏o���Ȃ��̂ł��邪��̂��Ă�Ă�n�F���_�Ɩ��ł��Đi�߂ė����c�_�̒��߂�����Ƃ��āA�����Ă��̖��ɂ��Č��Ă��������̂ł���B
�ϏƎ҂Ƃ͉����ƌ����₢�͗��Ă��Ȃ��ƁA���͐�ɏq�ׂ����A����͎��B���g���_���ɂ����Ăł����āA�_���̌`���Ⴆ����͂܂��ʖ��ƂȂ��Ă���B
�@�܂�A�������Łu���B���g���_���v�ƌ����Ƃ��A�����ňӖ����Ă���͎̂��Ƃ�����̂̌Œ肳�ꂽ�_���ƌ������Ƃł���B
�@�Ƃ��낪���B���̂��Ă�Ă�n�F���Ɩ��t�������E�́A�F����̂��X�P�[���̌n���ɕϓ����邱�Ƃŕ`���o�����F���ł������B
���Ȃ킿�����ɂ���_���́A��̂��Œ肳�ꂸ�A�t�Ɏ�̂̕ω��ɂ���ē�������̂ł���B
�ȒP�Ɍ����ƁA��̂��Œ肵�āA���E���L�q����_���ɑ��āA��̂�ϓ����邱�Ƃɂ���Đ��E���L�q����_�������B�̍��o�����̂��Ă�Ă�n�F���������̂ł���B���̘_���ŊϏƎ҂߂��Ƃ��A�C�Â��̖�肪���̓I�ɗ����o����悤�Ɏv���̂ł���B
�@���B�͂����ŁA��ꕔ�Ŏ��グ���̂��Ă�Ă�n�F���̊T�_�ɍĂѓ����čs�����ƂɂȂ�B���_�����ŁA���̉F���̍\�����J��Ԃ���Ƃ�͂Ȃ����A���̃X�P�[���̎����������T�����̐��E��O���ɂ����Ȃ���c�_��i�߂čs�����Ƃɂ��悤�B
�@�̂��Ă�Ă�n�F���̃X�P�[���̎��߂��Ƃ��A���B�̐��E�ł���q�g�̏�𒆐S�ɁA�ɑ�Ɍ������X�P�[���̏�ɂ͐_�l�����݂��A�ɏ��Ɍ������X�P�[���̏�ɂ͑f�l�i���ƂЂƁj�����݂����B�����ăX�P�[���̊e��ɂ����ẮA���ꂼ��̏Z�l�������F����̂Ƃ��Đ��E���F���̏�����グ�Ă���̂ł������B
�@�܂�X�P�[���̈ړ�����߂Ĉ�̏�ɌŒ肵�Đ��E�߂�Ȃ�A����͍��܂��Ɏ��B�����ǂ��ė����_�������藧���ƂɂȂ�B����͂ǂ̃X�P�[���̏�ɂ����Ă��������Ƃ�������ł��낤�B�F����̂��Œ肷��ƁA�Ƃ���ɓ����_�����A�f�l�̏�ł��q�g�̏�ł����邢�͐_�l�̏�ł��A�����ɐ��藧���Č݂��ɍs���������Ƃ͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ��̂��Œ肷��ƁA�����ɑ��đ傫��������̂�������������̂��A�ǂ���������悤�ɔF�����邱�Ƃ��o���Ȃ�����ł���B�F����̂��Ȃ킿��������������ȏ�A�����ɐ��܂��_���͊ϏƎ҂��z���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ��낪���̎�̂��X�P�[���̌n�ɉ����Ď��R�ɕω�������Ȃ�A����͕ς���Ă���B�����ɂ̂��Ă�Ă�n�F���̑傫��������̂��B
���Ă��̊e�X�P�[���̏�ɌJ��L������_���������ɗႦ��ƁA�̂��Ă�Ă�n�F���̃X�P�[�����ɂ������v�l�͏c���ł����āA�܂��ɁA�����ɉ����Əc���̐D�萬���v�l���E���������邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�o���ɂ���Ď��B�͂܂��ɂ��̎����̂��̂𗎂Ƃ��B���Ƃ͌����܂ł��Ȃ��F����̂��̂��̂ł��邱�Ƃɒ��ӂ�������ƁA���B�͂��͂�ȒP�ɏc���̎v�l����ɓ���邱�Ƃ��o����͂��ł���B
�@�Ȃ��Ȃ炱�̎v�l�͋q�̂���_�ɐ����āA���̒�����̂����R�ɃX�P�[�����ړ����Ȃ���i�߂���B���̎v�l�����������邽�߂ɂ͌Œ肳�ꂽ��̂�p���Ď��R��^���鎖�Ȃ̂ł���B���̂��Ƃ͎�̂��������ꂽ�҂ɂƂ��āA���Ƃ��ȒP�Ȃ��Ƃł��낤�B
�@���Ă��̊ϏƎ҂͉����̎v�l�ł͂��͂�_���̊O�ɂ��鑶�݂Ƃ��������Ȃ��������A�c���v�l�ɂ����Ă͏�������ς���Ă���B
�O�u���������Ȃ�߂������A�����ŏc���v�l�ɂ��L�q�����݂Ă݂����B�����Ƃ��A�̂��Ă�Ă�n�F���̍\�����������͂��܂������v������̂ł͂Ȃ��B�ϏƎ҂͂��̏d�w�I�ɍL����F�������ӎ����̂��̂ł���Ƃ�������ōςނ���ł���B�F���ɂ�����ӎ��݂̍���͊��ɑ�ꕔ�ŏq�ׂ��ʂ�Ȃ̂ł���B
�@�ϏƎ҂��������z�������݂ł���ƌ����_���́A���̊ϏƎ҂��̂��̂��Œ肳�ꂽ��̂̎��삩�瓦��čs���ׂł��������A��̂�ω������邱�ƂŎ��B�͂ǂ��܂ł��̊ϏƎ҂�ǂ��čs���邾�낤���B���̋����͂����ɂ���B
�@���B�l�Ԃ̒H�������_���̓��́A���Ƃ��Ă̖��肩��A���o�Ƃ��������o�Ċo������B���Ȃ킿�ϏƎ҂Ƃ������݂ɋC�Â����ł������B���͊ϏƎ҂��̂��̂ɂȂ邱�Ƃɂ���Ď��炪�F���ӎ��ł��邱�ƂɋC�Â��B����Ƃ��̈ӎ���_�l�̎����Ō���Ȃ�܂��ɂ���͐_�l�̓����A���Ȃ킿���Ȉӎ��ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�����o�����ĊϏƎ҂ƂȂ蓾���Ƃ��A���͂��̂Ƃ��_�l�̎��Ȉӎ��ƈ�ɂȂ��Ă��鎖�ɂȂ�̂ł���B���_�����ŕX�㎄�ƌ������t���g���Ă���̂́A�ϏƎ҂��Ӗ�����B
�@���B�͊o����B�������ď��߂āA���B�ɂ͔F���s�\�Ȑ_�l�̎����Ɏ���̂��B���͂��̂Ƃ��_�l�Ƃ��Đ����n�߂�B�q�g�̏�ɂ�����g�̂͂₪�Ėłщ�̂��邪�A�������o�����A���̐��Ɏ����o���������C�Â��͂₪�Đ_�l�̑Γ����Ƃ炵�n�߂�B
�@���B�̐l�����T�O�N�Ƃ���ƁA�_�l�͂��̂P�O22�{�̎��Ԃ������ďn������B���_�A��̂̂Ȃ����ɂ͊��Ɏ��Ԃ̊ϔO���������Ă����ł��邩��A���͂����_�l�̑̓����Ƃ炷�C�Â��Ƃ��đ��݂�������̂ł���B�@
�_�l���܂��o���Ɏ����Y���o�āA���̎��A���Ȃ킿�ϏƎ҂ɋC�Â��悤�ɂȂ邾�낤�B���̂��Ƃɂ���Ď����ϏƎ҂͐_�l�̎��Ȉӎ�������������A�_�l����މF���ӎ��̂Ȃ��ɗn������ōs���̂ł���B
�@�_�l�̊o���ɂ���Ĉӎ��͂���Ɏ������z����B�����Ă����͌����܂ł��Ȃ����̐_�l�̑̓��Ƃ��Ă���A�ϏƎ҂͑��̐_�l�̎��Ȉӎ��ƂȂ�̂ł���B
�@�ϏƎ҂͂������āA����Ȃ��ӎ������߂čs���̂ł���B���̍\�}�͂̂��Ă�Ă�n�F���̍\��������ɐ������s������Ă���B
�@�ϏƎ҂̑��݂����ʂ̕����ɖڂ�]����ƁA�����ɂ͑f�l�����݂���B���̎��Ȉӎ��͑f�l��ʂ蔲���ė����ϏƎ҂ɊO�Ȃ�Ȃ����낤�B�������ĊϏƎ҂͖����ɏ����Ȑ��E�ɓ��荞��ōs���̂ł���B
�@���ǂ̂Ƃ���ϏƎ҂̓X�P�[���̌n���ɍL�����čs�����݂ł���B�����Ă��̗��[�͖����̂��Ȃ��ɖ��v���Ă���B�����Ă������c���̎v�l�ɂ����E�_���Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@�_���ɖ����������̂́A�F����̂����݂��邩��ɑ���Ȃ����A���Ƃ���̂�ω��������Ƃ��Ă��A����͎�̂ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��̂ł���B���Ȃ킿�c���v�l�ɂ���Ă��A�ϏƎ҂͕߂炦�邱�Ƃ��o���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���̂��B �@
�_�����̂���̂Ȃ��ɂ͐��藧���Ȃ����\�ł���ȏ�A���B�͂����Ȃ�_���`���������Ă��Ă��ϏƎ҂��L�q���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B
�@���ہA�ϏƎ҂͘_���ł͂Ȃ��̌��ł���B���B�͈�̎v�l�𗣂�ϏƎ҂Ƃ��Ă̑̌��̒��ɓ����čs���Ȃ�A���̑̌���ʂ��āA�v�l�ł͌����čs�����Ȃ������̂��Ȃ��ɗ����ɂȂ�̂��B
�ϏƎ҂ɂ͎��Ԃ��傫���������ďꏊ�������Ȃ��B���R�A�`�������Ƃ��Ȃ��A����͂������̏u�Ԃ�S��Ƃ��đ��݂��Ă���B
�ϏƎ҂Ƃ��đ��݂���Ƃ��A�̂��Ă�Ă�n�F���ȂǂƂ������̂͂����̏����Ȗ��ɉ߂��Ȃ��B
�@�����Ď��B�͂��̊ϏƎ҂ɂȂ蓾��B�ہA���B�͏��߂��炱�̊ϏƎ҈ȊO�̉��҂ł��Ȃ��B���B�͐��܂��O���炱�̊ϏƎ҂������̂ł���B
�@�����K�v�Ȃ��Ƃ͂��̂��ƂɋC�Â������Ȃ̂ł���B
��Q�߁@�ϏƎ҂ƎЉ�
�P�D�ϏƎ҂Ƒ��Ҙ_�@
�@���B�͊o���Ƃ͂ǂ��������̂��ƌ����������B���_������ƌ����Ď��B���o���̒��ɂ��邩�ǂ����͕ʖ��ł���B
�@���t�łǂ̂悤�ɗ������悤�ƁA�ϏƎ҂Ƃ��Ă̎��������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��͉̂��x���J��Ԃ��q�ׂė����ʂ�Ȃ̂ł���B
�@�ϏƎ҂͌��t�ł͂Ȃ��A�C�Â��Ƃ��Ă̑̌����̂��̂Ȃ̂ł���B�������ϏƎ҂ɂ܂ŏ�������ɂ͒m���͉��̖��ɂ������Ȃ��B�ނ��낻��͏�Q�ɂȂ�B�������Ȃ��玄�B�͈���Ō��t�ɂ��`�B��i���D�ꂽ���̂������Ȃ��̂ł���ȏ�A���̏�Q���o��Ō��t���g�����Ȃ��̂ł���B
�@���閺�������w�Z����ƂɋA���āA�K�����Ă̗�������낤�Ƒ䏊�ɗ��������A�ޗ�������Ȃ�����o���Ȃ��ƌ����ė����B�ޗ��͔������낦������Ȃ̂ł��������Ǝv���A�悭�����ƁA�Ȃ��̂͌v�ʃJ�b�v���ƌ����̂��킩�����B
�@����̓W���[�N�����A�v�ʃJ�b�v�͗����̒P�Ȃ铹��ɉ߂��Ȃ��̂ɁA�ޏ��̓J�b�v��K�{�̂��̂Ǝv�����ݗ����̖{�����������Ȃ������̂ł���B
�@���t�͂���ȏ�Ɏ��B�̖ڂ�����܂��B���t�͊w�K�ɂ���ē����邪�A���̌��t�́A����͉����ƌ����₢�����ɑ��铚���Ƃ��ė^�����邽�߂ɁA���B�͎q���̎��ォ��A���t����������ׂĂ𗝉������Ǝv�����ތX����A���t�����Ă���̂��B�u���v�������t���Ȃ���Εs���ɂȂ邪�A�t�Ɍ��t���^��������ꂾ���ň��S���Ă��܂��B�{���͕������Ă��Ȃ��Ă��A���������C�ɂȂ��Ă��܂����̂��B
�@�Ƃ��낪�A���⎄�̗����Ă��鏊�͎��؎�`�I�ȋc�_�̔j�]���������Ȃ̂ł���B���t�ɏd�݂��������邱�Ƃ͂��͂�o���Ȃ��̂��B���B�́A���t�̌������ɂ���^���ɖڂ����������邵���Ȃ��̂ł���B
�O�u���͂��ꂭ�炢�ɂ��āA�ϏƎ҂��ʂ����Љ�I�ȈӖ������Ă��������B�����Ŏ��B�͑�Q���̑��Ҙ_�ɂ�����x�����čs���B
�@���Ҙ_�ł́A���҂Ƒ��l�ƌ�����ʂ������B���Ȃ킿����Ԃɐ��ݏo�������̂����҂ł���A���l�Ƃ͌���ԂɎ��݂���l�ԑ��݂��̂��̂��w�����̂ł���B
�@����Ԃɂ����鑼�҂�A�Љ�́A���̔��f�ɉ߂��Ȃ������B�����A����Ԃɂ͖��炩�ɑ��l�����݂��Љ������Ă��邪�A���B�͂��̌���Ԃł̑��l�ڒm�邱�Ƃ͏o���Ȃ������̂ł���B�܂莄�B�͎��݂Ƃ��Ă̑��l���A���̂Ƃ͉��������҂Ƃ��Ď���Ԃ̒��Ŕc�����鑼�Ȃ������̂ł���B
�@���������Ď��B�̐S�͊e���̒��Ŋ��S�ɌǗ����Ă����B���̎���ɂ͂�������̑��l�����݂��Ă��邪�A���͂��̒��̒N��l�Ƃ��Ė{���ɒm��ƌ������Ƃ��Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���̎����ϏƎ҂Ƃ��Ă̊o���ɒB�����Ƃ��A�����Ƃ��̌������͕ς���Ă���̂ł���B�ł͂��̎����́A���l�Ƃǂ̂悤�ɂ�����邱�Ƃ��o���邾�낤���B
�@�ϏƎ҂ɂ͂��͂�F����̂��鎄�͑��݂��Ȃ��B����Ƃ��͂₻�̎��_�Ŏ��̒��ɂ͎���Ԃ͑��݂��Ȃ��Ȃ�B�܂莄��������̂Ɠ����ɑ��ҏ����Ă��܂��̂ł���B���͂�ϏƎ҂��鎄�̑O�ɂ́A��̋��\�͑��݂��Ȃ��̂��B
�₪�Ď��͌���Ԃ̒��ɂ���̂�m��B�����ł͂��͂⎄�́A�����Ƒ��l�Ƃ̋�ʂ�����鎖�͏o���Ȃ��B�ނ��낻��ȕK�v�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ł���B�����ɂ͂�����̐��E�����O���Ă���B
�@�����Ă��̒��ɂ����āA���͎�������芪�����R�Ƒ��l�ƁA�����Ă������̑��݂Ƃ̊��S�Ȓ��a�̒��ɂ��邱�Ƃ�m�邾�낤�B���Ƃ����l���烀�`�ł���悤�Ƃ��A�����ɒ��a������̂�m��̂ł���B�L���X�g���E�̖j��ł��ꂽ�獶�̖j���o���Ȃ����ƌ����̂͂��̂��Ƃ������Ă���Ǝ��͗�������B
�ϏƎ҂ɂƂ��āA���̐��ɑ��݂����̂��̂͒��a���Ă���̂��B�����͂���ׂ����đ��݂��Ă���B�P�������A�����X���A���邪�܂܂̂��̂Ƃ��đ��݂��Ă���̂ł���B
�����̒��ɂ���l�X�͉萶����O�̎�q�̂悤�Ȃ��̂ł���B�l�ԂɂƂ��Ă̈����ł�����n�ɐA����ꂽ��q�ɉ߂��Ȃ��B�������͉̂����Ȃ��B���ׂĂ͑厩�R�̒��Œ��a���Ă���B��q�͂����ڂ��o���̂ł���B
�@���ɂ͖ڂ��o�����ɕ����čs�����̂����邾�낤�B��������������q�͑�n�ɋA���Ă܂��V���Ȏ�q�ݏo���B�������Đ��E�͉��X�Ƒ����čs���̂ł���B
�@�l�ԂƂ����ǂ��A���̎��R�̒��̎�q�ȏ�ł��邱�Ƃ͂Ȃ��B�܂�l�͂��̂܂܂Ŋ��Ɏ��R�ƒ��a���Ă���̂��B�����ė�O�Ȃ����ׂĂ̂��͈̂�̐����̒��Ő����Ă���̂ł���B
�@�ϏƎ҂͂܂��ɂ��̂悤�ɐ��E������B�e�a���P�l�����l���Ƃ��ɋ~����ƌ����̂����̂��Ƃ��痈�Ă���̂ł���B
�q�b�g���[�ł������a�������R�̈ꕔ�ł���B���Ƃ������͔j��҂Ƃ��Ă��邢�͕a���ۂƂ��ē����B����A�ϏƎ҂͎�q�ɐ������B��������݁A��тݏo�����Ɠ����B�������ǂ���ɂ��Ă������̐��E�ɕK�v�����瑶�݂��Ă���̂��B
�@���t�������Ƃ炦�Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̗��ɉB��Ă���^�������Ȃ���Η����͉��̂��Ă��܂����낤�B���͍��A�C�Â��Ƃ��ē������݂�\�����悤�Ƃ��Ă���̂��B
�ϏƎ҂͐��E�ɕs�K�v�Ȃ��͉̂��ЂƂȂ����Ƃ�m��B�ǂ�Ȃɐl�Ԃ���O���킵�悤���A�߉ނ̎�̂Ђ�̑����̂悤�ɂ���͏�Ɏ��R�̒��ɂ���B�ϏƎ҂͂��̂悤�ɐ��E������B���̐S�͐Â��ł���A����𗐂����͉̂����Ȃ��B
�@�����o�����Ȃ��l�Ԃ������������Ă��̖��ɖ�炳��Ă���̂ł���B�낤���Љ�����o���A���ꂪ���ɂ����͂��Ȃ����ƋC�����ށB�������J��Ԃ��B�������������̂Ȃlj����Ȃ��̂��B
�@��q���ڂ��o�����߂ɂ͊k�͊���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ͂��̋T�������ĕs���������Ă��邾���Ȃ̂��B�������t�ɍL���A�o������Ȃ�����͏[�������y�����L�����Ă���̂ɁA�l�Ԃ͏����Ȗڐ�̂��Ƃ����ڂɂ��Ȃ��ň�������������B���̒��Ŏ����̉A�ɋ����A�Ӗ����Ȃ��\�͂Ƌ��s���J��Ԃ��B
���邢�͈������߁A�����̂������B���������͂��ł������ɖ����Ă���B����͋��߂�K�v���Ȃ��B���B�͈��̒��ɂ���B����ɋC�Â���������Έ��͎̂Ă邱�Ƃ����ł��Ȃ����R�̐ۗ��ł���̂�m��B����قLj��͐��E�ɏ[�����Ă���B�L���X�g�͐_�͈��Ȃ�ƌ����̂͂��̂��Ƃ��Ӗ����Ă���Ǝ��͎v���̂��B�ϏƎ҂͈����̂��̂Ȃ̂ł���B�@
�܂��l�Ԃ̋��߂�K���͎v�l��̖����ɉ߂��Ȃ��B���A�n�ʂ▼�_�邱�ƁA�K���ȉƒ�A�K���Ȑg���A�����������̂͂��ׂĎv�l�̖����ɉ߂��Ȃ��B�v�l�̋��߂閞���͈�u�̂����ɏ����Ă��܂��B��R���Ō��ė�����A�̋�Y�͂��̂��Ƃ��ؖ����Ă���ƌ����邾�낤�B��������\���������Ă�����̂͂��ׂĖ��̕����Ȃ̂ł���B
�@�����A�^���͂��܂ł������邱�Ƃ��Ȃ��B�v�l���z���Ċo���������̂͂��̐^���̒��ɓ���̂ł���B�����ɂ͎���������B����͌����ď����邱�Ƃ̂Ȃ����݂̎����݊����̂��̂Ȃ̂ł���B�@�V�q�͖����R�Ƃ������t���g���B���̌��t�͐l�Ԃ݂̍�����ӎ����Ȃ���^����\���������ɓK�Ȍ��t���Ǝ��͎v���B
�@���ׂƂ͉������Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���ׂƂ͎��ۂ̍s�ׂł͂Ȃ��A�v�l���~����Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B���͎v�l���s�ׂƂƂ炦�����A�܂��ɂ��̍s�ׂ��~�߂邱�ƂȂ̂ł���B
�@����Ɛl�Ԃ͎��R�ɗ����Ԃ�B���ׂƂ͉������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ނ��낻������l�Ԃ̎��R�̂܂܂̍s�ׂ��n�܂�B�l�Ԃ̍s�ׂ͎��R�ɐ��܂��̂ł���B���̍s�ׂɂ͎����������Ă��邾�낤�B�Ȃ��Ȃ炻���ł́A��̗}�����������ꂽ�A�L�т₩�ŗL��̂܂܂̐l�ԂƂ��Ă�����肾����ł���B
�@�F���ɑ��݂��邷�ׂĂ̂��̂́A���̈�������Ɍ������Ă���B���̑̂����S�ł���Ƃ��A���̑̂̑S�Ă̍זE�͉��̍l�����Ȃ����R�ɋN����s�ׂ̒��Ő����Ă���B�S�Ă̍זE�������R�̒��Ő�����Ƃ��A���̐g�̂͌��S�ɓ������낤�B�S�Ă͏���ɑ��݂��Ă���̂ł͂Ȃ����݂Ɋ֘A�������Ă���̂ł���B
�@�l�ԎЉ���܂����̂悤�Ɍ���ׂ��ł���B�l�X�Ɋo�����N����ΎЉ�͎��R�Ɏ��܂��čs���B�����ɕ��@�ȂǕK�v���Ȃ��̂ł���B�܂��ɘV�q�͂��̂��Ƃ�����Ă���B
�@�ϏƎ҂ɂ͎������݂��Ȃ��B����͉��x���q�ׂė������Ƃ����A�������݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͓����ɑ��҂��Ȃ��ƌ������Ƃł���B����Ԃɂ͊ϏƎ҂Ƃ��Ă̎��Ƒ��l�����݂��邪�A����͂������݂��邾���ŁA�����̋�ʂȂNJ��ɂȂ��̂ł���B
�@���́A�l�Ԃ͌I�ȑ��݂ł����āA�����đ��l�Ƃ̐S�̋��L�͏o���Ȃ��Əq�ׂė������A�ϏƎ҂ɂ����Ă͐S�̑傢�Ȃ鋤�L���n�܂�̂ł���B�ł���ƌ����l�����̂��̂����ɖ����ł������Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@�������܂��A�l�Ԃ͂��������Ă���̂ł͂Ȃ��B����͂܂��ɖڊo�߂Ɍ��������R�ȗ���̒��ɂ���̂��Ǝ��͍l����̂ł���B�l�͂₪�Ėڊo�߂�B��Y�͖ڊo�߂̑O�̐��Ȃ̂ł���B
�@�{�_�̎n�߂Ɏv�l�̗��j���������A�����Ɏ����čĂшӖ��������Ă���B���Ȃ킿�l�ނ��o�������Ƃ��A���B�͂����ɑ傢�Ȃ��̐_�ݏo���̂ł���B���B�̗���čs����͂܂��ɂ����ɂȂ����Ă���ƍl������̂ł���B
�Q�D�ϊv
���ݎЉ�͔ɉh���ɂ߂Ă���悤�Ɍ�����B���̗��͎��؎�`�̉��Ŗڊo�܂����i���𐋂��A�s�s�͓y���������Ȃ��قǍ\�����ɂ���ĕ����A�ȕւȐ�����Ԃ��������Ă���B
���̐�����Ԃł́A�y�͂܂�ʼn������̂̂悤�ɍl�����A��e�͓y�̏�𗇑��ŕ����q�����Ƃ��߂���ł���B�x�O�̓c���͂ǂ�ǂ��n������Z��ƃA�X�t�A���g�ŕ����A���̖ʐς͔N���ɍL�����Ă���B���B�̌ւ镶���Љ�́A���⎩���̑��������Y��Ă��܂��悤�ȍ��������Љ��z�����Ƃ��Ă���̂��B
�@���̂Ȃ��l�H�����D�݁A�Ђ�����ȕւ��ƕx�݂����߂�B���������؎�`�̉��ł͐S�͈炽�Ȃ��B�n�����܂܂̐S��������x�͕��~���o�邱�Ƃ��Ȃ��̂ł���B
�@���̂��߂Ɏ��R�͉s�\�Ȃ܂łɒɂߕt������B�l�Ԃ̗͂��܂���������������ɂ́A�l�Ԃ̋��s�����R�̎���͈͂ɂ��������A���⎩�R�͒n���K�͂ł��̗ՊE�_�ɒB���Ă���B�l�Ԃ͂��ꂩ�����ǂ������čs���̂��낤���B
�@���R�͂��ꂩ�����A�����炭���̌��킸�Â��ɑ��݂������邾�낤�B�l�Ԃɂ���Ēn���͔j��悤�Ƃ��A���R�͉������Ȃ������悤�ɂ��葱���邾�낤�B�����Đl�Ԃ����������Ŏ���̎��^�Ȃōi�߂Ȃ��玀��ōs���B���̉\���͌��R�Ƃ��Ă���̂ł���B
����ɂ��Ă��A�l�Ԃ����R��ɂߕt����Ȃǂƍl���邱�Ƃ����ɊԈ���Ă���B�l�Ԃ����R��ɂߕt���邱�ƂȂǏo������̂ł͂Ȃ��̂ł���B�R�����A��������A��C����������B�n���̔얋�ł���I�]���w�̔j��ɂ��Ă��A����͎��R�̔j��Ȃǂł͌����ĂȂ��B�j��Ă���̂͐l�Ԏ��g�Ȃ̂ł���B
�@���͔�����g���Ă���̂ł͂Ȃ��B�����^���݂̂����̂܂܌���Ă���̂��B
�@����ɋC�Â����ꕔ�̐l�X���玩�R�ی�̉^���⌴�q�͐ݔ��Ȃǂ̐ݒu�ɑ��锽�Ή^���͋N�����Ă���B���������Ɍ��킹������̉^�����o���̉��ɍs��Ȃ���Γk�ɎЉ���ْ������邾���ŁA�債���͂ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B�ғːi����@�֎Ԃ̊��𐆂��Ȃ���u���[�L��������悤�Ȃ��̂ł����Ȃ��B
�ł͊��𐆂��Ă���̂͒N�Ȃ̂��B����͕�����Ȃ����B���g�Ȃ̂��B���B�̌�����~�]���Ђ�����@�֎Ԃ̊��𐆂��Ă���B
���������ƑP�ǂȎЉ�^���Ƃ͋C���������邩������Ȃ��B�����Č������낤�B���𐆂��Ă���͕̂�����Ȃ����{�Ƃł���ƁB�ނ�͎���̗~�]�̂��߂Ɏ��R��j�Čڂ݂Ȃ��̂��ƁB
�@�m���Ɍ��ݎЉ�����̂܂܂ɂƂ炦�����́A���̒ʂ肾�ƌ����Ȃ����Ȃ����낤�B�������^���͈Ⴄ�B�@�֎Ԃ̐擪�ɗ����Ă���̂͊m���Ɏ��{�Ƃł͂���B���A���������̎��{�Ƃ����o���Ă���͎̂��B�̗~�]�Ȃ̂��B���{�Ƃ͎��B�̗~�]���z���グ�đ傫���Ȃ�B�������������̂悤�ȋ���ȗ͂�~���A�n���̎�����H�����ɂ��Ă���B���̋���ȗ~�]�����o���ϑz�́A�����������Ђ̂悤�Ɏ���̐����݂ɂ���Ȃ���A�������A���ꂽ��т�ǂ����ߑ�����̂ł���B���̋��\�̋�Ԃɖ����Ă������A���B�͈�l�Ɏ��R�ɑ��ē��߂ƌ���˂Ȃ�܂��B
�����ɋ��~�Ȑl�Ԃł����Ă��A���B�̗~�]���ނ������Ȃ���A�ǂ����Ĉ�l�ŃI�]���w���j��o���悤�B��l�̐l�Ԃ̗͍͂����m��Ă���B����͂܂��ɂ��̎��R�Ƌ����o����悤�ɍ���Ă���̂ł���B
�@���̔������̎Љ����߁A�l�ނ����R�Ƌ��ɐ�����Љ�ւƉ��v�o������̂͋����������{�ł͂Ȃ��B�D�ꂽ��̎w���҂ł��Ȃ��B���͂₻�̂悤�Ȉꕔ�̂�����͂ɂ���Ă��̎Љ�̗���͎~�߂��Ȃ����낤�B�����ŕ֗��ŖL���Ȋ��́A���B�ɂƂ��Ă��܂�ɂ����f�I�Ŗ���I�Ȃ̂ł���B
�@�������ϏƎ҂͈�u�ɂ��Ă��̋��s�ɋC�Â��B�����͎���C�Â����Ƃɂ���ď��߂Ď��܂�̂ł���B
�@���B������ϏƎ҂ł��邱�ƂɋC�Â����Ƃ��A�s�K�v�ȗ~�]�͋�Y�Ƌ��ɏ�������B�������Ȃ��Ă��A�����ɂȂ�Ȃ��Ă��A�l�Ԃ͂��̂܂܂ōK���ł��邱�Ƃ�m��̂ł���B��̗}�����������ꂽ�A���R�̂܂܂̎��������߂����Ƃ��A�l�͉����̂ɂ��ウ������̒��ɋ��鎖�𗝉�����B�����Ȃ�Ǝ��{�Ƃ͂��͂⎄�B����~�]���z����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ邾�낤�B�ǂ�ȂɐS�������鏤�i�����o�������ŁA���B�͂���Ȃ��̂ɖڂ�����Ȃ��ł��낤�B�ǂ�ȕ������A�S���������̂����B���g�̂����ɂ���ȏ�A�����������i�ɂǂ�Ȗ��͂������͂��Ȃ��̂��B���B�͂��łɖ{�����������o�������ڂ������Ă���̂ł���B
�@���i������Ȃ���A�ł����~�Ȏ��{�Ƃ��A�������Ă܂Œn�����������낤���B�ނ͎���̋��~�Ɋ|���āA���Ƃ��k�����邾�낤�B�ނ͈��ӂŎ��R��j�Ă���̂ł͂Ȃ��B����������Ă���̂͂܂��ɔނ̗~�]���̂��̂Ȃ̂ł���B
�@�l�Ԃ̗~�]�͒m���𑝂₹�Α��₷�����傫���Ȃ�B�Z�p�����܂���܂邾�����̔�Q�͐r��ɂȂ�B�l�X�͂܂��܂������̐[�݂ɂ͂܂��čs���̂ł���B���X���R�̂��߂��������荞�l�X�̎��ɒB����ƁA�s���������オ��B�ǂ����Ɉ�������ɈႢ�Ȃ��B�l�X�͈���\���n�߂�B���������Ƃ͉��Ȃ̂��B
�@�ڊo�߂Ă݂�A�����Ɉ��ȂǂƂ������̂͂ǂ��ɂ��Ȃ��������ƂɋC�Â��B�������{�Ƃ������Ƃ��A�����Ĕނ�ɉh�{��^�������ė������B���A�����~�]�ɂ��A�A���̖������Ă����ɉ߂��Ȃ������̂ł���B
�@�l�ނ͍��⎩��̋����ɋC�Â��A���݂Ƃ��Ă̎��A���Ȃ킿�ϏƎ҂ւƊo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���₻�̎��ɗ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̂Ƃ���A���������ŏ��������Ƃ͊��ɘV�q�̌��Ƃ���ł���B�����ɂ��̉ӏ������p���Ă݂悤�B
���o��ҁA��O����
���̏�͖��ׂɂ��āA���i�����j���ׂ�����͖����B
�A�Ⴕ�\����������A�����A���Ɏ������牻����Ƃ��B
�����ė~������A��ꏫ�ɂ������ނ�ɖ����̞����Ȃ��Ă��@��Ƃ��B�����̞��́A�v�ꖒ�����ɖ��~�Ȃ��Ƃ��B
�~�������ĈȂ��ĐÂȂ�A�V���͏��Ɏ��������܂��Ƃ��B
�@�Ƃ���Ől�ނ��o���������A�Љ�̕ϊv�͎��R�ɋN���邪�A���̌�ɏo������Љ�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��낤�B�{�_�̍Ō�ɁA���̂��ƂɐG��Ă��������B
���͐�Ɏ��؎�`�̔j�]���q�ׂ��B�����Ę_���v�l�̋��\�������x�ƂȂ��_���ė����B����������͐l�ԂɂƂ��Ĉ����ƌ��������Ƃ͂Ȃ������B�_���v�l�͌��ǂ̂Ƃ��낱�̒n�������j�Ă��܂��قǂɐl�Ԃ�\�������͂���B������������܂����R�Ȃ̂ł���B�@�n����j��܂łɁA���E������������̂́A�l�ԂƂ������̖̂{����m��ʂ܂܂ɁA�����̒��Ř_���𑀂邩��ɊO�Ȃ�Ȃ��̂��B
�@�����Ď��B�͘_���v�l�z���āA���߂Ċo������̂��������A����������ƌ����ĊϏƎ҂ɘ_���v�l�����͂�܂�ė��Ȃ��ƌ����̂ł͂Ȃ��B���]�͂ނ���Љ�I�ȋ`����ӔC���玩�R�ɂȂ�A��Y��}������������鎖�ɂ���āA�{���̔\�͂�����悤�ɂȂ邾�낤�B�_���v�l�͓��R�����Ɍ����̂ł���B�܂��ɓ��]�͓��]�{���݂̍���ő��݂���B�ϏƎ҂͎v�l����A�C�Â������S�ɕ������Ă��邽�߂ɁA�v�l�̎����\��^���ƌ��܂��������Ȃ��B���̂��߂ɁA���܂�Ă���v�l�̌��p���������o�����Ƃ��ł���̂��B
�@�{���̎v�l�͎��R�̗���Ɩ��ڂɂȂ����Ă���B�o�����邱�Ƃɂ���āA�v�l�����̖{���̎p�̂܂܌��߂�Ȃ�A���̗���͎��Ȃǂƌ����A�����ۂ��Ȃ��̂Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̉F�����̂��̂̎v�l�ł��邱�Ƃ��������Ă���B�v�l�͂܂��Ɏ��R�̈ӎu�̌��ꂾ�����̂ł���B
�@�����炱���A�ϏƎ҂ɋN����v�l�́A���ꎩ�̂��P�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B
�@���B�͕��ʁA�����ɋN����v�l���A���̂܂܍s�ׂɒ��������邱�Ƃ��o���Ȃ��B���ꂪ�P�������f����A������l�i�̃t�B���^�[��ʂ��Ȃ�����̎v�l���M�����Ȃ��̂ł���B�����Ă��̎v�l�Ǘ��̍s���͂����l�������Đl�i�҂ƌĂсA�v�l�̂܂܂ɐ�����l�̏�ɒu���B�����Ă��ꂪ���S�ȎЉ�ƍl����̂ł���B
�@�������ϏƎ҂͂���Ƃ͑S���t�̎Љ����������B�v�l�̂܂܂ɐ�������̂����P�ł���A�v�l�ɑ���^�����̂Đ�Ȃ��҂́A���R�̗����j��ł���҂ƌ��Ȃ����B
�@���B�͑O�͂Ŏv�l�n�}����������A���̂悤�ȕ������ꂽ�v�l�͂����ɂ͖����B�v�l�n�}�̋��E�������ׂĎ�苎�����v�l������n�߂�̂��B�̂̋��X�܂Ŋo�����N����A���B�͉Ԃ�����Ɠ����ɂ��̍����k���A���̐����B�G�߂�̊��������ɐ����̉̐����B�Ԃ���ޑ�n�̐U�����A��Ԓ��̐��ޑ�C���ċz���A����ɑ����F���̔g�������B�g���͑̓��ɐ��ݓn��A���̂����Ƃ��[����������V���Ȑ����̋����N����B�g�����S�g�ɍs���n��A���ׂĂ̊��o���ڂ��J���B�����Ĉ�u�ɂ��ꂪ�N�����Ă���B���̑̌������������ł���A�{���̎v�l�̎p�ł���B�v�l�𐧌����Ȃ���A���̑S�g�ɋN����g���̗���ɏ���āA���]�������B�܂��ɉF���I�Ȑ����̋��߂�܂܂ɗ��O�v�l�����ݏo����čs���̂��B�����Ɏ��R�̂܂܂́A�l�Ԃ̍s�ׂƎp�����O���A�������B
���͂�l�́A�����̓��ɐ��܂��v�l��s�ׂɖ����Y�܂���邱�Ƃ͖����B�l�͂������R�̒��ŁA�S�Ă̂��̂Ƌ�����������̂܂܂ɐ����čs���̂ł���B�����Ɏv�l�̑��݂���Ӗ����������̂ł���B
���@�� ��
�̂��Ă�Ă�n�F���_���I����ɂ�������
�@������\��̂����������A�����̖������āA������������߂Ă��������̂��̂��Ă�Ă�n�F���̌��^�ɂȂ����B���̔��z���܂����R�̂܂܂ɂ���ė����v�l�ɊO�Ȃ�Ȃ��B
�@���͂�������ė���v�l��߂炦�邾���ŁA�_����P��o�����Ƃ͌����Ă��Ȃ������B�K�^�������̂́A���̓��]�����_��P��o�����ɂ͗D��Ă��Ȃ������ƌ��������낤�B
�@���͂�������������Ȃǂƌ������p�̊���������ď����Ă���̂ł͂Ȃ��B
�@�قړ�\�N�ɂ킽���āA���͎����̎v�l�ɐ����t�����A�����v�����܂܂ɂ��̂���ė���v�l���������߂ė����̂ł��������B���ꂪ��̂܂Ƃ܂�ƂȂ����̂́A�����炭�A����ė���v�l�Ɏ�������Ȃ��������炾�Ɗm�M����B
�@�v�l�͂�������ʂ蔲���ė����ɉ߂��Ȃ��B���͎v�l�̌�ʐ����͂�����������Ȃ��B���������̒m���������ׂɁA����ȏ�͂ǂ����邱�Ƃ��o���Ȃ������̂ł���B
�@���������Ă��̈�A�̕����ɂ͖�������������܂܂�Ă��邾�낤�B���������A�����ς��̎v�z�Ƃ������Ȃ�A���̖����̑O�ł�������ł��܂��āA��ɐi�߂Ȃ����������m��Ȃ��B
�@���d�ɂ����͂���Ȏ��ɂ͂����܂��Ȃ��ɁA�c�_���d�˂ė����̂ł��������A�����Ɏ����āA���͂��̎v�l�̖{�������Ɍ������Ă����̂���������悤�ɂȂ����B
�@�l�Ԃ͊F�A�o���Ɍ��������Ƃ��鑶�݂Ȃ̂��B���B�ɉB����Ă���^���͂��ׂĂ��o���Ɍ��������Ƃ��闬��������Ă���̂��B�l�͂����A�����Ɏ���̓��Ɍ��������̐������Ƃ���Ȃ�A�K�������Ɋo���Ɍ���������������B�{���͂��̈��ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�@
���̏������ƌĂׂ����̂��͕�����Ȃ��B����͎��������ƌĂ�ł����̂�������Ȃ��ƌ����̂Ɠ����Ȃ̂�������Ȃ��B
���������邱�Ƃ́A����͎��̎v�l�̕ϑJ�����������̂��Ƃ������Ƃł���B���s������J��Ԃ��āA�悤�₭���ǂ蒅�����C�Â����ϏƎ҂̎����͊m���Ɏ����̎����ł���B���͍����̎��o�Ɗo���̊Ԃ�g�ł��̏�ɂ���B�ϏƎ҂̐��E���_�Ԍ����Ƃ��A���z���璷���N���������ď����A�˂ė������̖{�����A�o���̉��ł́A�قƂ�ǖ����l�ł��鎖�ɋC�Â����B
�@���̋C�Â����A���̂����܌����ϏƎ҂̐��E�̐^�������ؖ����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
�@�{���́A���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��āA�o���Ɏ����q�̂悤�Ȃ��̂������̂ł���B�o���Ɏ������͂������p�̒����ɉ߂��Ȃ��B
�@���̈Ӗ��Ŏ��͎����̂��̎v�l�ߒ������̂܂������Ƃɂ����̂ł���B�t�قȘ_���W�J�▵���͎蒼����������ǂ��̂�������Ȃ����A����������ł́A�_�����ɂ��Ď����̂Ă邱�Ƃɐ��肩�˂Ȃ����낤�B�g���Ă炤�����A�H�����v�l�̓���L��̂Ɏ������Ƃ̂ق����ǂ�Ȃɑf���炵�����낤�B�݂��ڂ炵���p�����Ă��Ă��A�����Ɏ����n������Ȃ炻��͂���Ȃ�ɖ{���Ȃ̂ł���B�@�ނ��뎄�́A���̎��s����ƒt�ق��̒��ɁA�ǎ҂�����̎v�l�����荞�߂�\�������߂����̂ł���B
�l�Ԃ͖{���͋ꂵ�ޕK�v�Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��̂��B�����Ă��̗��R�����݂��Ȃ��B�K�N���K�N�ł���悤�ɁA���͒��ł���悤�ɁA�l�Ԃ͐l�Ԃł���悤�ɍ���Ă���B�l�͂�����l�̐l�Ԃł�������̂��B���������ɂȂ�̂ł͂Ȃ��B���������ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��Ȃ��B�l�͂����A�����̈�u�����ׂĂȂ̂��B�g�����`�����ӔC���A�w����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�ׂ͂��ׂċ��\�ł���B���邪�܂܂̐��������^���ł���A���̐��ɗ����Ԃ鎖���o���ł���B
���͌|�p�Ƃ�W�Ԃ���l��ł��邪�A���̂悤�ɕ����𑀍삷���Ƃ�������������n�߂Ă����B����Ί����v�l�Ƙ_���v�l�����݂ɓ����Ď����n���ւƓ������̂�������Ȃ��B���ɂƂ��Ă���͑o���̑��̂悤�ɕK�v�Ȏv�l���@�������̂ł���B
�@�_���v�l�͋��\���Ǝ咣�������A������������������Ƃ��Ɣ��f����̂͑�ςȌ��ł���B���\�͗��Ƃ��ׂ������A���ł͂Ȃ��B�ނ��눫�Ƃ������̔��f�����������ƒm��ׂ��Ȃ̂ł���B
�@���悻�l�Ԃ̓����琶�܂�Ă�����̂ɕs�K�v�Ȃ��͉̂����Ȃ��B�Ⴆ��Y�́A�g�̂̒ɂ݂ƑS���������������Ă���B��Y�͂܂��ɕs���S�ȐS���C�Â����悤�Ƃ��鎩�R�̉c�݂Ȃ̂ł���B�����Č��S�Ȑ����ɂ͋�Y�͌����Đ��܂�邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B
�@���\�͂₪�Ċo����U���B���S���͂܂��ɂ������琶�܂��̂ł���B�v�l�ɂ��Ă̒T���́A���ǂ��̂悤�Ȍ`�Ő^���ɍs���������B���͂����m�M����̂ł���B
�@�v�l�͌��߂邱�Ƃɂ���āA�������������߂��B�C�Â����̂��̂̒��ɐg��u���A�ڂ܂��邵���ϓ]���Ă����v�l�́A�^���̂悤�ȍ��_�͂Ȃ��Ȃ�B�����ɐ^�������̐��̂悤�ɋP���n�߂�̂ł���B
�@���̐��̌��̌��ŁA���͂���܂łɂȂ����났��̌������B�����Ă��̂��났�𒆂��璭�߂�A����͊m���ɒm���������ė���̂ł͂Ȃ����Ƃ�������B���났�Ƃ͎��݂̑̊��������̂ł���B
�@���̎�����������������Ǝv���B�l�Ԃ͉��̂��߂ɐ����Ă���̂��Ɩ����A�������������߂��Ɠ��������B�����͕������������Ƃł���ɐ[�����킢�ƍ������悤�ɂȂ邾�낤�B�ɕ��f���ꂽ�l�Ԃ͕������������Ƃň�ɂȂ�̂ł���B